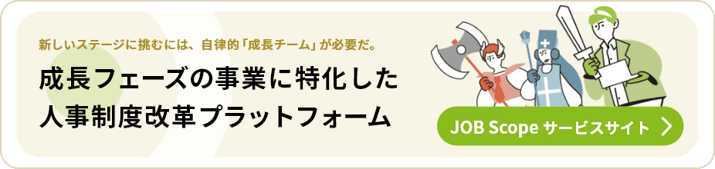多くの経営者が人的資本を「最も重要な資産」として位置づけているにもかかわらず、貸借対照表上では資産として認識されてこなかった。なぜ人的資本が資産計上されないのかという点に問題意識を抱き、いち早く人的資本の本質的な特性をふまえて、人的資本の会計を究明してきたのが、神戸学院大学経営学部教授の島永和幸氏だ。著書『人的資本の会計-認識・測定・開示-』では、人のもつ知識・スキル・能力等に着目した会計のあり方、すなわち「人的資本の会計」がいかにあるべきかを探究している。「日本も人的資本の会計時代がようやく幕開けした」と語る島永教授に、人的資本会計への向き合い方を聞いた。インタビューの前編では、人的資本経営を巡る論点や情報開示の意義を語ってもらった。
目次

01政府主導の下、急ピッチで進められた日本の人的資本経営の情報開示
日本においては、人的資本経営を巡る議論が活発です。どのような論点があるとお考えですか。
わが国において、人的資本経営が本格的に議論されてきたのは、2020年に伊藤邦雄一橋大学特任教授(当時)が取りまとめたいわゆる「人材版伊藤レポート」の公表からという印象をもっています。もちろん、他社に先行して取り組んでいた企業も一部ありました。とはいえ、どちらかといえば、役員への女性の登用や男女間の賃金格差の是正など、法律で開示が義務付けられた内容をどうフォローアップしていくかが多くの企業の関心事であって、自社の状況に合わせてどのように人的資本管理を戦略的に推し進めていけば良いかという議論は未成熟であったように思います。
労働生産人口が年々減少していく中で、各企業が生産性を上げていかないといけないことは自明のこととはいえ、人材を育てる、ウェルビーイング経営(企業関係者の幸せを追求する経営)をする、あるいはリスクマネジメントの観点で、人的資本を全社的にどう開発し、活用していくのかという視点が、欠けていたといえます。
リスクマネジメントの視点からいえば、21世紀に入り、GAFAに代表されるICT企業が顕著であるように、企業の価値創造において「人が大事だ」と指摘されるようになり、さらに人権を巡るさまざまな問題がグローバル企業で出てきました。その後、安倍政権の末期、あるいは岸田政権に入ってから「人への投資」がようやくクローズアップされ、政府の強力なリーダーシップの下、人的資本経営やその開示が推し進められてきたわけです。いわば企業がバリュードライバーとして自発的に人的資本経営を語るというよりは、日本に良くありがちな政府主導型で今に至るというところかと思います。
しかも、非常に短期間の中で有価証券報告書に人的資本の情報を開示するよう進めました。本来なら、人的資本経営が業界や各企業に少しずつ成熟していく中で、人的資本の情報開示のあり方について一定の共通認識が醸成されていくものです。しかしながら、今回は、非財務情報可視化研究会(内閣官房が人的資本など非財務情報についての価値を評価する方法について検討を行い、企業経営の参考となる指針をまとめるために開催した会議体)、等での議論が先行して、開示ありきの結論で制度化が図られました。
一部の企業を除けば、情報開示の義務化に対して人的資本経営の経営実態が伴っていない気がします。従前から自発的に取り組んできた会社からすれば、「ようやく時代が追いついて来た」というところでしょうが、多くの企業はまだ十分にキャッチアップできていません。それにも関わらず、開示もやらないといけないということで、「どう対応したら良いのか」と模索している企業がほとんどだという印象です。

02まだまだ人的資本経営に関する論点が整理できていない
人的資本経営の実現に向けて、何がポイントになってくるとお考えですか。
じっくり考えないといけないと思っています。東証プライムであっても、グローバルで資金調達をしてグローバルに工場があり、グローバルで商品を売っていて人的資本マネジメントも行っているような企業であれば、人的資本経営は非常に馴染みやすいかもしれません。しかし、ローカルなマーケットでビジネスをしている企業、すなわち日本人を対象に商品を売っていて、従業員も日本人、採用マーケットも日本限定の企業だと、海外の投資家に人的資本に対する取り組みを理解してもらう必要はあまりないと言って良いでしょう。
いわゆる、価値創造のストーリーの中で、何故欧米と日本では人的資本が違うのかと言うと、ヨーロッパの場合は人の移動が自由なので、安い労働力がユーロ圏で行き来できます。しかし、日本は米国のように移民を受け入れる仕組みにはなっていません。せいぜい特定技能外国人(国内の人材を確保することが難しい状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人)が入ってくるだけです。労働生産人口が減っていく中で国内の企業が何もしないまま生き残っていくとはとても思えません。そうなった時に、グローバルスタンダードの基準という、人的資本経営をそのまま持ってきても多分、日本人を相手に日本の経営をしていて日本で商品を売っている企業と「伊藤レポート」や「価値協創ガイダンス」(企業と投資家を繋ぐ「共通言語」として、対話や情報開示の在り方の拠り所となる枠組み。経済産業省が策定)などの高いレベルを目指している企業とでは、多分違っているはずです。
東証スタンダードや東証プライムでも、国内マーケットがメインであったり、企業規模が小さい企業もそうですし、さらに非上場企業の場合には、まだ人的資本経営という言葉自体も浸透していないと思います。なので、その辺りの軸で考えないといけません。恐らく、まずは上場企業の中でもグローバルで競争している企業はライバルと目される海外企業と比較をされることがあるので、人的資本経営を議論する余地があります。しかし、そうでない場合は他国との違いを踏まえつつ、日本的な経営の良さがどこにあるのか、何を変えなければ欧米にキャッチアップしていけないのかなどといった論点を整理しなければいけないと思います。その議論がないままに今に至っている気がします。

03情報開示をすることで投資家とのギャップが埋まる
2023年度から上場企業における人的資本の情報開示が義務化されました。開示の意義を解説していただけますか。
大きな枠組みで言うと、米国証券取引委員会(SEC)が2020年に上場企業に対して人的資本開示を義務化しました。その前に、私自身が国内では誰よりも早く紹介していたのが、2018年12月に国際標準化機構(ISO)が発表した人的資本に関する情報開示のガイドラインである「ISO30414」です。実は、サステナビリティ情報(企業が持続可能な社会の実現に向けて行っている活動や取り組みの情報)の中で残されたピースが人的資本の部分でした。環境やガバナンスはもうかなり進んでいて、環境の分野では ISSB(International Sustainability Standards Board:国際サステナビリティ基準審議会)でも基準ができていましたし、ガバナンスではガバナンスコード(企業統治の方針)も作られていました。
しかし、人的資本についてはISSBもこれから議論をしていくというところでした。その中で全体としては、いわゆるグローバル・ベースラインはISSBが作るものの、その上の部分は各国で作っても良いというのが彼らのスタンスだと思います。なので、日本型の人的資本の情報開示がどうあるべきなのかを議論しないといけません。これまで財務会計の分野では貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書と呼ばれる財務情報の開示というもので事足りていました。ただ、21世紀に入ったらそれが通用しなくなってきてしまったのです。
これは、よく指摘されていることですが、日本企業は設備投資や有形固定資産(1年を超える長期に渡り利用される資産)への投資は熱心なのですが、GAFAや海外の大手製薬会社と比較すると人への投資や研究開発への投資は遅れています。ただでさえ、弱かったところに、追い打ちを掛けるように新型コロナウイルスの感染拡大により大打撃を受けてしまいました。
なぜ、日本企業は人への投資や研究開発への投資に積極的でなかったのか。それは、費用が当期の費用に全部なってしまい、貸借対照表上の資産にならないからです。そうなると、当然経営者は自分の任期中には「なるべくストックオプションの価格を上げたい」「経営者としてできるだけ長く務めたい」と思うと、費用を上げたくないので人的資本への投資には、むしろネガティブになってしまうわけです。できれば人を減らしたいというインセンティブが働いてしまいます。
それが、銀行や建設などの業界でのさまざまなトラブル対応の遅れにつながっています。それらが起きた時に朝令暮改のように「ここを点検しましょう」と言っても、組織風土として納期を守ることが優先であれば現場は守りません。守っていたら納期が間に合わない、あるいは残業をしないととても回らないとなると、たとえ今までがそうであったとか、しかも、本来はサービスでコストを発生すべきところを、価格転嫁しないで中小企業に支払いをするようにやってきたわけです。それが今ようやく、労使と政府が価格転嫁をして掛かるべきところにお金を掛けることになりました。人にも回すことができますし、AIや労働サービスにも投資ができるようになったのです。
裏返していえば、これまで人への投資をおろそかにしていたということです。まるでお題目のように人的投資や情報開示と言われようになってきましたが、これまでの財務情報だけの1本足打法ではなく、財務情報で伝えられない部分をナラティブ(物語的)な技術情報やKPI(重要業績評価指標)などを用いて、非財務情報として利害関係者に情報提供をしていく、そういう時代になっていると思います。
今インターネットで探せば、数年で社員が退職してしまうブラックな企業はすぐに類推できます。そうしたKPIの情報が統計的に処理されていくと、「こういう会社はこういうことに投資をしないといけない」「こういう会社はこういうリスクマネジメントをしないといけない」であったり、「こういう会社は恐らく問題を起こして、将来株価を下げることになる」といった因果分析ができるようになってくるでしょう。
「個社性」とよく言いますけども、個社で重要な情報を積極的に開示していくことによって、企業が持っている情報と投資家が持っている情報のギャップが埋まり、不信感がなくなれば、株価も自然に上がっていきます。投資家が過小評価するというのは、やはり会社に対して何らかの払しょくできない不信感を持っているためであると考えられます。そのギャップを埋めていくためには、非財務情報、今で言うサステナビリティ情報が必要なのです。特に今まで価値競争優位の源泉と言われた人的資本の情報が、不足していたにもかかわらず開示していませんでした。それを今やろうとしているところに、重要なトレンドがやって来たという印象があります。これを一時的なものに終わらせてしまうのか、あるいはこれが制度として定着されていくのかは、政府や研究者、あるいは企業がどう知恵を絞っていくかどうかによると思います。

04任意開示と法定開示の役割をわけなければいけない
上場企業における人的資本の情報開示義務化ですが、初年度の取り組みぶりをどう評価されましたか。
既に統合報告書(財務情報と非財務情報を集約した資料)を発行してきた企業が700社ほどあります。そうした企業はそこで作成していた図表を貼り付けたりして、対応することができました。しかし、統合報告書を発行していなかった企業は、急いで対応しなければならなかったということで、温度差があると思っています。なかには、「詳細は統合報告書を参照してください」「サステナブルレポート(持続可能な社会の実現に向けた企業の取り組みを開示する報告書)をご覧ください」といったパターンもあると思います。
やはり、有価証券報告書(事業年度ごとに、企業が自社の情報や経営状況について外部へ開示する資料)と任意開示情報の区分や役割、分担を決めていかないといけません。結局重複して開示すると「有価証券報告書だけで良いのでは」という話になってしまいます。「より重要な情報は有価証券報告書のここの部分に載せます」とか、その辺りの任意開示と義務的な情報開示の役割分担の仕方を考えていかないといけないと思います。まだまだ人的資本やサステナビリティ情報をどう開示していくのかが、日本の会計基準の中では固まっていませんからね。そこは、私も一つの研究対象としています。
人的資本の情報開示は日本企業にどのような影響をもたらすとお考えですか。
投資をしてリターンが得られるというのはわかりやすいです。有形固定資産や原材料は一対一の関係ですから、それでお金を掛ければ設備は増えますし、サービスや製品も提供されます。そういったことは、わかりやすい関係なのですが、無形財と呼ばれる、例えばブランドにお金を掛けたり、あるいは顧客関係にお金を掛ける、技術にお金を掛けても成功しない場合があります。
特に、技術だと「千三つ」という言葉があるように、幾らコストを掛けても千のうちわずかに三つぐらいしか成功しません。何とかそこで儲けて、さらに別の製品やサービスを立ち上げて、それをマネジメントしながら次の戦略に結び付けています。人的資本に関しても、例えばブルーカラーの労働者層に一律で5万円ずつの投資をしたからといって、その金額に相当する収益率が得られない場合もあったりします。
「企業として、今年はここに1億円もの投資をする」と書いてあれば、その中身が問われないといけません。やはり、優先順位を付けて投資をしていくことが大切だからです。人的資本も同様です。企業の特性や優秀な人材を育てるという方針に特化すると、人は替えがつかないわけです。人は仕事を作っていきますし、生み出していくし、イノベーションの源泉になっていきます。それを踏まえて、「こうしたストーリーでいきたい」と伝えた上で裏付けとなるものとして、「これだけの金額を投資する」とならないといけません。それをしないで、単に「一律で5万円ずつ投資します」で果たして効果があるのか疑問です。そのあたりの人的資本における個社性、業種特性を合わせて、人的資本の戦略と実行のPDCAサイクルを上手く回していかないといけないと思います。そこは、恐らく経営者が今までやっていなかったことです。人的資本経営が昔からあったわけではないので、まだまだ上手くフィットできていません。
必ずしもヨーロッパ型や米国型を持ってくれば良いというわけでもないのです。横文字を縦文字に直したら、それでうまくいくというものでもありません。その辺りの開示の仕方を考える必要があります。例えば、「当社のパーパスはこれだ」と掲げて、それに対してこういう人事制度を組み立てているという説明だけでは、実際の活動のストーリーが語れていません。「こういう制度を導入しました」と事実を言っているだけに過ぎないわけです。「将来に向けてうちの会社はこれを目指していくためにこういうことをやっています」と語られないと、恐らく本当の意味での人的資本開示が有効に働いてこないと思っています。

05マクロ経済の中で企業が果たす役割に基づいてジョブ型雇用を考える
ジョブ型雇用に関してはどのような見解をお持ちですか。
マクロ的な視点で見ていくと、例えば派遣や非正規雇用が貧富の格差を生み出しています。分厚い中間層が日本経済を支えてきて、それに対して、例えば高校や大学に進学する、塾に通う、あるいは部活をするとか、そこで人間関係やコミュニケーションのスキルを身に付けるといった余裕を生み出していたはずです。正規雇用の人には賃金アップの効果があるものの、非正規雇用の人は、例えば時間あたりの最低賃金が1000円だとすると8時間働いても8000円、月に20日間働いても16万円にしかなりません。これは、正規社員の初任給よりも低いわけです。しかも、ボーナスもありません。そういう人たちが日本ではかなり多く生まれてしまっているのが現状です。
米国の文献では、「リスク移転」(リスクを第三者に移転すること)という言葉が出てきます。以前は、企業がリスクを負っていました。つまり、解雇するのが難しいから、企業が右肩下がりの時、あるいは赤字経営になった時でも、企業が社会的な安全弁として働いて給料をしっかりと払っていました。例えば、生活保護を払わないといけない、治安が悪化したり、健康が悪化すれば病院にかからないといけないとか、あるいは、本当は優秀な人材であったら大学まで行き、イノベーションを目指す人材になったかもしれませんが、それを諦めざるを得ないということが、子供にも波及してくるわけです。そういったことを考えずに、マクロ的なものとして企業に派遣社員の登用を拡大させる政策を展開することで、結果的に分厚い中間層が失われ、貧富の差が拡大し非正規雇用の人たちに、その企業が元々負担していたリスクを移転していくことになります。果たして、こうした状況が,わが国のあるべき姿として本当に良いといえるのでしょうか。
もう一つは、AIが普及してICT技術を持った社員がかなり必要になって来ています。データサイエンスとか、そういう高度な技術やスキルを持った特定の業種の人はグローバルで引っ張り合いになっています。その一方で、AIやコンピューターによって仕事が奪われる人も出てきます。その人たちに再教育をしたり、あるいは仕事を与えていかないといけません。それが今までのように企業が正社員として採用していれば、他のスキルを身に付けて「こちらの仕事に移ってください」と言えました。それを、「もうあなたたちは仕事がないので終わりです」という形にしてしまうと、その人たちのスキルを磨く場が提供されなくなってしまいます。
今日、ステークホルダー資本主義(ステークホルダーへ貢献するための企業経営方針)の中で、企業が持つべき役割の一つとして、そういったことが期待されているわけです。特に企業が組織と株主のために利益を生み出す株主資本主義(企業経営の目的は株主の利益最大化であるという考え方)でやってきたことを止めて、従業員のためにも企業が社会的責任を果たしていかないといけないということが、改めて見直されていたところにコロナが追い打ちを掛けたわけです。それでも、日本は分厚い内部留保があったために企業が倒産せずに、従業員を雇いながら他の仕事に就いてもらうこともできました。
21世紀において、重厚長大産業のもの作りの時代からソフト化社会へと移っていく中で、今まで培ってきたスキルが通用しなくなって来ています。そうした社会の中でどうやってセーフティネットとして人を救っていくか。それが、単に政府や地方公共団体に依存するのではなくて、そこで出てくるのが地方の労働を支える企業であったりします。単に「儲からないから撤退する」というのではなくて、地域の雇用を守るのも企業に求められる重要な役割といえます。地域を支えるためにはどういったビジネスモデルを構築して上手く回していくかということも、企業として考える必要があると思います。
なので、単にジョブ型雇用だけを取り上げるのではなくて、マクロ経済の中で企業が果たすべき役割と人の採用の仕方、人材育成の仕方とか、その企業では合わなくなってきた人への対応を考えるべきです。例えば、多少の教育を与えるとか、職業斡旋をしてあげるといったことです。
実際、中小企業には大企業で培っていらしたノウハウやコネクションを活かせる機会が数多くあります。人材の流れができれば、中小企業は販路を拡大できますし、技術開発ももっと進むはずです。残念ながら、現状ではそれが上手くいってはいません。その辺りの人的資本の開示、いわゆる「こういう人材を募集します」「こうしたポジションが足りていません」ということを中小企業を含めて、もっと多くの企業が開示していけば、上手く人材の流動性が高まり、経済全体として労働力不足やミスマッチを解消できるのではと思っています。そこに人的資本の開示の役割もあるのではないでしょうか。

島永 和幸氏
神戸学院大学
経営学部 教授
1975年長崎県生まれ。1998年長崎大学経済学部卒業。2003年神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了(博士(経営学))。2003年神戸大学大学院経営学研究科 助手、2004年神戸学院大学経営学部 専任講師、准教授を経て、2019年より現職。専門は、人的資本会計、サステナビリティ基準、国際会計。とくに、人的資本の開示や会計問題に関心を持つ。主な著書に、『人的資本の会計-認識・測定・開示-』(同文舘出版、2021年)がある。同書にて、グローバル会計学会2020年度学会賞(2021年)、日本公認会計士協会学術賞(2022年)受賞。