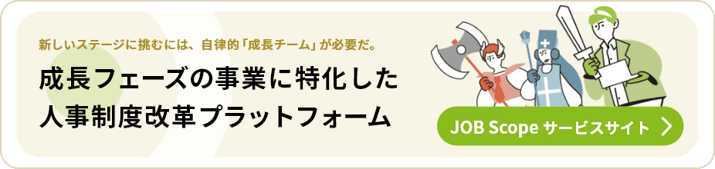人的資本マネジメントの目的は、事業ポートフォリオの再構築にある(後編)
日本企業の最大の問題点は、「事業ポートフォリオの組み替えが進まないことである」と指摘されているのが、一橋大学大学院経営管理研究科 教授の円谷 昭一氏だ。「成長分野に人材を異動させ、変革を進めていかなければいけない」と主張する。金融庁が策定するコーポレートガバナンス・コードに織り込まれている「人的資本」の意味合いも同じ方向性といえる。「人的資本は人事の問題でも開示の問題でもない。あくまでも経営の問題である」と強調する円谷昭一教授にその本質を聞いた。インタビューの後編では、日本企業における情報開示の現状や統合報告書の位置付けなどについて語っていただきました。
インタビュー前編を読む
目次

01ポートフォリオ戦略と人事戦略は合致せざるを得ない
人的資本経営の実現に向けてポートフォリオ戦略と人材戦略をいかに合致、連動させていけば良いのでしょうか。
まずは、前提としてポートフォリオの組み換え戦略が上にあって、必然的にそれを行うために、その下についている人を動かすことが不可欠になってきます。なので、連動するというよりも経営戦略をしっかり定めると、人をどうするのかという話が当然出てきます。そんな関係です。
恐らく、日本の大手企業は今でも資源配分上、不採算事業に資源が投下されていて、そこに人が配置されていると思います。なので、組み替えを行うとなると「ここにいる人をどこに移すのか」という議論が出てきます。必然的に人的資本経営が求められてくるので、もう経営戦略を定めるとその下の事業にいる人をどう活てくるわけです。やらざるを得ないということです。
日本企業の経営者に人的資本経営や人的投資の重要性が着実に定着してきているとお考えですか。
これも先ほどのお話と全く一緒です。「このままの事業のポートフォリオだと10年後、20年後は無理だ」という意識を持って事業の組み替えを考えている経営者であれば、もう当然、人的資本をどうするかといった意識も持っていると思います。だから、経営の組み替えを進めている会社は、もう否応なく人的資本をどうするのかという議論に巻き込まれるので、そういう意識を経営陣が持っています。
逆に、そうではなく経営の組み換えのことはあまり考えていないが、「人的資本はやろう」という会社は、ある意味働き方をどうするかとか、ダイバーシティをどうするかという議論で人的資本を捉えているので、捉え方が違ってくると思います。この点、どうしてもマスコミを含め世間は、一緒に捉えてしまいがちですが、もちろんどちらが良い悪いというわけではありませんが、前者と後者では捉え方が違ってきます。

02情報開示は勇気と決断。法律で求められているからではない
円谷先生は、IRを中心としたディスクロージャーを研究されてらっしゃいます。日本企業における情報開示の現状をどう捉えておられますか。
従来までの有価証券報告書においても、いかに法令に従って瑕疵がなく、いわゆる誤りなくフォーマットに則って書くというのがディスクロージャーで重要だったわけです。その意識が今でも残っている中で、法令で求められないことは書く必要がないのではという発想が当然あります。株主総会の招集通知でも有価証券報告書でも、法令や証券取引所、業界団体などが作ってるフォーマットに流し込めないようなものは開示する必要がない、そういう発想の中で考えると、「法定開示でなければ出す必要がないのでは」となりがちです。しかも、「自社にとってあまり良い情報ではないのであれば出す必要ない」という会社がほとんどだと思います。そうした中で自社にとって不都合な情報であっても出していくというのが、“勇気と決断”だと言えます。
米国やヨーロッパの企業は、そういう形式に流し込む開示は基本的にはしていません。あくまでも、自社にとって何が必要な開示なのかを考えるという姿勢でやっているように思います。なので、そこは何とも言えません。日本固有の開示制度の仕組みがまだ引っ張ってしまっているので、それを持って「日本企業が紋切型だ」と非難するのは酷かなという気がします。
従って、女性活躍を開示しなさいと言うと、自動的に女性管理職比率になってしまいます。何故なら、女性管理職比率が法定開示の項目に入っているからです。また、男性の育休取得率も法律で求められた開示項目に入っているので、それをそのまま全部出せば、人的資本開示は終わりだと考えているであろう会社も散見されます。当局がそれを求めていたという歴史があるからです。なので、何ともそこは難しいところではあります。
―2022年度決算から上場企業では、有価証券報告書へのサステナビリティ情報の開示が義務化されました。これも、法定開示だからやるしかないという対応では問題ですね。
そうですね。ただ法定開示の部分は今でも残っているわけです。いわゆる形式に則って書かなければいけないわけです。それにプラスして「任意開示もやりなさい。そちらは自分で考えてください」ということです。要は、頭の使い方が異なる二つの開示を同時にやらないといけない状況にあります。簡単に言うと今までの形式開示に自分で考えなければいけないサステナビリティ開示が乗ってきたということです。違う頭の回路が必要なものを同時に二つ求めていて、量も倍増しているので現場はほぼ限界に来ています。「正直、何をやったら良いのですか。どちらを重視すべきですか」と悩んでいて、「取り敢えず求められたことを作文しておけば良いのでは」みたいな感じの開示が増えてきてしまっています。
そろそろ、どういった方向でこの国の上場会社における開示の舵を切っていくのか、作らなければいけない開示資料は何か、その取捨選択といいますか、スクラップアンドビルドが必要だと思います。また、有価証券報告書の開示にしても、今まで積み上げ積み上げでやってきていたところに、さらにサステナビリティが積み上がり、「これについては今までと違う発想で作ってください」「自分の言葉で書いてください」と言われても、一部の大企業を除けば多くの上場会社にとっては相当にハードルが高いと言わざるを得ません。
スポーツで譬えるならば、「監督に従いなさい」と言いつつも、その一方では「自分で判断しなさい」と言う。その二つを同時に求めているようなものです。選手からすれば、「どのぐらい監督に従ったら良いのですか」「自己判断をどれだけすべきですか」「自己判断して、それが失敗となった時に監督にどのぐらい怒られるのですか」…。その辺りが曖昧なまま突きつけられてしまっているので、そのしわ寄せが開示担当者に来てしまっています。

03統合報告書で何を伝えるのか。その思いが制度に関わる
円谷先生は、「第3回日経統合報告書アワード」の副審査委員長をお務めになられました。各社の取り組みぶりをどう評価されますか。
だいぶレベルが上がってきているというのが、私だけでなく審査員全員の印象だと思います。ただ、統合報告書はそもそも欧米企業では日本企業ほどは作ってはいないのです。実は、世界で最も有名な株価指数であるNYダウ工業株30種に名を連ねる全米トップ30の会社でも、統合報告書を作っているのは数社ぐらいしかありません。いわゆる、既存の情報開示資料では書けないような重要な情報を新たに別媒体を作ってそこで開示しているわけです。例えば、製薬会社であれば新薬の開発状況やその新薬によってどれだけの人が幸せになるのかといった情報です。それらは既存のアニュアルレポートとは別媒体にした方がかえって世の中には響くかもしれません。既存の情報開示資料に書けるのであれば、無理して統合報告書を作る必要はないのです。なので、欧米で統合報告書を作っている会社は日本ほど多くはありません。
日本はそうではありません。上場会社4000社のうち、1000社に迫る企業が統合報告書を作っていると言われています。これほど作っている国は、世界の中で日本だけです。しかも、何かを伝えたいがために、任意開示資料である統合報告書を新たに作っているわけではなくて、多くは「他社が作っているから」という理由で「自社でも作らないといけない」と考えているのです。「伝えたいことがあり、それをうまく伝えるための媒体を新しく作りました」という欧米と、「他社が作っているので作りました」という日本型の統合報告書では、自ずとメッセージ力が違ってきます。そういう意味では、日本におけるほとんどの統合報告書は、本来の統合報告書ではなくて、色々なところに散らばっている情報を集めて一つにまとめた集合報告書みたいなものであって、そこにはあまりメッセージ性がなかったりします。
と言っても、一部の企業は統合報告書の意義に気づいています。当然ながらそうした気づきがあって、「これを伝えたい」という想いがある会社は、統合報告書の精度がすごく高いです。その数は50社ぐらいでしょうか。そうした会社が、「日経統合報告書アワード」の2次審査にリストアップされてきます。なので、上位50社に関しては進化が目覚ましいものがあります。
何のために統合報告書を作るのか。改めて問い直す必要があるということですね。
これは、統合報告書に限った話ではありません。最初にはなりたくないけれども、最後にもなりたくない。それが、経営者のメンタリティなのだと思います。なので、経営陣は「予算を付けるから開示部門で統合報告書を作るように」と指示します。そして、開示部門となるIRや経営企画などの部署は、支援会社から企画を出してもらって、そこに微修正を加えるという流れになりがちです。結局、会社として何を伝えたいのかが見えないという、「負のサイクル」に陥ってしまっています。
最近は、統合報告書を学生にも読んでもらいたいと考えている企業が多いと聞きました。どうなのですか。
多いですね。就職活動を進めるにあたり統合報告書に目を通しておこうという学生も増えて来ています。なので、私のホームページでは、「学生による統合報告書感想プロジェクト」を展開しています。ここでは、学生一人ひとりに一社を割り当てて、その会社の統合報告書を読んだ感想を発表してもらいます。もう百社ものレポートが掲出されていて、「もう少し詳しく知りたいので学生に来てもらって話を聞けないか」という依頼も企業から寄せられています。なので、今年も実施したいと思っています。
「学生による統合報告書感想プロジェクト」
http://tsumuraya.hub.hit-u.ac.jp/special03/index.html

04社会全体でリスキングの枠組みを構築する必要がある
近年は、リスキリングも注目されています。円谷先生も「リスキリングは一企業の枠を超えて、社会全体でリスキリングの枠組みを構築する必要がある」と指摘されています。その意図を教えていただけますか。
テクノロジーが大きく進歩する中、例えばエンジンの技術者をどうやって再配置するのかは、一自動車メーカーだけの問題ではありません。自動車業界の各社が抱えている共通の課題です。なので、1社1社でリスキリングをやっていても非効率です。全部を合わせて国がやった方が良いのです。
実際、シンガポールではそれをやっています。「スキルズフューチャー運動(Skills Future)」と題して、国民向けの生涯職業能力開発プログラムが展開されているのです。リスキリングの仕組みでもあると言って良いでしょう。
このプログラムのアニュアルレポートを見ると、そのスキルの汎用性という軸と将来需要という軸、そもそもそのスキルが求められる求人数の三つがグラフで表示されています。「このスキルは、この職業でもこちらの職業でも使えるとあって汎用性があるけれども、将来需要はあまりない」といったことを国が見える化しています。しかも、この職業に就くためには、こういったスキルが必要でそれをどこで習得できるか、幾ら掛かるかもわかるようになっています。
さらに、スキルズフューチャーで特徴的なのが「スキルズフューチャー・クレジット」という仕組みです。国民は、25歳になれば一定額のクーポンをクレジットとして支給され、それを使ってスキルを習得していけます。それだけでなく、40歳になるとまたクーポンが支給され、リスキングができるようになっているのです。
こういう仕組みが国として出来上がっているのは、日本にとっても参考になると思います。リスキリングの分野によっては一社が単独で取り組むよりも、社会的な効率性が高いと思うので、構築を検討してみてもよいかと思います。

円谷 昭一氏
一橋大学大学院経営管理研究科教授
2001年3月一橋大学商学部卒業。2006年3月一橋大学大学院商学研究科博士後期課程を修了。商学(博士)を取得。埼玉大学経済学部専任講師・准教授を経て、2011年4月より一橋大学商学部教授に就任。2021年より同学経営管理研究科 教授となる。2007年より日本IR協議会客員研究員。2020年より金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」委員。研究領域は、企業のInvestor Relations(IR)を中心としたディスクロージャーにある。とりわけこれまでは業績予想情報、セグメント情報などに焦点を当てた研究を行ってきた。現在は政策保有株式情報などを用いて、ディスクロージャーとコーポレート・ガバナンスの関係について研究を進めている。著書に「政策保有株式の実証分析: 失われる株式持合いの経済的効果」(日本経済新聞出版)、「コーポレート・ガバナンス「本当にそうなのか?」2 ―大量データからみる真実―」(同文舘出版)などがある。