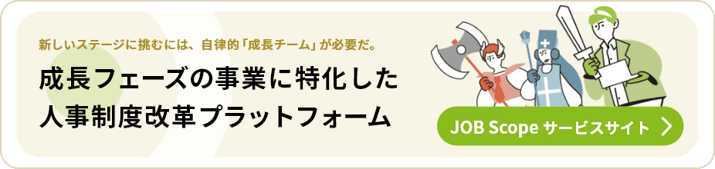トレンドに惑わされず、本質を見極め自社にとっての最適解を導く(後編)
世の中には、流行廃りがある。ましてや、スピード感が加速する現代では、そのサイクルが劇的に短くなってきている。それは、経営や人事の領域でも同様だ。「人的資本経営」や「ジョブ型雇用」などの言葉がもてはやされ、その本質や何故今重要なのかを理解せず、盲目的に追随していないだろうか。こうした中、「トレンドとして定着しつつある段階こそ、深い洞察が必要だ」と指摘するのが、早稲田大学 大学院経営管理研究科の竹内 規彦教授だ。組織行動論の第一人者としても国内外で広く知られている同氏に、企業経営者や人事責任者が今留意すべきポイントを聞いた。後編では、組織行動論の概要や新人やシニア育成の課題と提言などを語ってもらった。
目次
- 日本社会がジョブ型雇用にかたむくことはない
- 組織における人々の行動を可視化する「組織行動論」に注目
- 個を尊重した新人育成とシニア世代のモチベーション向上が重要
- 自社の経営に何が求められているのかを真摯に考えよう

01日本社会がジョブ型雇用に傾くことはない
ジョブ型雇用に関してはどのような見解をお持ちですか。
歴史的に見ると、メンバーシップ型かジョブ型かというトピックが周期的に社会現象化しているように思います。言葉はその時々によって変化するのですが、私にとって最も印象的なのは今から20年ぐらい前ですね。ブームになった成果主義か年功かという議論です。根底にあるのは、やや乱暴な分類かもしれませんが、人事の経営手法において日本型か米国型かどちらを採用すべきかということが問われるようなタームが周期的に訪れているような感じがします。
成果主義は人材の評価や報酬面でジョブを明確にすることを前提として、ジョブの中での報酬の序列化を行うというのが、基本的な考え方だと思います。一方で、ジョブ型雇用は、採用の場面により特化しています。職務内容や経験、スキルや資格要件を明確にして、特定のジョブに限定した雇用を行うことが基本だと思います。
メンバーシップ型雇用はよく「就社」と言われます。これに対して、ジョブ型雇用は文字通り「就職」です。ある意味、就職という概念を取り戻すというか、本来の就職のあり方に近づいていくというのが、ジョブ型雇用だと解釈できます。
ただし、最近ではジョブ型かメンバーシップ型かというのは、採用や雇用という場面に限定せずに、先ほど私が申し上げた、「米国型」か「日本型」かといった組織の編成原理全般を指しているようにも見受けられます。
ジョブ型雇用は今後、日本企業に広がっていくとお考えですか。
これも20年前の成果主義の例に照らすと、成果主義は2000年代前半に一部の記事や書籍で取り上げられて瞬く間にブームとなりました。かつての未曾有の経済成長から一転してバブルが崩壊したおよそ10年後、失われた10年と良くいわれた時です。一昔前まで米国で称賛されていた日本的経営に産業界が自信を失っていたことも、成果主義がブームとなる背景にあったかもしれません。しかし、成果主義はメディアでこぞって取り上げられた数年後には、批判する本が出ることがあっても、それ以降話題にはならなくなりました。実際に、企業で成果主義を導入したけれども、短期間で止めてしまったり失敗に終わってしまったというケースが多数散見されました。
これは、前編でご説明した「マネジメント・ファッション」のサイクルそのものだと思います。今回のジョブ型雇用に関しても、同じ流れをたどる可能性は否定できません。コロナ禍の中で、個別的な働き方へのシフト化や、自身のキャリアに対する危機感を持たれる方々が増えたと実感しました。そういう意味では、コロナを契機として、メンバーシップ型雇用のデメリットに目が向きやすい社会的な条件が整えられたのかなと思います。こうしたところに、「ジョブ型」が心地よい言葉として受け入れられる心理的素地ができたものと考えられます。
ただ一方で、今回のジョブ型の議論は、必ずしもジョブ型が是でメンバーシップ型は非だとステレオタイプ的な視点で企業や社会が捉えているわけでもないようです。少なくとも私が日々接している実務家や経営者の方々の声を聞くと、ジョブ型について皆が賛成かというと、必ずしもそうではないですね。
つまり、現在のジョブ型の議論は賛否両論が伴っていて、かつての成果主義の時のような勢いはないと思います。加えて、ジョブとメンバーシップのハイブリッド型の導入を検討している企業も少なくありません。そう考えると、企業や経営者が自社に合った形での導入を検討しているのであれば、社会全体がジョブ型に傾くとまではいかない気がします。

02組織における人々の行動を可視化する「組織行動論」に着目
竹内先生のご専門である「組織行動論」とは、どのような学問なのですか。
「組織行動論」は、元々米国で誕生し発展している学問です。今世界的にも広がっており、日本でも研究されています。ヨーロッパや他のアジア諸国でも非常に盛んに研究されている分野です。平たく言えば、組織の中での人間行動を意味します。組織における人々の行動をより正確、かつ的確に理解し、それに合わせたマネジメントを考えていくというのが、組織行動論のエッセンスになります。
特に人文系や社会科学系の研究は、どちらかというと個別のケースや事例を定性的に研究することが多いのですが、組織行動の研究に関しては心理学との関係が非常に強いです。ご存知の通り、心理学は実験や定量的な研究が中心です。人の心を定量化して、それを解析するという手法を用います。なので、組織行動論も定量的な実証的研究が主流となっています。
要約しますと、職場や組織の中での人間行動を定量的に測定し、可視化し、それを丁寧に活かしていこうという学問だと言えます。
組織の中での人間行動を可視化することで、従業員のモチベーションアップやチームビルディングに役立つということでしょうか。
必ずしもモチベーションやチームビルディングだけではありません。リーダーシップでもそうです。組織の文化を測定したり、あるいは個々人のストレス・チェックなどを通じて潜在的な課題を可視化することによって、組織や個人の課題を発見し解決につなげていきます。
「組織行動論」の重要性を経営者の方々にも認識してもらいたいということですね。
そうですね。ただ最近は、企業側もデータドリブンの視点をお持ちで、定量的な課題発見や解決の取り組みには積極的という印象を持っています。昔は、「調査をさせてもらいたい」とお願いしても、なかなか対応してくれませんでした。しかし最近は、企業側から「社内の状態を可視化してもらいたい」というニーズがかなり増えています。この10年ぐらいで雰囲気が変わりましたね。可視化することのメリットをご理解いただいているのかなと思っています。
人事部門もデータを重視する傾向が高まっているということですね。
そうだと思います。例えば、人事部の中でも、社内のデータ分析に関する業務をされている方が結構おられます。アナリティクスというか、分析のスキルも上がってきていますね。我々のビジネススクール(早稲田大学ビジネススクール)でも、企業データ分析の授業が選択必修科目として用意されています。私の社会人MBAのゼミでも、社内での調査票の設計からデータ収集、統計分析、報告書の作成や論文化の仕方まで、一通りのスキルを習熟できるコンテンツにしています。私が感じる限りでは、データに対するアレルギーはだいぶ少なくなってきています。

03個を尊重した新人育成とシニア世代のモチベーション向上が重要
竹内先生は、新人の育成やシニア人材の活用についても研究されています。それぞれに関して現状どんな課題があるとお考えですか。その解決策もご提案いただけますか。
まずは、新人の育成に関しては、個の尊重がキーワードです。従来までは、新人育成は、特に会社へのオンボーディングの面では、組織から個人へ価値観を刷り込んでいくことが中心だったと思います。オンボーディングとは、新人が入社後に組織の一員として育っていくプロセスを指しますが、実は、導入教育や研修による組織主導型のオンボーディングだけでは限界があることが、私の研究を含め最近の新人育成の研究で明らかになってきました。
より効果的な手法はないかということで、私は新人主導型のオンボーディングを組み合わせて実施するよう提案しています。新人が育っていくプロセスには、組織から育てられる側面と自ら育つ側面の両面があります。つまり、会社主導、組織主導で育ててもらうアプローチと、個人ないしは新人が自ら主体的に育っていくアプローチの両面があるということです。とはいえ、「自ら勝手に育ってください」と新人を突き放しても新人は育ちません。自律性を言葉で押し付けるのもナンセンスです。
新人主導型のオンボーディングを促す1つの手法として、自ら積極的に育つきっかけ作りがあります。例えば、新人に対するメンタリングや1on1などがそのきっかけとなるケースは少なくありません。ポイントは、「個人が尊重されている」と感じる支援をすることです。これを少し理論で裏付けますと、人は他者から個人として認められたいという普遍的な欲求を持っています。「他人から自分を良く見られたい、高く評価してもらいたい」、そういう欲求です。これを心理学では自己高揚欲求やセルフ・エンハンスメント・ニーズと呼んでいます。会社から個人が尊重されているという感覚により、この自己高揚欲求は満たされていきます。すると、自ら積極的に会社に貢献しようと努力したり、仕事に楽しんで臨んだり、あるいはリテンションの意識が高まっていく、こうしたメカニズムがあるのです。
これは、実際に我々が、新人の入社から約10カ月間、彼・彼女らの態度や行動を定点観測で調査・分析をしてわかったことです。最終的に仕事を楽しんだり、あるいは会社に貢献しようという気持ちが高まっている人たちは、あるタイミングで、自分が会社から個として尊重されて認められているという意識が高まった人たちでした。つまり、マスで管理するという手法だけではなく、新人一人ひとりに対して個別的な対応・支援を行うことが、オンボーディングには効果的といえるでしょう。
さらに興味深いことに、上記のプロセスで会社への貢献意欲が高まっている新人は、自らの自律的なキャリア成長感も高まっています。入社後、会社に適応していくということは、ある意味、会社が敷いたレールに乗るわけですから、自律的なキャリア意識はむしろ低下するのではないか考えがちですが、逆です。会社への適応も高まり、かつ自律的なキャリアの成長実感も高まっています。これは、組織への貢献と個の自律化の両立が不可能ではないことを意味しているかもしれません。新人主導型のオンボーディングは、単に社畜化を促すものではないのです。
次に、シニア人材の活用に関してです。シニア人材活用に関する企業の調査結果を見ると、シニア人材の活用におけるボトルネックとしては、シニアのモチベーションに関する課題感が強いようです。例えば、若年層とのコミュニケーションの課題や、シニアに対する報酬が人件費を圧迫するという課題よりも、一番多いのはシニアのモチベーションをどう上げていくかという課題です。
逆に言えば、課題がある程度焦点化していて明確なので、打ち手はあると思います。つまり、優先順位として、シニア人材活用をより進めていくには、まずはモチベーションに対する課題をクリアしていくことが重要だと思います。中高年人材のモチベーション対策を体系的に行ってシニア層のモチベーションが底上げできれば、シニアは重要な人材プールとなり得ると言えるかもしれません。
私が最近行った研究成果から、二点指摘したいと思います。まず一つは、中高年人材のモチベーションの改善には何が重要かと言うと、企業側のウェルビーイング重視の経営姿勢だということがわかりました。中高年人材は、組織の中でも、経営層と階層や年齢が近いケースが多いです。なので、経営層の考え方や姿勢に非常に敏感になります。彼らが何をどうしようとしているのかということに対するアンテナや感度が非常に高いのです。経営層が従業員の幸せを心底気にかけているという姿勢が見えて、また目に見える形で施策に反映されていると、シニアの心の状態が改善することがわかってきました。具体的には、ポジティブな感情、例えば楽しいとかわくわくしたとか、活気がある…、そういった感情状態が安定的に醸成されることが確認できています。
もう一つは、まだまだ自分には活躍できる機会が残されているという感覚、これを「未来展望」と言っていますが、これが高まると定年後も現役で働きたいという意志が強まることも確認されています。いわば、企業がウェルビーイング重視の姿勢をしっかりと打ち出すことが、シニアの心の若返りを促すということです。ここで言うウェルビーイング重視の経営姿勢とは、サスティナブルHRM、つまり人的資本経営の基本的な考え方に沿ったものだと思います。その意味ではシニアの心の若返りを促進するためにも、サスティナブルHRM、もしくは人的資本経営の実践というのは、意義があると言えるのではないかと思います。

04自社の経営に何が求められているのかを真摯に考えよう
最後に中小・中堅企業の経営者や人事責任者へのメッセージをお願いいたします。
経営の手法や考え方に関する新しい言葉が次々と生まれています。一方で、氾濫する情報や知識の中で、必要なものとそうでないものを我々一人ひとりが見極める力が、今まで以上に重要になってきていると思います。新たな言葉やバスワードに踊らされることなく、自社のビジネスや経営にとって何が求められているのかという判断軸を持っていただきたいというのが私からのメッセージです。
本質を見極めるために大事なことが二点あります。まず、一つは経営のリテラシーを高めることです。つまり、経営学で説明されている基本的な考え方や概念に当てはめて物事を考えてみることです。そのためにも、教科書を表面的に読むのではなく、しっかりと読み込んで自分の血や肉としていく、そのプロセスが大切です。その上で、今社内で起きている出来事やこれから向かっていこうとしている方向性に対して、打ち手として何を考えたら良いのかを模索することが重要なポイントだと思います。
もう一つは、意思決定のプロセスに現場を巻き込むことです。もちろん、最終的な意思決定をするのは経営者かもしれませんが、やはり意思決定をする前の段階で、例えば今考えていることや仮説みたいなものがあったとしたら、それが本当に社内で共感をもって受け入れられることなのかどうかを検証する必要があると思います。つまり、ビジネスの世界には正解がない、あるいは、正解を発見するというのは、容易なことではありません。しかし、社内で共感してくれる人たちが沢山いるのであれば、それはもしかしたら、いわゆる最適な解に一番近いものなのかもしれないということです。
ですから、独りよがりで意思決定するというプロセスではなく、現場にぶつけてみる、あるいは多様なステークホルダーにぶつけてみて、それで共感を得られるようなものであれば、おそらくそれが目指している判断軸であると思います。

竹内 規彦氏
早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授
名古屋大学大学院国際開発研究科博士後期課程修了。博士(学術)学位取得。専門は組織行動論、人材マネジメント論、および職業心理学。東京理科大学・青山学院大学准教授等を経て、2012 年より早稲田大学ビジネススクールにて教鞭をとる。2017年4月より現職。2022年より京都大学経営管理大学院にて客員教授を兼務。
米国Association of Japanese Business Studies会長、経営行動科学学会会長、Asia Pacific Journal of Management副編集長、 欧州Evidence-based HRM誌編集顧問等を歴任。組織診断用サーベイツールの開発及び企業での講演・研修等多数。