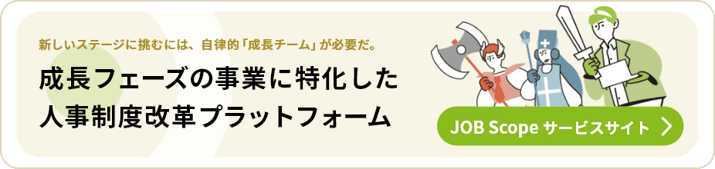人的資本経営の実現には、経営人材の育成が不可欠(後編)
VUCAの時代と叫ばれて久しい現代。ビジネスの変容はますます激しくなっている。まさに、企業経営者にとっては、嵐の中で船をこがなければいけない状況にある。経営のプロとしてスピード感のある判断をしないと、いつ転覆するかわからないと言って良いだろう。といっても、経営者に任させていれば良いというものではない。その経営判断が、正しいのかを常にチェックする機能も重要となる。それが、ESG経営の「G」であるガバナンスだ。日本において、コーポレートガバナンスの権威と言われるのが、東京都立大学大学院 経営学研究科、経済経営学部教授の松田千恵子氏である。今回は同氏に、ガバナンスの視点から人的資本経営について語ってもらった。後編では、企業価値の高め方や今後の人事部門の在り方を聞いた。

01ジョブ型雇用という名の
論理矛盾が起きている
ジョブ型雇用に関してはどのような見解をお持ちですか。
これも、「定義をきちんとしていますか」とお聞きしたいです。「一体何を指してジョブ型雇用と言っているのか」が不明確な場合も多いですし、誤解されている方も沢山います。単に人事評価をきちんと行うことを指している場合さえありますが、それはジョブ型であるかどうかを問わず当然に必要なことです。未経験の新卒採用だけに人材獲得を頼りながらジョブ型雇用であると豪語する企業もあります。論理矛盾をあちこちで起こしてるように見えます。
本来的なジョブ型雇用を考えると、日本の会社が一足飛びにそこまでいくとは思いません。ただ、特に若い人たちを見ているとプロフェッショナル志向が非常に強いので、「どういう仕事なのか」について、きちんと機能定義する必要はあります。昔のように「ジェネラリスト型でとにかく採るからね」ということは通用しなくなってきていると思います。私のゼミの学生も、配属ガチャ(新入社員が希望する勤務地や職種に必ずしも配属されないこと)を最も嫌います。「これは何をする仕事なのか」という機能定義だけは明確にしておかないといけません。
それと、企業の中途採用に関して良く人事の方に聞かれるのは、「優秀なITエンジニアや、著名なマーケッターを採用しようとすると、社長より給料が上になってしまいます。どうすれば良いですか」という質問です。それは当たり前です。社内価値ではなく、市場価値の高い人がより多くの給料をもらえるに決まっています。その辺りの思い込みみたいなものも整理しないといけないと思っています。
だから、本格的なジョブ型という話はまだ少し先の話です。まずはその辺りの「ジョブ型とは何なのか」、少なくともジェネラリストの新卒一括採用や終身雇用が崩れて来た時に何をすれば良いかといったことを一つひとつ考えていかないといけません。何だか、ひどく雑な定義のもとに、雑なことを考えているだけみたいになっている気がします。
確かに、多くの先生が定義の曖昧さを指摘されています。
おっしゃる通りです。人的資本経営にしても戦略人事やジョブ型経営にしても、いずれも定義ができていません。定義できていないことについては、皆手が動かないのです。高らかに語られていますけれど、中身が全くなかったりします。もう少し地道に「終身雇用を前提とした社内制度は相変わらずだが、終身雇用を信じている若年層はもうほとんどいない」とか、「採用の際にも学生に配属ガチャがあると嫌われて応募者が集まらない」などといった、実際に起こっている問題をまずきちんと認識し、その上でどうすれば良いのかを、その会社が個別に自分の頭で考えるしかないと思います。
「その先はジョブ型です」と言った時に、ジョブ型と言っているものについて、定義できていない人がそちらに移れますか。どう考えても疑問でなりません。

02企業価値には
右脳的と左脳的がある。
その統合が大切
松田先生は、企業理念や社会的意義を「右脳的な企業価値」、将来キャッシュフローの現在価値を「左脳的な企業価値」と定義されています。それは、どのような意味合いなのでしょうか。
これは、わかりやすく言っただけです。左脳的という方はデジタルなので、いわゆる投資家が言う企業価値です。これは明確に定義すれば、要は負債と資本のコストを勘案した将来キャッシュフローの総和の現在価値です。それを上げていくのが、投資家に向けて企業価値向上と言う時の企業価値だと思います。そちらが左脳の話です。
ただ、サステナビリティの文脈なども考えると、最近は経済的価値だけ上げていれば良いわけでもありません。そもそも事業会社たるもの、事業が社会にとってマイナスになってはいけません。プラスの存在でないといけないのです。そういうことをきちんと考えていこうという企業の社会的意義みたいなもの。これはややエモーショナルなものなので、右脳的と呼んでいます。
ただ、人間の脳も、左脳と右脳だけあれば動くというものではありません。脳梁(左右の大脳半球をつなぐ交連繊維からなる構造)で統合して初めて高次な人間の頭の動きができるわけです。同様に、企業においてもこの二つの価値を統合する必要があります。脳梁の働きをするのがまさに経営者の仕事であり、統合された将来の姿をきちんと作って、両方の企業価値を上げてくださいという意味で使っています。
中小、中堅企業の経営者や人事責任者にはどんなメッセージを送られますか。
経営環境が大きく変わってきていることを多分認識されていると思います。それゆえに今いる従業員も、それから新卒に限らず中途採用も含めてこれから入って来る従業員も相当意識が変わって来ています。ですので、意識の変化をきちんと捉えていかないと、正しい人事政策にならないと思います。正しい人事政策とは、どういう話かと言えば、いかに自分の企業を魅力的に磨き倒すかに帰着すると思います。
今までは人事という枠の中に人の話を入れていました。採用やキャリアデベロップメントも含めて、人事制度をその維持という範疇でしか考えられていなかったと思います。そうではなくて会社の有り様や、それこそ経営戦略の話だいうことをもっと意識していただくと良いと思っています。

03もはや従来からの
人事部の建付けでは
機能しない
その意味では人事の在り方も変わっていく必要がありそうです。
まずは、今の人事部という制度では駄目だと思います。私は二つに分けた方が良い気がしています。一つは、いわゆる労務管理です。現状はこちらによりリソースを割いている会社が多いと思います。もう一つは、経営戦略から出てくる人へのニーズをいかに満たすかを考える部署です。それこそ戦略人事です。本当は、この言葉は嫌いなのですけれどね。人材開発と言っている方もいたりします。その二つに分けて考えないといけません。今までの人事部の仕事をそのまま行っているだけではもう機能しないと思います。
別に私は、人事部の悪口を言いたいわけではありません。今までの人事部は、終身雇用、年功序列、協調型組合という、(経営学者アベグレン・ジェームズ・C.の言う)日本型経営システムを前提とした部門なのです。しかし、今はこうした前提が崩れているので、今の部門のまま何とかパッチを当ててどうにかしていこうというのは、多分機能しないと思います。現在の環境にあわせて改めて必要な機能を見た時に、少なくともこの二つに分けて考えないと駄目だというのが私の考えです。
人事部にいる、かなり多くの人は実は労務管理を担当しています。足りないのは戦略人事というか、人的な意味での経営資源をどうするかを考える人たちです。この機能に、私は名前を付けにくく感じています。人的資源と言いたいのですが、別の文脈から人的資本という言葉が出てきてしまって却ってわかりにくくなっています。人的資本は投資の元手となるから価値を生み、資源は使えばなくなるからコスト的な見方だという人もいますし、両方とも投資家的な用語で嫌だという人もいます。個人的には、人的資本を持っているのは個人であって企業ではなく、企業が現在雇用している従業員の能力を人的資本などと自分のもののように称するのは僭越だと思っているわけですが、詳しく話すと長くなるのでこのくらいにしておきます。話を戻すと、経営戦略論的にはやはり、人的な意味での経営資源をどうするかというのが論点です。経営資源、リソースだと考えた方が良いです。ただ、どこからでも調達できるような、その辺にある一般的なリソースではなくて、非常に特殊かつ貴重なリソースをどのように経営戦略と融合させていくかを考える人的経営資源配分機能が必要だと思います。今の人事部はあまりやってないですよね。
もう一つ指摘したいのは、人事部だけでやろうとすると手がつかないということです。人事部にはどうしても経営戦略を理解してやっている人が少なかったりします。やはり、これはトップマネジメントおよびそのチーム、そしてそれを支えるブレーン、日本で言えば経営企画部門がやはり中心となるのでしょうが、そうした経営の中心となる側から手を伸ばして人材開発機能を作るべきです。人事部門も、人事のデータベースなどを基にした情報提供を行う形でそこに入るのが良いことはあるでしょう。コーポレートガバナンス的に言えば、こうした分野においては指名委員会が非常に大きな役割を果たすことになります。

松田 千恵子氏
東京都立大学 大学院 経営学研究科 教授/経済経営学部 教授
一橋大学大学院特任教授
東京外国語大学外国語学部卒、仏国立ポンゼ・ショセ国際経営大学院経営学修士。筑波大学大学院企業科学専攻博士課程修了。博士(経営学)。日本長期信用銀行にて国際審査、海外営業等を担当後、ムーディーズジャパンの格付けアナリストを経て、コーポレイトディレクションおよびブーズ・アンド・カンパニーでパートナーを歴任。現在は、マトリックス代表取締役の他、日本 CFO協会主任研究委員、公的機関や上場企業の社外役員・経営委員等も務める。