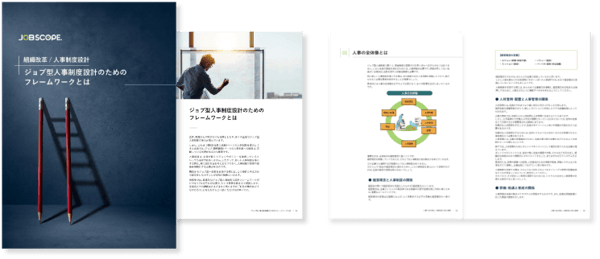独立行政法人中小企業基盤整備機構の発表によると、日本の中小企業数は約336万社(令和3年経済センサス 活動調査)。実に日本における全企業数の99.7%をも占める。また、中小企業で働く従業員数は約3310万人。全従業員数の69.7%を占めるに至っている。まさに、日本を支えているのは中小企業と言っても良い。そんな中小企業が時代の荒波を乗り越えて成長していくためには、どうしたら良いのか。そのメカニズムを検証しているのが、大阪経済大学の江島 由裕教授だ。近年では、実践的な起業教育にも取り組むなど、さらに活動範囲を広げている。インタビューの後編では、アントレプレナー人材を輩出する鍵や大学における起業教育の在り方などを聞いた。
目次

01アントレプレナーシップ・マインドを地域に根付かせる必要がある
まだまだ、アントレプレナー人材は輩出できていないとしたら、どうしたら良いのでしょうか。
多分ドラスティックには変わらないと思います。だから、非連続と言うよりは、漸進的に、少しずつ、着実に、変化の角度を上げていく必要があると思っています。少し悲観的に聞こえるかもしれませんが、皆さんご承知の通り、世界における日本の経済的立ち位置/存在感は、GDPに代表される通り低下し、今後、ますますその傾向が強まる嫌な予感がします。100年後の日本の経済的・政治的・社会的なプレゼンスが高まり、活力ある日本を取り戻すためにも、アントレプレナーシップ・マインドに溢れた社会基盤が必要で、それがより良い経済社会の実現につながっていくと信じています。
アントレプレナーシップ・マインドとは、前にも少し述べましたが、根っこは、企業家的志向性(EO)と同義と捉えて良いと思います。組織だけでなく、個人の思考や行動様式として、社会での営みの中で能動的に社会を一歩先取りし、リスクを厭わない、そんな人々の活動を指します。そして、そうした個人を社会が積極的に受入れ、本気でいかす寛容性と支援マインドが求められているのです。これは、様々な価値観、文化、経験といった違いを認識しリスペクトし、受容するダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包括)の考え方と親和性があり、それを前提としてます。
残念ながら日本は、歴史的にみて多様性を受け入れることに慣れていないのかもしれませんが、マイノリティへの配慮という視点も含めて、ダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包括)は、バズワードで終わらせることなく、自然に社会で当たり前のこととして認識され、実質化されていくことが必要であると思っています。そして、この延長線上に、起業への挑戦や失敗を終わりと捉えず、成功への途中プロセスとみる風潮が芽生えてくるのではないでしょうか。広く様々な価値観に基づく多様な社会が、アントレプレナーを生む土壌となり、活力ある日本を育むことになるとみています。
起業家社会の到来はまだまだかもしれませんが、まずは身近なコミュニティや地域で、知り合いが、起業に挑戦し失敗した時に、一時的に雇用や仕事の場を紹介したり、何か新しいことに挑戦、再挑戦、再々挑戦する時に、資金面、メンタル面、ネットワーク面で、地域のご近所仲間が応援し励ましたりする、そんな地域のムーブメントと風土の醸成が変化の起点になるのではないでしょうか。実際、そうした動きがあることも知っています。起業家のコミュニティ、経営者コミュニティ、国・自治体・大学の応援コミュニティなど、着実に起業家エコシステムは動き出しています。

02大学教育を通してアントレプレナーな生き方を醸成していきたい
アントレプレナー人材の育成に向けて大学は何ができるのでしょうか。
「アントレプレナーは育成できるのか」。これは、海外の学術誌の中で議論があったテーマです。結構反響を呼びました。つまり、アントレプレナーとしての資質は、後天的に育成できるものなのか、あるいは先天的に決まっているものなのかという議論で、実践にかかわる関係者からも注目を集めました。これは、答えがある訳ではありませんが、いろいろと考えさせられるテーマではあります。
最近、先天的というか資質面から、アントレプレナー気質/傾向をもつADHD(注意欠如多動症)起業家の研究を進めています。その行動様式をみると、前に述べた企業家的志向性(EO)の特徴と強くフィットすることがわかりました。イーロン・マスクやスティーブ・ジョブズもADHD起業家としての傾向が強く、彼らの逸脱した思考や行動が、イノベーションを生み、社会を大きく変えたという分析があります。また、そこまでダイナミックな動きでなくても、ADHD起業家の中には自身の生きづらさからの解放の手段として、好きなことを自営業やフリーランスとして営む人々もいます。いずれもADHDという気質が契機となりアントレプレナーシップを発揮している訳です。
脳の機能に原因がある発達障害であるADHD起業家は、ある意味アントレプレナーシップの鍵行動が、意識あるいは訓練することなく、自然に出てしまう傾向があります。そういう意味では、アントレプレナーというのは、先天的な資質にかなり影響を受けているということかもしれません。
一方で、ADHDの特異な行動は社会活動の中で、逸脱行為としてネガティブにみられるがため、カウンセリングなどを通じて抑えようとします。そういう意味においては、その資質は変えられると言えなくはないでしょう。つまり、アントレプレナーシップは、抑制だけでなく、逆に発揮についてもコントロールできる可能性があるということです。先天的にその資質がそれほどなくても、後から訓練や教育を通じて社会的に介入することで、アントプレナーは育成できるかもしれません。
そうした中で、大学や大学院教育に落とし込んでみたときには、様々なアントレプレナーが生み出されています。大学や大学院に通いながら起業する人は増えています。小さな雑貨屋を運営するケースもあれば、自営やフリーランスとして好きなことを仕事にするスタイルもあります。ビジネスパーソンとして、大企業に入って新事業開発を担う人もいます。とても多彩です。画期的な発想とアイディアで、従来のビジネスのやり方や仕組みを変えようと試みる人も生まれています。規模や動機などから、「これだ」と決めるのではなく、現代のアントレプレナーは、それを生き方の問題として捉え、その意味を深く考える必要があると思っています。そうすることで、多様なアントレプレナーの育て方やいかし方を見つけ出すことができるような気がします。
今、どこの大学でも、起業や事業創造に関する授業が展開されています。そこでは、ビジネスプランの作り方、資金調達の方法、人や組織のマネジメントの型など、実践的な活動を意識した知識やノウハウの提供が主です。また、ビジネスプランコンテストやそれをブラッシュアップする各種セミナー、VCやエンジェルなどとのネットワーキング、起業スキルを磨くインターンシップなど、学生向けの学習の場は、格段に拡充しています。これは、学生にとってはとてもありがたく、これまでにはなかった学びの場です。テキストを読んで収益計算をしていた段階から、実践の帳簿をみる段階になり、リアルビジネスで役立つ世界が近づいてきた印象です。ただし、これは全て、言ってみればビジネスの技術的な側面で、なくてはならない知識とノウハウではありますが、真面目に取り組めば、誰もが同じレベルまで到達できるものでしょう。
そうではなくて、こうしたスキルを何のために、どのように活かすのか、どうすれば失敗を超えてビジネスを軌道に載せられるのか、起業ビジネスの実態と本質をどこまで知っているのかといった、挑戦し続けるマインドセットへの刺激やインプットへの深い学びが、何より必要ではないでしょうか。
最近、「エフェクチュエーション」(成功した起業家に見られる思考プロセスや行動パターンを体系化した意思決定理論)という言葉が注目されています。これは、簡単に言うと、新事業を成功させる場合、通常は、まずゴールを決めてそれを実現する手段を探るというアプローチが主流ですが、不確実性が高い場合は自分は何ができるのかという手段主導でアプローチをしながらゴールを定めていく方が、失敗は少なく成功確率が高まるという考え方です。
起業の実践では先が読みづらいので、常に試行錯誤がつきまといます。だから、粘り強く、自分が何者かを知り、周囲との関わりを通じて、柔軟に物事を進めていくことが大切になります。そのことを、このアプローチが学術的知見に基づき教えてくれています。こうしたことも、なかなか従来の大学の教育では実践されていません。
振り返ると、起業について教えること、つまり「起業の教育」は可能なのかもしれませんが、起業家(アントレプレナー)を育てる、つまり「起業家教育」は、真に難しいことで、だからこそ、やる意義があるのかもしれません。大学では、本気度や熱量のある起業家を育てていく必要性を感じています。そして、その先には、何より本人の成長と幸福感があり、それが起業家社会の醸成へと結びついていくと信じています。

03学内にアントレプレナーシップ(ENT)塾を開講する
江島先生が塾長をされている、大経大ENT塾の概要をお聞かせいただけますか。
2023年1月に大阪経済大学にアントレプレナーシップ塾が開講し、私が初代塾長を拝命致しました。英語のEntrepreneurship の略語を取り、ENT(アント)塾と名付けました。私が参加する全米経営学会のEntrepreneurship(ENT) Divisionと同名です。
大経大ENT塾では、アントレプレナーシップ・マインドの醸成を狙いとし、その本質と実践を学びます。表面的な打ち上げ花火のような場ではなく、本物志向の塾を目指します。ここは、本学にいる学生であれば誰でも参加できます。「会社を起こしたい」、「将来ビジネスを成功させたい」、「始めたビジネスを軌道に載せたい」など、どんなことでも学生の思いを全面的に支援する塾です。また、ここは、単位付与はしていません。やる気と熱量が全てです。選考も、思いと熱量と塾へのコミットメントを問います。本当にやる気がある人たちに、「この指とまれ」方式で集まってもらいます。一番の狙いは、同じような考え方を持つ仲間が集まり、協働し、試行錯誤を繰り返し、連続的に化学反応が起きる、そんなENTコミュニティづくりです。
ここでの学びは、将来多方面で活かせます。例えば、起業や連続起業、学びながら、働きながらの起業準備、会社内での新事業開発、副業としての起業、後継ぎベンチャーなど多様です。社会を変えるようなスタートアップから、ワークライフバランスを重視した自営業まで幅広く支援します。
塾が開講してほぼ2年が経ちましたが、塾生の問題意識は多様で、熱量に溢れています。皆、個性豊かです。それぞれの経験、生き方、動機や思いなど「個」の違いを大切にし、仲間と喜びや悩みを共有しながら切磋琢磨し、楽しみながら、起業や事業創造に取り組んでいます。塾修了後も、OB・OG、学外の関係者などとの交流の場を通じて、類は友を呼ぶではないですが、ENTの輪は広がっています。
大経大ENT塾は、基本のフェーズ1、応用のフェーズ2、実践のフェー3と段階毎に、内容を変えて年間運営しています。フェーズ1は、何より何か新しいことに挑戦することの意義、価値、喜びを理解してもらうことにあります。学生と年齢が近い、若い起業家を呼んで、どんな思いで起業をしたのか、大変だったのか、今充実しているのか、儲かっているのか、これからどうするのかなど、本音で良いことも悪いことも、語り合える場を中心にプログラムを組んでいます。ここは、起業家マインドを醸成するとともに仲間を作ろうとするフェーズです。起業家は関西を中心としたIPO直前とか、あるいはIPOしたてで、苦労しながらも本気でビジネスに取り組んでいる人たちに参加してもらっています。
フェーズ2になると、次は少しビジネスの作り方にシフトします。チームで外部のビジネスプランコンテストへ必ず応募し、出場することを目指し、各チームには学内の教員がメンターとして付き、専門的な助言やチームビルディングのガイドを実施します。目的は、自分たちのアイデアを世の中の人に見てもらい、そしてコメントをもらい、ネットワークを作り、繋がっていくことです。同時に、チームビルディングの難しさも学んでもらいます。小さなチームであっても、フリクション(あつれき)は絶えません。ここを乗り越える経験と学習も大切ではないでしょうか。
そして、最終のフェーズ3は、いよいよビジネスをローンチする段階です。私自ら、個々の事業アイディア、ビジネスプラン、リソースなどを目利きして、学生の思いと現実とのバランスを考慮し、選考したものを、外部のプロのメンターやVC(ベンチャーキャピタル)や関係機関を紹介しながら伴走支援します。ちょうど今、フェーズ3を終えローンチした大経大ENT塾第一号のビジネスを、私が引き続き月一回のペースでモニターし、支援を継続しています。
フェーズ2までとは異なり、ここではリアルビジネスの難しさに直面します。こちらも、彼らと壁打ちをしながら、必要なリソースの紹介や助言はしますが、最終的には彼らに決めてもらってます。独立と自立を促すことが我々のミッションです。決して、甘やかさず、起業家がしっかりと自分の足で歩んでいけるようにサポートします。そういう意味では、小さなミスも、大きな失敗でない限り良しとすることもあります。アントレプレナーシップ教育で著名な米国のバブソン大学には、小さな失敗を敢えて経験させる授業があるようです。失敗からの学びこそが大事です。
将来、大経大ENT塾は、もっと広がりをもったものに進化させたいという野望を持っています。拠点は大阪経済大学にあるものの、塾生は本学の学生に限らず、広く関西の高校生や大学生や大学院生まで広げて、意欲を持った若い人たちが集い、本物のアントレプレナーシップ・マインドが根付く場をつくれればと思っています。このENT塾で、豊かな発想力と創造力を養い、かけがえのない仲間と出会い、突き抜けたアントレプレナーが生まれることを切望しています。

04逸脱した能力がイノベーションを生むきっかけとなる
神経発達症とアントレプレナーの関係性について、もう少しお聞かせいただけますか。
近年、海外でこのテーマに関する研究が増えてきています。もう少し補足すると、先ほど言いました通り、脳の機能に原因があるとされる発達障害の1つとしてADHD(注意欠如多動症)がありますが、これがビジネスにポジティブに働くことについての関心が高まってきた、ということです。
発達障害の専門医や臨床心理士もたくさんいて、何十年もの間研究が進められてきましたが、私はこれをアントレプレナーシップという視点から研究を進めています。一般的には、発達障害としてのADHDは、多動性、衝動性、不注意性の特徴を持つとされ、ビジネスシーンでは、必ずしもポジティブには認識されづらく、本人も周囲もそうした行為をコントロールするような対処方法を検討する傾向にあります。
確かに、一つのことに集中しすぎて打合せを忘れる、仕事に夢中になり徹夜を繰り返し身体を壊す、場の空気を読めずにクライアントを怒らす、衝動的にお金を使い果たすなど、困り事が多々あります。一方、集中力が際立っているがために、ハイレベルの知識やスキルの修得が早く、好きな仕事へのコミットメントが強く業務の生産性が高いとも言われます。また、気に入ったことや得意なことなら、周りを気にせず、リスクを厭わず、突き進む行動力には驚かされます。
ADHD起業家の研究を進めていると、その症状の多動性と衝動性が、アントレプレナーシップの発揮に重要な役割を果たしていることがわかってきました。もちろん、その症状にはグレーゾーンもあり、明確にどういった資質が、起業や事業創造に直結するのか、その条件についても諸説ありますが、ADHDという資質は、必ずしもネガティブな側面だけではなく、アントレプレナーシップを発揮するポジティブな側面も併せ持っているということは確かなようです。
では、その分岐点はどこにあるのかということですが、私のこれまでの研究からは、ADHDという診断(特性)を受け入れ、自分の行動を客観視するという「メタ認知」が鍵を握っているのではないかと、とみています。ただ、もちろん、これが全てという訳ではありませんし、そもそもADHDの症状がポジティブに働くとも言い切れません。むしろ、リアルビジネスの世界では、これまで通り生きづらさを感じている方々が多いのが実態ではないでしょうか。ADHD起業家として脚光を浴びる人はごく僅かでしょう。生きづらさや苦しみが重なり、二次障害を発症し鬱になる人たちもいます。そういう方々が、生きやすい形で、自営業やフリーランスとして自分の個性や能力を発揮する、というアントレプレナーの選択もあることは、先ほど申し上げた通りです。
ADHD起業家であるイーロン・マスクやスティーブ・ジョブズの逸脱したアントレプレナーシップ行動が、世の中を変えるイノベーションを生む駆動力になっていたことは間違いないでしょう。同時に、ウェルビーングを追求し、生き方としてのアントレプレナーを選択するADHD起業家もいます。アントレプレナーシップの多様な意義と役割があるということです。

05村づくりからもオーセンティックな経営を学べる
寄稿「村から学ぶオーセンティック経営」を通じて、読者に最もアピールされたかったポイントを教えていただけますか。
これも、今までお話をしてきたアントレプレナーシップ発揮の延長線上にあるものです。今度は、小さな村がアントレプレナーシップ・マインドに満ち溢れているという話です。村や町などの自治体が民間に学ぼうというのは、昔から良くありましたが、逆はあまり聞きません。村づくりを一つのマネジメントのあり方として捉えた時、雑誌で取り上げた西粟倉村の挑戦は、現代の企業経営にとって、初心にかえるように新鮮で、学びが多いと感じ、執筆した次第です。
西粟倉村はローカルベンチャー発祥の地として知られています。2004年、平成の大合併に反対し、自主自立の道を選びました。その結果、補助金が減り、財源は大変でしたが、その後20年で、村は大きく変わり、躍進を遂げました。1500人に満たない小さな村に、50を超える会社が生まれたのです。
その発端は、2008年の百年の森林構想で、唯一無二の村の資源である森林資源を守り、管理し、活かし、循環させ、稼ぐというビジョンを示し、そこにこだわり、国に過度に依存せず、自立することを村として宣言します。村が今あるのは過去のお陰で、未来の村は今の行動にかかっている、という考え方を村で共有させます。そして、この宣言を契機に、Uターン、Iターン含めて共感が生まれ、磁石のごとく人が集まり、ローカルベンチャーとして注目を集めることになったのです。
その背後には、大きく一歩踏み込んで、これまでの村の考え方を変えようとした村役場の存在が欠かせませんでした。ローカルベンチャーと彼等を支える村役場との協働が、西粟倉村を飛躍させた要因の一つでした。その上で、村は3つのマネジメントの基本にも忠実でした。一つは経営戦略論です。厳しい外部環境の中、生き残りをかけて自立の道を選んだ訳ですが、その道筋を百年の森林構想をロードマップとし、地元の森林資源をコアコンピタンスと位置づけ、明確に描き行動しています。二つ目はマーケティングです。百年の森林構想や森林資源が紡ぐ村の空間を大切にし、その魅力をストーリー、体感、共感で周囲と直接つなげようとする二人称的アプローチをとっていました。
三つ目は、経営組織論です。自主自立の道と価値創造のマーケティングに舵をきった西粟倉村ですが、それを動かすのは組織です。生き残るための仕組みや仕掛けに、地元の経営者とともに中心的に取り組んだのは村役場でした。時間がかかる面倒なことばかりでしょうが、変化を厭わず、ぶれることなく、志と熱量と創意工夫で、それを可能にしたのではないでしょうか。そこには、一点突破で、価値を生み出そうとするアントレプレナーシップ・マインドが溢れていたとみています。基本を大切にする、西粟倉村のオーセンティック(本物/本質)経営には、一見の価値があるのではないでしょうか。
村から学ぶオーセンティック経営 大阪経済大学 経営学部 教授 江島 由裕
江島先生、貴重なお話をありがとうございました。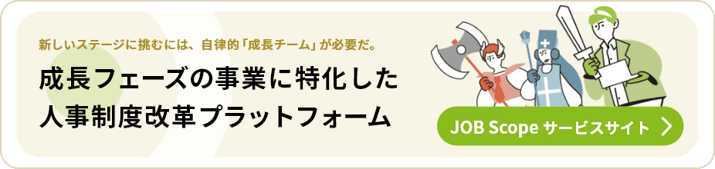

江島 由裕氏
大阪経済大学 経営学部
経営学部 教授
米国ピッツバーグ大学大学院公共・国際事情研究科 修士課程修了。公共・国際事情修士(MPIA)。上智大学 博士(経営学)。専門分野は、アントレプレナーシップ、中小企業経営、中小企業政策。日本ベンチャー学会清成忠男賞など受賞多数。