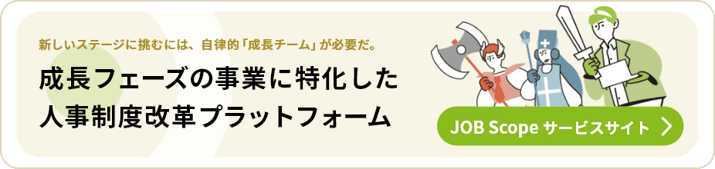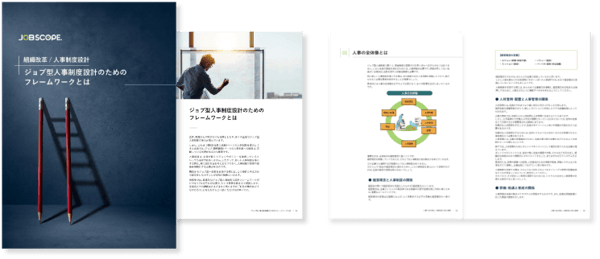社会環境がダイナミックに変わりゆく中、企業は生き残っていくために経営戦略や事業戦略、人材戦略を変えていく必要がある。それは、誰もが認識しているはずだと思っていても、実際には何らかの要因によって遅々として進まない、あるいは予想外に時間が掛かってしまうということがありがちだ。どこかに問題があるのは間違いない。そうした中、長年「企業が変わる」をテーマに経営学を研究されてこられた大阪大学・渡辺 周准教授は、豊富な実証研究を通じて得た知見に基づき、経営者に新たな示唆を提示してくれている。インタビューの前編では、「組織の〈重さ〉」プロジェクトに参画する中で気づいたポイントをメインに語ってもらった。

01企業の変革を促す要因、阻害する要因とは何か
渡辺先生の研究概要を教えていただけますか。
私の専門は、広い意味で言うと経営学です。特に経営戦略論と経営組織論を手掛けています。どちらかというと経営戦略をメインに、その戦略の問題を考えるために、組織ないしは人の問題を扱っています。それが、私の研究者としての立ち位置です。戦略論といっても幅広い問題がありますが、私が大学院以来やっているのは、「企業が変わる」ということです。戦略を変える、もしくは新しいビジネスに参入する、既存のビジネスから撤退する。そういったときにどういった要因が新規参入を促進したり、逆に撤退を阻害するのかというように企業が変わることを可能にする能力だったり、逆に阻害してしまう要因を研究しています。
特に昨今では、どういった論点をお持ちでいらっしゃるのか教えていただけますか。
私がこの関係のテーマで最近関わった研究を2つご紹介したいと思います。1つは、「組織の重さ」という大きな調査プロジェクトです。これは、2003年から隔年で7回ほど日本のさまざまな大企業にご協力いただいて調査を続けてきたデータを分析した研究です。
何となく重たい組織とか、逆に軽快な組織ということをビジネスパーソンの皆さんも感じられることと思いますが、その感覚に極めて近い考え方です。組織の中で新しい事業を起こすとか、既存製品をリニューアルするとか、もしくは既存のビジネスから撤退するといったときにそうした活動を阻害してしまう組織の劣化度合い、これを組織の重さと呼んでいます。
調査に協力していただいたのは大企業ですが、分析の対象としては事業部単位です。事業部の規模の中央値は、大体、200人から400人ぐらいです。そのため、大企業だけの話というわけではなく中小企業にも当てはまるところが結構あると考えています。
また、もう1つ現在進行中の研究として、「組織における年齢ピラミッド」の問題も考えています。これは、どういうことかといいますと、雇用のあり方が多くの企業で今、まさに変わっている最中かと思いますが、特に日本の伝統的な、いわゆる大企業の中には、新卒採用をしてそこから定年まで雇用するというスタイルの会社も未だに多くあります。また、そうした会社が景気によって新卒の採用数を大幅に増やしたり、逆に減らしたりすることで、結果として、日本企業では、年齢構成がかなりいびつになっている会社を見つけることが出来ます。その典型が、いわゆる就職氷河期世代で、この層だけが他の年齢層と比べて薄い会社というのが存在します。そのいびつさが企業にどのような問題を企業にもたらすのか、ということを、学習院大学の鈴木健嗣先生や、中央大学の西村陽一郎先生、中京大学の加藤政仁先生と共同で研究しています。

02「組織の〈重さ〉」は負の側面をもたらす
「組織の〈重さ〉」プロジェクトは、渡辺先生単独で調査を進めておられるのですか。
いいえ、違います。この調査は、一橋大学で行われていた21世紀COE、グローバルCOEという大規模な研究プログラムの中核的なプロジェクトとして実施されました。元々は、私の指導教員でもあった一橋大学名誉教授の沼上 幹先生(早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授)が中心となって始められました。私自身は、最初は大学院生のリサーチアシスタントとしてお手伝いをさせて頂き、教員になってからは研究メンバーの1人として加えて頂き、今年、これに関する書籍で、そのうちの1章分の分析を担当する機会をもらいました。
この調査から見えてきた、渡辺先生なりの見解を読者にご紹介いただけますか。
私のオリジナルというよりは、7回の調査を経て安定して観察された傾向、重要なポイントをお伝えできればと思います。まず、前提としてお伝えしたいのは、組織の重さによる負の側面です。
負の側面のわかりやすいところとしては、重い組織では、調整に時間がかかっています。つまり新規事業を始めるにしても、既存製品のリニューアルをするにしても、撤退をするにしても、調整に時間がかかってしまい、製品リニューアルで言えば、リニューアル後の製品コンセプトを考えたり、そのための調査をするといった市場向けの活動ではなくて、社内向けに根回しをしたり、「反対をするのではないか」と思われる人を説得したりするというような、内向きの活動に過剰に時間が使われているということが、重たい組織では見られます。
それから、当然ながら利益率だったり、売り上げの伸びなど客観的な成果の側面でも、重たい組織では良くない傾向があるというのが、組織が重たいことによる問題として我々が観察出来た2つ目の点です。ここで気を付けて頂きたいのは、われわれは、「根回し自体が不要だ」「調整が不要だ」と考えているわけではありません。そうではなくて、そうした根回しだったり、内部向けの調整が過剰になってしまっている組織があるのではないかというのが我々の問題意識であり、それらが過剰な組織が実際にあり、それが問題を引きおこしていることを確認したということです。
そうだとすると、そうした組織にならないようにするために、どうすれば良いかということが次に問題となります。
主なメッセージとして、三つぐらいお伝えできればと思っています。1個目は、単純ではあるのですが、やはり組織の規模を小さくすることがすごく大事だというのが、我々の分析から出てきている結論です。もちろん、そうではない優れた会社も多くあるとは思いますが、我々のデータで出てくる重たい組織というのの結構な部分が、肥大化した組織になっているので、単純ではありますが、組織を小さくするというのが極めて重さを軽減する上では重要だということです。
こうしたことを申し上げると「そんな簡単に組織を分割できない」「組織を分ければ、追加で人を雇わないといけなくなるから、コスト高になる」「シナジー効果が失われてしまう」などの反応をビジネスパーソンの方からはいただきます。ただ、例えば、Aという商品とBという商品の両方を同一の工場で生産しているので、「当社の組織を分けて小さな事業部に分割するのはできない」みたいなことをおっしゃる方は多いのですが、実際に中を見てみるとAを作る生産ラインとBを作る生産ラインが完全に独立していているといったことが生産の現場や研究開発の現場で結構見られます。
そのため、組織をできる限り分けて小さな事業部にしていくことが、私たちの研究から「組織の重さ」を低減するために大事だと明らかになりました。

03「組織の〈重さ〉」を低減するには、小さな組織と計画の落とし込みが重要
「組織の<重さ>」を低減するために、中堅・中小企業の経営者に何かアドバイスや、経営のヒントをいただけますか。
そうですね。1個目の組織を小さくするというのは、中小の企業であれば、既に小回りが利いているということになります。この点は、どうしても組織が巨大になり、重くなりがちな大企業と比べた中堅・中小企業の利点であり、逆にいえば、そうした弱点を突いていくところに可能性があると思われます。
二つ目の我々の調査から明らかになった組織を健全に保つ上でのポイント、つまり軽い組織と重たい組織の違いとして、計画がよく見られているか、もしくは、計画が個人まで落とし込まれているかという点が挙げられます。
恐らく多くの方が、「計画は個人を拘束し、その場、その場の状況に応じた対応の足かせとなる。その結果として、計画に縛られているほど、調整に労力がかかるし、そうした組織こそが重たい組織であろう」といったイメージを抱かれるのではないでしょうか。しかし実は、我々の研究結果は、そうではなくてきちんと計画が立てられていて、またその計画が個人にまで落とし込まれ、さらにその計画を達成度合いと報酬がリンクしていたりして、計画に人が従っているほど「組織の重さ」は軽い傾向があるということが明らかになっています。簡単に言ってしまえば、事前にきちんと計画を立て、それを皆が見て動いていれば、事後に改めて調整に過剰な労力を割かなくて済むようになる、ということかと思います。この点については、大企業だけに限らず、中小企業の方はであったとしても有効な示唆なのではないかと考えています。
自社は組織として重いのか軽いのか、その判断軸というか判断指標はあるのでしょうか。
我々は組織の<重さ>を測るために12項目の質問を用意し、しかもそれぞれの事業部で7人以上の方に答えてもらう、というかなり大がかりな調査をしています。当然ながら、正確に診断しようとするとかなりの手間がかかります。では、直感で診断するのはどうか、となると、肌感覚と一致する場合もあれば、そうでない場合もあると思います。
元々この調査研究は、日本企業のビジネスパーソンの方々が当時、抱えているのではないかと思われた問題、つまり組織がとにかく重くて自分で何かしようと思っても組織が動かない、というようなところを発端にしています。そうした研究なので、ビジネスパーソンの方が直感的に判断される自分の組織は重たいな、というような感覚と、我々の調査が示す値はそれほど変わらない可能性はあります。
しかし他方で、特に大きな組織になってくると、自分で組織を全て見たり、感じたりすることは出来ませんから、例えば、事業部長クラスは組織が健全だと考えているのに、その下のミドルは現場を動かすのに苦労している、といったことは当然あり得ます。また、そもそも組織が複数の人で構成され、何らかの利害対立や調整が存在しないことはあり得ないことを踏まえれば、どの組織にも「重さ」は存在し、どれだけ重いかは相対的な問題だということになります。ただ、そうした相対的な位置付けは、組織の中にいる人にとっては分かりづらいかと思われます。
そうなると、何らかの客観的な測定が必要だということになります。組織の重さ調査では、実際にご回答頂いた方々はもちろんですが、企業で調査の窓口になって頂いた方にも、かなりお手間をおかけする分、得られた調査結果を、それぞれの企業に対してフィードバックを行っていました。かなりお手間をおかけした調査ではあるものの、それでも多くの方々にご協力頂けたのは、そのメリットもあったからだと考えています。
渡辺先生は、「組織における年齢ピラミッドと経営戦略」と題する講演もされておられます。どのような内容をお話になられるのですか。
先ほどもお話した通り、日本の特に大企業の中には、新卒一括採用と終身雇用、また新卒採用数を景気によって大きく左右させることで、年齢構成がかなりいびつになっている企業が存在します。このいびつさが企業にどのような問題を企業にもたらすのか、という問題を研究しています。まだ研究の途中であり、企業の方にお話を伺ったりしながら、どのような問題があるのか、様々な分析を進めている最中なのですが、これまでに明らかになった点をお話させて頂きました。
現在までのところ研究で明らかになったことは、すごく単純に集約できてしまうのですが、企業が戦略を転換することを考えると、ミドルの層の厚みが重要だということです。企業の中で、何か事業へ進出するとか、同じ事業であってもこれまでとはやり方を大きく変えるような場合、それを中核的な実働部隊となって支えるのはミドルです。そのため、そうしたミドルが少ないと企業は戦略を変えられなくなるということになります。既存のビジネスから撤退してこれから伸びていくようなビジネスに進出することができず、企業は今やっているような事実をずっと続けるしかなくなってしまうということです。こうした点を統計的な分析から明らかにしたというのが、今のところの我々の暫定的な研究結果ですが、他にどのような影響があるのかについて、まだ研究中です。
渡辺先生は、 「日本企業における経営者交代の影響に関する再検討:意思決定への影響と責任に注目して」と題する研究にも取り組まれています。研究の動向・成果をお聞かせいただけますか。
先ほど申し上げた通り、私は企業が変わるのか変わらないのかということを考えています。特に役員のレベル、役員構成のようなものから考えていますので、経営者交代の影響に関しても研究をしています。内容としては、かなり学術的なので難しくなります。実務的な問題意識とはかけ離れているかと思いますので、ここではあまり詳細には触れないでおきましょう。

渡辺 周氏
大阪大学大学院経済学研究科
准教授
2010年一橋大学商学部卒業。2015年一橋大学大学院商学研究科博士課程単位修得退学。
一橋大学大学院商学研究科特任講師、東京外国語大学世界言語社会教育センター助教、同大学大学院総合国際学研究院講師などを経て、2022年4月より大阪大学大学院経済学研究科准教授に。