>組織経営の一丁目一番地は、人的資源管理の理解なり(後編)
人口減少が加速する日本。どの業種・企業でも人手不足に悩んでいる。ただでさえ、採用難であるのに、転職も一般化。せっかく入社したとしても、数年後には辞めていくケースが珍しくない。「人材は貴重な経営資源」と理解していても、その人材が確保できないでいるのが実状。せめて、今働いている社員にできるだけ長く勤務してもらわなければいけなくなってくる。それが、昨今「リテンション」という用語が注目される背景なのかもしれない。
その「リテンション」にいち早く着目し、16年前に研究書である『人材定着のマネジメント』(中央経済社)を執筆されたのが、青山学院大学名誉教授の山本 寛氏だ。その後も、人的資源管理論やキャリアデザイン関連の著書を立て続けに世に送り出してきた。さらに、2025年には2冊の書籍を出版。その知識探求欲は留まることはない。今回も新たな論点を提示してくれた。インタビューの後編では、人的資源管理論の重要性や役割、今後考察していきたい論点などについて伺った。
目次

01人的資源管理の専門知識と施策を深く理解できる一冊を編著
さらに2025年5月10日には山本先生の編著書『働く人と組織のための人的資源管理―人的資本経営時代の基礎知識』(中央経済社)が出版されました。こちらは、どういった内容の本なのでしょうか。特徴をご紹介ください。
これに関しては、5つの特徴があります。まず、この本は元々、全国に約45000人いらっしゃる社会保険労務士の方々への研修システムの構築が出発点となっています。実は、全国社会保険労務士会連合会会長の方から、「労働法等と並んで、唯一の人的資源管理の国家資格である社会保険労務士(以下、社労士)に人的資源管理に関する専門知識を身につけてもらうような研修システムを作ってほしい」というご相談をお受けしました。それが発端です。
ご存じの通り、社労士の方も給与計算といった総務絡みの仕事は、IT化の進展によりどんどんなくなって来ています。やはり、今はコンサルティングにシフトしています。そうすると、人事の方と人的資源管理のテーマをやりとりするときに一定レベルの知識がどうしても必要になってきます。
二番目の特徴は、多くの人的資源管理論の体系的書籍に欠けている労働安全衛生等、社労士が関わることが多い分野を盛り込んだことです。そのため、類書より章の数はやや多くなっています。このように内容が多岐に渡るため全18章の構成とし、各分野を専門とする13名が執筆しています。
三番目は、現代社会における労働のトピックの多くに触れられることです。具体的には、人的資本経営、タレントマネジメント、組織開発(OD)との関係、同一労働同一賃金、健康経営、従業員エンゲージメント、キャリア自律等です。現代組織が抱えている新しい課題の多くを網羅しています。いずれも、企業の人事の方と話をするには知っておくべきものばかりです。
しかも、課題に触れられるだけでなく、施策面も深く理解できます。それが、四番目の特徴です。なぜかというと、経営者や管理者を含む現場レベルの問題解決に役立つことを目指しているからです。いわゆる、リモートワークや1on1ミーティング、社内公募制度、アルムナイ(卒業生)制度、多様なハラスメント対策等、現代組織で実施されている数多くの施策を取り上げています。
最後、五番目は新しいリーダーシップ理論、自己効力感等、学術的な理論やモデルに基づく新しい考え方や概念について深く学習されたい方にもお薦めできるテーマを取り揃えていることです。具体的には、PE fit(person-environmental fit; 個人と組織の適合、人と環境の適合)や組織(再)社会化(新しく会社や組織に参入した従業員が、会社や組織の環境ややり方に適応するためのプロセス)、シェアドリーダーシップ(所属している組織(チーム)のメンバー全員がリーダーシップを発揮している状態)等です。それらが、わかりやすく解説されています。

02社員に長く活躍してもらえる職場づくりが欠かせない
山本先生は、2025年3月15日に「構造的な人手不足解消に向けた人材定着(リテンション)のためのマネジメント」と題する講義をされました。参加者に最もお伝えになりたかった点は何でしたか。
こちらは二点ありました。まずは、とにかく構造的少子高齢化を背景にした採用難と人手不足が深刻であることです。といって、人手不足の対策として今まで何もしてきてこなかったわけではありません。AIやロボットの導入、そして新しい人材の導入として外国人労働者の活用、中高年労働者の活躍、女性労働者の活躍の促進が図られてきました。しかし、それらの施策だけでは限界があります。
例えば、人間が行って来たすべての仕事をAIやロボットに置き換えるところまでには至っていません。それに、大企業の工場ではFA(ファクトリーオートメーション:工場の生産工程を自動化していくこと)が進んでロボットやシステムがほぼ人間の労働の代わりをしていますが、中堅・中小企業では人が担ってきた仕事のAIやロボットへの全面的な置き換えには、導入費用等、相当のコストがかかり、限界があるということで、やはり人手に頼らなければいけなかったりします。
外国人労働者に関しては、我が国の技能を発展途上国に伝え、国際貢献することが主な目的だった技能実習制度から、日本国内の人手不足を補う人材育成と人材確保が主な目的の育成就労制度に変わってくることもあり、人数自体は増加してきました。しかし、大都市では高い賃金を支払えるので外国人労働者が集まりやすいものの、そこまで賃金を払えない地方には行きたがりません。ただでさえ地方は、人口減少に歯止めがかからないのに、都市部との賃金格差もあり、一部の成功例を除いて、全体的には期待通り進んでいないのが実状です。
もちろん、女性労働者の方も、非正規の比率が高いとか管理職比率が低いという欠点はあっても、労働力率(生産年齢人口に占める労働力人口の比率)は非常に高く先進諸国でもトップクラスにあります。また、定年の延長等により、中高年労働者の方で働いている人の労働力率は、もちろん非正規も含めてですが、先進諸国でもトップクラスにあります。つまりこれから、新しい人材が潤沢に入ってくるという可能性は低く、ロボットにも短期間では全面的に置き換わらない。そうなると、どうしても社員に長く勤続し活躍してもらうしかありません。自ずとリテンションが重要になってくるわけです。
なぜ重要かと言えば、少なくとも数年はその会社で研修とかを受けて、能力開発をしていただいて、組織の風土や文化にも慣れて働いている人に抜けられてしまうと非常に痛いからです。少しでも長く働いていただくというのが、やはり大事になってきます。なので、ここがとにかくポイントだということでお話しをしました。

03人的資源管理は日本の経済成長を支えてきた重要な要因
山本先生は、2025年5月13日に全国社会保険労務士会連合会が主催する『働く人と組織のための人的資源管理研修』で、「人的資源管理序論」と題して講演をされておられます。改めて、人的資源管理の重要性や役割をアピールいただけますか。
講演では、人的資源管理の重要性や役割、歴史や概念、わが国の組織における特徴や戦略的人的資源管理、経営労務監査や、特に近年注目されている人的資本経営についてお話しました。人的資源管理の重要性や役割としてお伝えしたいことは、二点ありました。
まずは、第2次世界大戦後の我が国の高い経済成長を支えた要因の一つに、我が国独特の経営のやり方である「日本的経営」が挙げられます。日本的経営の三種の神器として、終身雇用、年功処遇(序列)、企業内労働組合の三つがありますが、これらはすべて人的資源管理に属しています。すなわち、人的資源管理は我が国の経済成長を支えてきた重要な要因であるということです。
もう一点は、会社に入って非管理職のときには、それこそITや人事、営業等、色々な仕事をすると思います。ただ、どんな組織でも管理職になると、業務指導や業績評価、リーダーシップ等、それまで触れていなくても人的資源管理に携わらなければなりません。もちろん、管理職にならない方もおられるとはいえ、多くの方が管理職や管理職的立場になるとしたら、人的資源管理は多くの人にとって関係が深い分野だと言えます。だからこそ、ある程度は知っておいた方が良いと思います。
近年、社会保険労務士のニーズや存在感が高まっているのは、人的資源管理の重要性を多くの企業が理解し始めているからなのでしょうか。
確かに、それはあるかもしれません。ある社労士の方とお話をしたところ、「とにかく最近はコンプライアンスやハラスメント、人権という言葉が多く使われるようになって来ている」と指摘されていました。その辺りは、やはり社労士の専門領域ですからね。
そういう問題が一度でも起こり、SNS等で拡散すると会社のブランドや価値を毀損する大きな問題になりかねません。いわゆる、人が絡む問題ですよね。ということで、社労士はある意味、会社のリスクマネジメントを担保していく上でも重要だと思います。

04今後はエイジレス社会・組織の実現に尽力していきたい
山本先生が今後考察を深めていきたいとお考えの論点がございましたら、お聞かせください。
一言で言うならば、エイジレス社会への一里塚としてのエイジレス組織の実現です。「リバース・メンター」制度等を通じて、年齢による区別(差別)をなくし、意欲や能力に応じて活躍できる組織を創り上げていきたいのです。私は現代には、3つの「レス」があると思っています。エイジレス、ジェンダーレス、ペーパーレスです。このうち、最も進んでいないのがエイジレスです。年功序列はなくなってきたと言われますが、相変わらず年齢に基づく区別(差別)があります。組織で若手社員が活用されない、年齢を理由にした「エイジハラスメント(エイハラ)」といった、相手の年齢や世代を用いた差別的な言動が横行しています。
そうではなく、日本全体でエイジレス社会になってもらいたいというのが私の願いです。その一里塚として、会社・組織がエイジレス化していくことが重要になってきます。具体的には、年齢による区別や差別をなくして、意欲や能力に応じて活躍できる組織を目指していくことです。そのためにどんなことをしたら良いのかという具体的な施策が、「リバース・メンター制度」のさらなる普及です。
この制度は、1999年米国のゼネラル・エレクトリック(GE)で年長者がICTの使い方を若手から教わることを目的に始まり、その後P&G、Dell、Microsoft、Roche等に広がりました。日本でも、2017年頃から制度化する企業が徐々に増えてきています。恐らく、皆さんはメンター制度についてはご存じかと思います。先輩社員等がメンター(助言者等)となり、メンティである若手等の相談に乗り、キャリア形成を支援することです。その反対が、「リバース・メンター制度」です。すなわち、若手が上司や先輩社員に、逆方向(リバース)に技術や考え方等を助言し支援する仕組みを意味します。この制度が最も有名になったのはコロナ禍でした。台湾のデジタル担当大臣オードリー・タン氏が35歳以下のリバース・メンターを採用して初期のコロナ対策を進め、成果を挙げたことで注目が集まりました。
日本においてエイジレスが進んでいない結果として、組織ではまだまだ若手社員が活用されていなかったりします。若手社員の意見が取り入れられませんし、昇進では相変わらず年次や年齢が考慮されがちで、その結果やる気をどんどん失い辞めています。その一方、年齢を理由にした「エイハラ」も指摘されるようになりました。例えば、若手社員に「若いんだから○○すれば」等の言動、「若いことを理由に雑用をさせる」等や、中高年社員に「その年齢でまだ○○なのか」等の言動や、「定年が近いことを理由に仕事を回さない」等が該当します。
どうして「リバース・メンター制度」が求められているのですか。
基本はコミュニケーションの不足が大きな要因だと思います。日常的に世代や年齢が異なる相手とコミュニケーションを取っていないと、相手との間の「ジェネレーションギャップ」を理解できません。しかも、現代は人口減や少子高齢化による人手不足の深刻化もあり、世代を越えた交流や協力の必要性が一段と高まっています。
では、「リバース・メンター制度」では具体的に何を行うのかというと3点あります。一つ目が、若手がよく知っていてベテランが苦手な分野の伝授です。例えば、インターネットの上手な検索、ZOOM等オンラインツールの使い方、ツイッター(X)等SNSの活用法も若手の方が得意だと言えます。二つ目が、最新の知識・技術に関して好奇心や吸収力が高い若手から伝授することです。DXに関するAIやRPA等の知識を、新しいことに対する吸収力が高い新人・若手に会得してもらい、その知識をトップや経営陣等に伝え、DX経営に対する知見を深めていく必要があります。三つ目が経営、管理職向けに、現役子育て世代が子育てをする上で働き方の制約や会社に理解してもらいたいことを直接伝え、子育てへの理解を深めることです。今の経営者や管理職は育休を取得した経験がほとんどありません。子育てをした経験も少ないと言っても良いほどです。そうすると、仕事と両立するのに何がネックになっているのかが本当のところよくわからないので、実態に即した改善策等が見つかりませんし、現実的で役立つワーク・ライフ・バランス施策も構築できなかったりします。
「リバース・メンター制度」の発展段階には、幾つかのフェーズがあります。第1フェーズは、ICTに関するスキル・技術の移転、第2フェーズは、それ以外の分野の専門知識の移転・意見交換です。現在は第3フェーズに来ています。ダイバーシティやインクルージョン等の新しい考え方・価値観の共有や、異質な価値観の相互作用を通したイノベーションの創出を図る段階です。

05日本においても「リバース・メンター制度」の導入を進めるべき
「リバース・メンター制度」の導入メリットについても説明いただけますか。
5点挙げたいと思います。一つ目は、若手社員のメリット。これに関しては、コミュニケーション能力の向上が指摘できます。二つ目は、上司、経営者の利点です。上司も経営者もマネジメントされる側の気持ちを理解することができるようになるので、部下の指導や育成のスキルアップができます。三つ目は、共通のメリットです。働きがいやエンゲージメント増進につながります。四つ目は、部署やチーム、組織全体のメリットです。これについては、階層が逆転し、通常の階層に依存しない関係性を構築でき、相互学習ができますし、知識の共有、文化や世界観の共有が進みます。最後、五つ目が社会全体のメリットです。間違いなく、「リバース・メンター制度」はエイジレス社会、エイジレス組織の実現への突破口になる可能性が大です。年齢による区別(差別)をなくし、意欲や能力に応じて活躍できる組織を創出していくことができます。
現状における「リバース・メンター制度」の実施状況は、どうなのですか。
非常に低いというのが実態です。少しデータが古いのですが、富士通総研が2017年に実施した調査結果によると、「何らかの形で経験がある」と回答した方は7.4%でした。ただ、割と効果があると思っている人が多くて、「互いに信頼できる関係を築くことができた」(48.2%)、「仕事上の課題を克服し、より効果的なアプローチをとることができた」(44.5%)、「会社・部署全体に有益な結果や成果をもたらす」(44.1%)などの割合が高かったです。
では、なぜ日本では「リバース・メンター制度」の導入が普及していないのかというと、まだまだ日本では年齢や勤続年数による序列意識が根強いからです。上意下達の仕組みと言い換えられます。年上の人の方が知っていて、それをOJTなどを通じて若手や年下に教えていくと言う意識が未だ残っています。それに、「リバース・メンタリング」や「リバース・メンター制度」というネーミングも堅すぎます。「ヤング・メンター制度」と表現を変えてみるだけで、親近感がぐっと高まる気がします。
それでも、日本国内でもP&G日本本社や資生堂、住友化学、岩手県庁、富士通ソフトウェアテクノロジーズなどと導入事例が増えてきています。今後さらに「リバース・メンター制度」を広げていくためのポイントとして、私は4点あると思っています。まずは、シニア社員や経営トップの問題意識による働きかけによって導入すること。第二に官庁で実施し、成果を公開してもらうこと。第三に入口として、制度化されていなくても実質的に行われている例を探索して推奨すること。そして、最後は人事部門が調整役として重要な役割を果たしていくことです。容易ではないかもしれませんが、何とか実現できるよう私も尽力していきたいと思っています。
―山本先生の今後のご活躍を期待しています。本日は貴重なお話をありがとうございました。
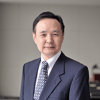
山本 寛氏
青山学院大学
名誉教授
キャリアデザイン論担当。博士(経営学)。メルボルン大学客員研究員歴任。働く人のキャリアとそれに関わる組織のマネジメントが専門。日本経営協会 経営科学文献賞などを受賞。大学では、人的資源管理論とキャリアデザイン論を担当してきた。主な著書(単著)は『連鎖退職』、『なぜ、御社は若手が辞めるのか』、『「中だるみ社員」の罠』(以上、日経BP社)、『自分のキャリアを磨く方法』(創成社)、『人材定着のマネジメント』(中央経済社)、『働く人の専門性と専門性意識』、『昇進の研究』、『転職とキャリアの研究』、『働く人のためのエンプロイアビリティ』(以上、創成社)など。2025年2月に『人事労務担当者のための リテンション・マネジメント-人材流出を防ぐ実践的アプローチ』(日本法令)を出版。
