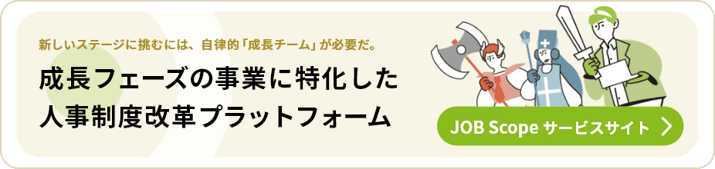近年は、経営学や経済学の領域においても心理的なアプローチが脚光を浴びいている。もはや、心理学は臨床と教育だけのものではなく、職場や産業でも応用されようとしている。日本において、その流れをけん引してきたのが、立命館大学総合心理学部 教授の髙橋 潔氏だ。産業・組織心理学、組織行動論の第一人者として広く知られている。未来が見通しにくい現代社会。特に日本は閉塞な状況を脱しきれず、未だにもがいている。人的資本経営の時代において、日本企業はいかに組織の競争力を高めていけば良いのかを髙橋氏に聞いた。インタビューの後編では、アセスメントの重要性や人事評価の在り方などを語ってもらった。
目次

01タレント・マネジメントにトレードオフを想定する必要がある
最近はタレント・マネジメントも注目されています。アセスメントの重要性についてご説明いただけますか。
タレント・マネジメントにおけるトレードオフを、しっかりと理解をしてほしいと思います。トレードオフがどこにあるかというと、アクイジションとリスキリングです。流動化している労働市場からタレントを獲得する、確保するという考え方と、リスキリングによってタレントを固定化する。この2つに関して、トレードオフを想定する必要があるというのが、僕の考え方の一つのまとめです。
どういうことかと言うと、大学院のクラスでもこんな話をしています。タレントと称するものを会社の中で活用する時に、採用選考を通じて外部から採ってくる役割と、内部で育成をする役割は、そもそも両方とも同じことを目的にしています。同じ目的のためだから、どちらかをやればどちらかはやらなくて良いという帰結になるはずです。もし、採用選考と育成がトレードオフ関係にあるとすれば、採用選考が完璧ならば、職務を十分にこなせる能力を持つ人材を、外部・内部市場から調達できるので、育成は不要となります。
逆に、もし育成が完璧ならば、どのような人材に対しても、教育訓練によって必要な能力を醸成できるので、丁寧な採用選考は不要。誰を採っても良くなります。それこそ、先着順やくじ引きで人を採っても、育成がしっかりしているから問題ないということになってきます。実際には、良い人を採って良い教育をしようとするわけですから、両方の合わせ技、ハイブリッドなわけです。ただし、ここにトレードオフがあると考えると、これまで慣習的に行ってきた人事施策に対しても、お金のかけ方を考えたり、大所高所から距離を置いて眺めることができます。
これは現代的に言うと、アセスメントを通じたアクイジションとリスキリングは、同じ目的のことなので、総額人件費が固まっているのであれば、どちらにどれぐらいの力を割けば良いのかという考え方ができるはずです。今この国では、リスキリングが極端に推進されている気がします。日本の組織の特徴としては、「我が社は人材育成に自信があります」というようなことばかりを言ってきました。そういう会社の倣いがあるので、足りないものはリスキリングすることによってという流れになるのは順当だと思います。ですが、トレードオフ関係を意識していくと、アセスメントを通じたアクイジションを丁寧にすることによって、リスキリングのコストを有効に使うことができるのではと思います。これはバランスが大切なのですが、トレードオフを意識したら、人事にも面白い発想が出てくる気がします。
人材アセスメントの方にフォーカスすると、アセスメントするものは何かという問題が端的に現れてきます。評価要素の問題です。具体的には、能力・職務遂行能力。行動・コンピテンシー、パーソナリティ、エンゲージメント・職務満足、メンタルヘルスなどが挙げられます。
アセスメントは、どういう方法で何を評価するかを表す概念です。現状では評価要素ごとに、アセスメントのメソッドがあらかた固まっています。固着した認知の枠組みと運用を改めて、自由な発想で組み合わせたり、新しいメソッドが開発されると、自社にフィットするアセスメントのあり方が考えられると思います。

02職場のウェルビーイングをアセスメントする「WACMモデル」
職場のウェルビーイングは、どのような視点で捉えていけば良いとお考えですか。
元々、メンタルヘルスは、精神的健康を維持するポジティブな意味合いなのですが、うつや不健康といった良くない意味で使われることも多いと言えます。それに代わって、ウェルビーイングが今すごく流行っています。世界保健機関(WHO)憲章では、ウェルビーイングを「病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも社会的にも満たされた状態」と定義付けています。ただし、医療の領域に留まってしまう傾向があり、自分で食事が摂れる、自分で排泄処理ができる、自分で家事ができる…、そういう健康寿命やQOL(生活の質)に関係した概念として捉えられています。ウェルビーイング経営という言葉が目新しく響きますが、もともと健康やメンタルヘルスの流れで考えられてきたので、職場のウェルビーイングだけを取り出すことはあまりないし、あまり熱心な取り組みがなされているとはいえません。
ウェルビーイングが展開してきた中で、米国ペンシルバニア大学教授のマーティン・セリグマン氏は、「PERMAモデル」を提唱しています。ポジティブ心理学の流れを汲んで、以下の5つの要素でウェルビーイングを考えていこうというものです。
この中に、エンゲージメントという言葉があるので、労働領域で流行りのエンゲージメントと似たようなものが捉えられています。PERMAモデルは、今普及している最もポピュラーなモデルです。なので、PERMAモデルでウェルビーイングを考えていくのが順当であると思われています。ただし、生活における良さと質のようなものを中心に考えられているので、職場のウェルビーイングに関しては疑問符がつきます。
そこで、今僕自身としては、仕事快適・仕事有意義・関係快適・関係有意義の4つで、職場のウェルビーイングをアセスメントする「WRCM(ワーコム)モデル」を推奨しています。職場のウェルビーイングを4領域24項目で測り、偏差値化していくものです。
快適さと有意義さは、両方ともウェルビーイングを意味しています。伝統的に、ウェルビーイングは大きく二つで考えれば良いと言われています。一つは、ヘドニック・ウェルビーイング(へドニア)です。これは、喜びや幸福や快適さなどのポジティブな感情、いわゆる快感のようなものを経験することや、不安やうつといったネガティブな感情がない状態を言います。
もう一つが、ユーダイモニック・ウェルビーイング(ユーダイモニア)です。こちらは、人生の意義や目的のために善行を積んだり、悟りを求めて修道するような良き生き方を指します。たとえ不快や苦痛があっても、それを行うことに価値があるとか、望ましいと感じている状態です。
これを職場にあてはめてみると、快適に働いているというのと、働き方が有意義であるとの二つにわけられます。さらに、仕事の領域と関係の領域をクロスさせます。後者には人間関係だけでなく、社会や国際関係や自然環境など自分より大きな存在との関係、スピリチュアルなものとの関係も含めての関係性となっています。これら4つの次元を設定して、仕事快適・仕事有意義・関係快適・関係有意義という4つの因子で捉えていこうとしているのがWRCMモデルです。
従業員がいきいきと働ける職場は、ダイバーシティ&インクルージョンの時代に、組織が求めていくべきものです。給与や労働時間や有給休暇などの条件がよければ、従業員のウェルビーイングが高まります。また、職場のウェルビーイングが高ければ、労働条件にかかわらず、生産性が高く、欠勤が低くなります。組織全体の業績をアップさせるスタートは、職場全体のウェルビーイングを把握することから始まります。
従業員のウェルビーイングの現状を偏差値として把握できるとしたら、次にどのような支援をすれば、職場のウェルビーイングが保たれるかということにアプローチできます。組織全体で見ると、職場のウェルビーイングの高さで、そのユニットの生産性がどれほど高まっていくのかが把握できます。最終的には、ウェルビーイングの高い組織は、事業全体の利益や企業全体のパフォーマンスと繋がるのか、あるいは株価とどのように繋がるのかも把握できる手立てになると思い、一生懸命リサーチと実査を続けているところです。

03新たな視点で人事評価の目的や仕組みを考えたい
人事評価についても何か新たな視点はございますか。

僕なりに二つ考えています。一つは人事評価のメッセンジャー機能です。人事評価の目的を整理すれば、まずは、昇進・昇格・賞与・配置など処遇を決める管理目的で、人事評価がなされてきました。それに加えて、能力開発や人材育成など人をどのように育成していくか、活かしていくか、そのために能力開発の目的で評価を行う流れがありました。この二つで大体押さえられてきたのです。
しかし、1on1ミーティングが実践され、成果の評価や育成の目的で評価を行う意味が薄れてくれば、人事評価に新たな視点が求められています。評価をみれば、会社の中で誰が優遇され、何が評価されるのかがおおよそわかります。それは組織のバリューなのであって、人事評価の仕組みを見れば、その会社の価値を映し出す鏡になっていることがわかります。会社のバリューを端的に落とし込んだのが人事評価なので、年長者が優遇されていれば、前例と経験を重んじ革新を嫌う組織であることを、出した成績によって処遇が大きく左右されるのであれば、成果を主に考える組織であることを、従業員は感じ取ることになる。評価制度は組織の「価値」や「経営理念」「経営哲学」を,わかりやすく実感を持って伝える役割があります。なので、メッセンジャー目的として考え直していく必要があると思います。だから、実は「評価で上になった」「下になった」と言って一喜一憂するのではなくて、従業員としては、会社の大切にしている価値観は何かを評価から読み取り、人事部としては、メッセンジャーとしての意味合いを制度の中に組み入れていく必要があると、主張したいと思っています。このメッセンジャー機能が、第一の視点です。
もう一つの視点は、人事評価の未来です。人事制度の未来、評価の仕組みの未来がどうなるかです。僕が考える人事評価の未来は3つあります。一つ目が、「スーパー成果主義」です。一握りのスター社員が引っ張る成果の非正規分布に対応する制度で、客観成果をベースに処遇する成果主義の発展形と言えます。売れるものと売れないものの格差が大きく広がっている時代には、成果主義を振り切って、本当にスーパーな成果を出した人にきちんと処遇していく仕組みが必要です。吉本興業の芸人さんを見てください。明石家さんまやダウンタウンのように数億円プレーヤーがいる一方で、バイトして生活をつないでいる芸人もいます。これまで、成果に見合った処遇がされずに不満を抱えていたスター社員に対しても、不満を解消し厚遇できるわけですが、その一方で、他の社員からは格差不満の声が出る恐れがあるので、処遇格差が受け入れられやすい組織文化・競争文化が必要となってきます。
二つ目が、「戦略主義」です。例えば、DX人材や変革型リーダー人材など、競争戦略・成長戦略に合った人材を高く評価する人事制度を言います。これは、人的資本経営にも対応する考え方です。いわゆる経営戦略に合わせて人事戦略がないといけないので、経営戦略に合致した人を高く処遇していく仕組みとして立ち現われて来ると考えています。この場合、外部人材・異能人材に依存することがあるので、内部昇進・内部処遇の仕組みと齟齬が生じてしまう可能性があります。それだけに、人事制度の複線化や制度変更が欠かせません。
三つ目が「貢献主義」です。これはメンバーシップ型を維持したままで、成果ではなく組織への貢献を評価するという形で、評価のあり方を見直していく考え方です。目標管理の仕組みの中で目標に当たるものを、例えば金額ベースでの成果をやめてみる。そして、部下を何人育成するとか、イノベーションのためのアイデアをいくつ提案するとか、メンタルヘルスに関する相談窓口をスタートさせるとか、介護休暇のサポート情報をまとめて開示するとか、あくまでも自分が主体的に組織やメンバーに貢献できる目標を立て、それがどれほど達成できたのかという軸で、評価のポイントを定める制度となっています。目標管理の仕組み自体はそれほどいじる必要はないので、成果主義から貢献主義へと考え方と枠組みを変更していくことで、メンバーシップ型を維持しながらも、会社に役立つことを柔軟に評価しあえる仕組みができると思います。また、ワークライフバランスやメンタルヘルスなど、貢献の基準が多様に設定でき、働きやすい職場につながるメリットもあります。その半面、企業成果や成長につながらない可能性も否めません。
それぞれに一長一短があるので、どれを取るかは各社の判断に任されます。こうした三つの可能性の中で、それぞれの組織に一番しっくりくる仕組みや制度を作り、自社の人事哲学を従業員に伝えていくのが良いと思っています。

04人事のファンクションは、経営者を支える右腕となること
最後に中小・中堅企業の経営者や人事責任者へのメッセージをお願いいたします。
人事担当者は経営者の右腕になる、企業の経営者は自分の右腕をみつける。そうした「右腕理論」を実践していただきたいです。ちなみに、国民生活金融公庫総合研究所の『新規開業白書』では、右腕を「経営者を補佐するパートナー、重大な判断を下す際に相談するような人、もしくは欠けると経営が成り立たなくなるような人」と定義しています。
会社の仕組みを見ていくと、日本の企業でも海外の企業でも1人で何かを決めていくのではなく、多くがペアリングの下、パートナーシップを持って経営を実践してきました。例えば、本田技研工業であれば本田宗一郎に対する藤沢武夫、ソニーであれば井深大に対する盛田昭夫。アップルであればスティーブ・ジョブズに対するスティーブ・ウォズニアックです。こういうペアリングが従来は見られました。ビジョンを推進したり、未来を見通すのが上手い人と、お金の面や人事のコントロールをする人のペアリングが、すごく大切だということを示す例でしょう。
今は優良な企業であれば、リーダーシップチームという形でCEOの下に、CFO(最高財務責任者)やCHRO(最高人事責任者)など、何人もの人がチームとなって経営を担う流れが当たり前となっています。経営者に対してどのようなサポートをするのか、その補佐役が必要なのは今も変わりません。
右腕となる人がどのような役割を担っているのか、ベンチャー企業に調査したデータがあります。上位の3つを回答してもらったのですが、それによると技術面での補佐や営業面での補佐、経営管理面での補佐など実務のサポートが上位に上がっている一方で、精神面での補佐がトップに位置付けられています。経営者は、1人で資金繰りに困り、自分たちの持っている技術で本当にやっていけるのか、色々な不安があるものです。ストレスと一言では片づけられない心理的重圧が、幾重にもかかってきて、夜も眠れないなんてこともあるでしょう。そんなときに、きちんと相談に乗れる人、悩みを真剣に聴いてくれる人が、右腕として傍にいないと、しっかりとした経営が成り立たないだろうと思います。往々にして補佐役の人選には、実務の専門性が判断材料とされてしまいますが、実務もわかって心理も理解できる人材を選ぶのがよい。精神面のサポートこそ、右脳人材が担う重要な役割であると、調査結果を見て目を開かされました。
経営者としてみれば、ワンマンで行けるところまで行っても良いのですが、人的資本経営の下で人事に要求すべき点があるとしたら、右腕となって自分を支えてくれる人材、困ったときに見て見ぬふりをしたり、責任逃れをするのではなく、わがこととして考え、精神的に支援してくれる人材をしっかりと選び出していく。そこに戦略人事のファンクションの意味合いを、感じてもらう必要があります。
人事部としてみれば、経営者は孤独であることを理解し、ストレスや無力感で押しつぶされそうになる経営者を、親身になってサポートをしていける人材をいかに供給できるか。あるいは、自分たちがどうやって会社のトップを支えることができるかを、意識していく必要があると思い、「右腕理論」の効用を論じました。「人事は他人事」などといううがった見方は、MBA出身のドライな経営専門職の言うことです。経営者も人の子で、理性でドライに割り切れない悩みを抱えるものです。浪花節ではないものの、右腕をキーワードにして、企業戦略に資する人事のファンクションを捉えていくのが良いでしょう。
――髙橋先生、貴重なお話をありがとうございました。
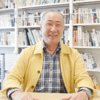
高橋 潔氏
立命館大学総合心理学部 教授 ╱
立命館大学大学院人間科学研究科 教授 ╱ 神戸大学 名誉教授
1960年大阪府生まれ。1984年、慶應義塾大学文学部卒業。1996年、ミネソタ大学経営大学院修了(Ph.D.)。南山大学経営学部および総合政策学部助教授、神戸大学大学院経営学研究科教授を経て、2017年より現職。専門は産業・組織心理学、組織行動論。人事評価やコンピテンシー診断など、企業と人のマネジメントについて心理学的視点からアプローチ。近年、ウェルビーイング経営に関する研究にも取り組んでいる。経営行動科学学会元会長、日本労務学会元常任理事、人材育成学会常任理事、産業・組織心理学会理事、日本心理学会代議員などを歴任。著書に、「ゼロから考えるリーダーシップ」(東洋経済新報社)などがある。