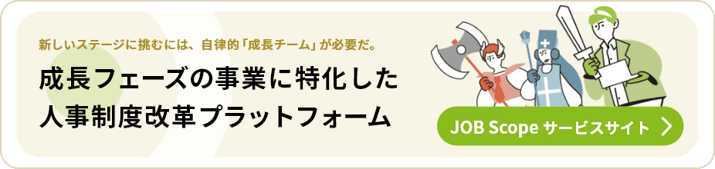人的資本経営がクローズアップされる昨今、日本でも人的資本や情報開示への関心が高まっている。ただ、果たしてどれほどの人がその本質を把握しているのであろうか。「言葉だけが先行しているのではないか」と疑問を呈するのが、30年余に渡り人的資本理論と人間行動の経済学的なアプローチを研究し続けたきた一橋大学大学院経営管理研究科の教授・小野浩氏だ。今こそ、人的資本の意味や人的資本投資の必要性をしっかりと理解すべきだと説いている。インタビューの後編では、人的資本と企業価値をつなぐ条件や経営者へのメッセージなどを語ってもらった。
目次

01ハピネスやウェルビーイングが、人的資本と企業価値をつなぐ
小野先生は人的資本を企業価値に効果的に繋ぐ条件として、エンゲージメントを含むハピネスやウェルビーイングを置くと指摘されています。その意味合いを教えていただけますか。
私の研究背景で言うと、長きに渡り人的資本や働き方を主に研究してきました。2000年代に入ってからは、幸福度の研究を始めました。働き方とハピネスの研究を別々に扱っていたわけです。我々の世界には多くの場合共同研究者がいます。私の場合、共同研究者は働き方とハピネスでは全然違う人たちだったわけです。この5年、6年でそれぞれの研究領域が少しずつ融合してきたのです。それで、働き方とハピネスがどのように結びついているかという話が出てきました。
先行研究を引用して言うと、今まで働き方とハピネスでは相関があると指摘されていました。それが最近では、こんな因果関係が出始めたのです。生産性が高いからハッピーなのではなくて、ハピネスが生産性を高めると、確実に矢印が見えてきたのです。これは、労働経済の世界では画期的な発見だと思います。マスコミはあまり気にせずに因果関係を言い出しますが、学者はすごく慎重です。なので、その因果関係がわかるということ自体が我々の世界では驚きであったと言えます。
その辺りから人的資本とハピネス、生産性みたいなものを考えると、やはり両方が必要だという気がしています。ものすごい優秀な人たちがいても職場環境が整っていなかったら、能力は発揮できません。逆に、ハッピーな人だけいても、皆能力が低かったら生産性は上がりません。優秀な人が集まった良い組織にウェルビーイングを高める仕組みがあったら、ものすごく生産性がアップするわけです。
最近私は、Googleを視察してきました。すごい優秀な人を使い込んでいて、彼らがパフォーマンスを発揮できるような土壌を作っています。そういう仕組みに少し関心が出てきたわけです。
それとモチベーションを高めるような条件として、例えば性善説や心理的安全性(自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して表現できる組織状態)、自律性(物事を進めるにあたり他者から支配されたり、強制されたりすることなく、自分自身で規範や計画を立てて、自らの考えで目的達成に向けて行動すること)、良い人間関係などが必ず必要になってくるという論文を2017年に執筆しました。
働く質を高めるための基礎条件─事例研究からの示唆
小野 浩(一橋大学教授)著

02人的資本が企業価値に与える金額の計算モデルを開発中
小野先生は、「人的資本理論の実証化研究会」の座長もされています。組織の目的と活動内容を教えていただけますか。
この研究会では、人的資本を「能力」と捉え、企業価値や業績にどのように寄与しているのかを検証しています。
人的資本理論の実証化研究会
毎月勉強会が行われ、まず私がその場で必ず参加企業に人的資本理論と実証化の話をさまざまな切り口からしています。別のチームが参加企業からデータを集めて、それをフィードバックするという、そうした位置付けです。理論だけではなくて、産学連携により実証化にも結びつけていくということです。
2022年の設立ゆえ今年で3年目を迎えました。その中で扱って来たテーマを、さらに深みを入れて出版したのが、『人的資本の論理 人間行動の経済学的アプローチ』です。
人的資本が企業価値に与える金額を計算できるのですか。
研究会で複数の参画企業のデータを使って分析しながら、並行して、各企業においても計算モデルを作成する支援をしています。モデルのベースを作り、データを一定期間貯めて検証を繰り返して精度の高いモデルを作っていく必要があります。学術的な研究会なので、そこまでたどり着くためには色々なハードルがあります。例えば、社会学・経済学ではパネルデータ(特定された個人または企業を定期的に追跡するデータ)も取らないといけません。今年どれくらい人材育成にお金を使って、今年どれだけ売り上げが高まったかなどを知りたくても、その二つの因果関係はわかりません。また、今の企業業績は過去の人材投資から得られることですから、遡ってデータを取得する必要があります。このように適切なデータを蓄積しながら検証していくことで、人的資本が企業価値に与える金額を計算できると考えています。

03人的資本経営と人的資本がかみ合ってない
2023年3月期決算から、人的資本の情報開示が義務化されました。企業の取り組みをどうご覧になられますか。
厳密に言うと、情報開示項目は人的資本の直接の指標ではありません。例えば、ダイバーシティやエンゲージメントは、インフラ作りの指標です。決して、直接的な人的資本の指標ではありません。私の位置付けとしては、こういった条件が整っていれば人的資本の発揮度を高めることができるということで、情報開示自体が無駄な努力であるとは思っていません。そのポジショニングとしては、人的資本が上手く回るのかどうかを判断するための材料だと思っています。
もう一つは、私の懸念として情報開示が目的化されているようなところがあります。そこも気になりますね。
今後、日本企業が戦略的開示を進めていくために大切なことは何でしょうか。
これも、私の研究会で良く話すことです。情報開示の目的が良くわかっていないというのと、現場でやっている人たちがwhyを十分理解していません。なので、その両方が必要です。全体像が良く見えていないのに、「とにかくこのデータを集めてこい」と上から指示されてやっているので、現場の人たちからするとやりがいを全く感じていません。whyがわかっていないから、下手をすると継続しないかもしれません。
なので、目標をはっきり理解してもらうことが重要です。ただ、やはり上の人も理解していなかったりします。人的資本経営と人的資本がかみ合っていないのだと思います。

04賃上げから生産性向上を見込むのは危険な思い込み
中小、中堅企業の経営者や人事責任者へのメッセージをお願いいたします。
一般的な見方として、中小企業は大企業に比べたら意思決定が早くて柔軟性があると思います。その気になれば、人的資本の発揮度をどんどん高められる条件をそろえられるはすです。ただ目先の生産性向上を目指して、決まり事やルールを増やすのは良くないと思います。持続可能性を考えると人的資本の継続的な投資が必要になります。
昨今賃上げが話題になっています。賃金が上がること自体は良いことですが、なぜ賃金を上げるのか、いろいろな調査結果からわかったその理由とは、企業が賃上げを通して従業員のモチベーション向上を期待しているということでした。。確かに賃金を上げたら、モチベーションまたは生産性は高まるかもしれない。しかし(拙著『人的資本の論理』でも説いているように)、これは短期的な効果に過ぎず、持続可能ではありません。人的資本のストックを高めて生産性が高まり、付加価値が向上して賃金が上がる、そういった流れが人的資本投資から始まるのです。繰り返しますが、賃上げから生産性向上を見込むのは危険な思い込みです。
それは経営者からしてみれば聞きたくないことかもしれませんが、人的資本投資からしてみれば、生産性向上が伴わない人的投資は付加価値の向上に繋がらないわけです。中小企業も賃上げムードになっているのは良いのですが、それを持続可能にするためには、必ず人的資本投資を継続的に行っていただきたいと言いたいです。
「何故、日本の生産性が停滞しているのか」「どうして日本経済が伸びないのか」と言えば、答えは簡単です。この30年間ずっと人的資本投資を怠ってきたからです。1990年代のバブル経済崩壊の結果、長期雇用を重んじ、人員削減を避ける傾向が強い日本企業は、大量の余剰人員を抱え込んでしまいました。その反動として、人を資産ではなくコストとして扱ってしまい人件費を削減することだけを考えるようになりました。また、正規社員よりも割安で採用でき、しかも長期にコミットしなくてよい非正規雇用を増やしました。そうした節約ムードから入って来ているので、人に投資するという発想が浮かばなかったのです。これからは、もっと人に投資をして人を育てる。人が成長すれば企業も成長する。そうしたステップへと踏み出していただきたいとお伝えしたいです。

小野 浩氏
一橋大学大学院
経営管理研究科
国際企業戦略専攻 教授
早稲田大学理工学部卒。野村総合研究所コンサルタントを経て、シカゴ大学大学院社会学研究科博士課程修了、Ph.D取得。ストックホルム商科大学准教授、テキサス A&M 大学准教授を経て2014年より現職。 2017年スタンフォード大学客員教授。現在、テキサス A&M 大学特任教授も務める。専門は人材マネジメント、人的資本理論、幸福度、統計学。著書に『人的資本の論理 人間行動の経済学的アプローチ』(日本経済新聞出版)などがある。