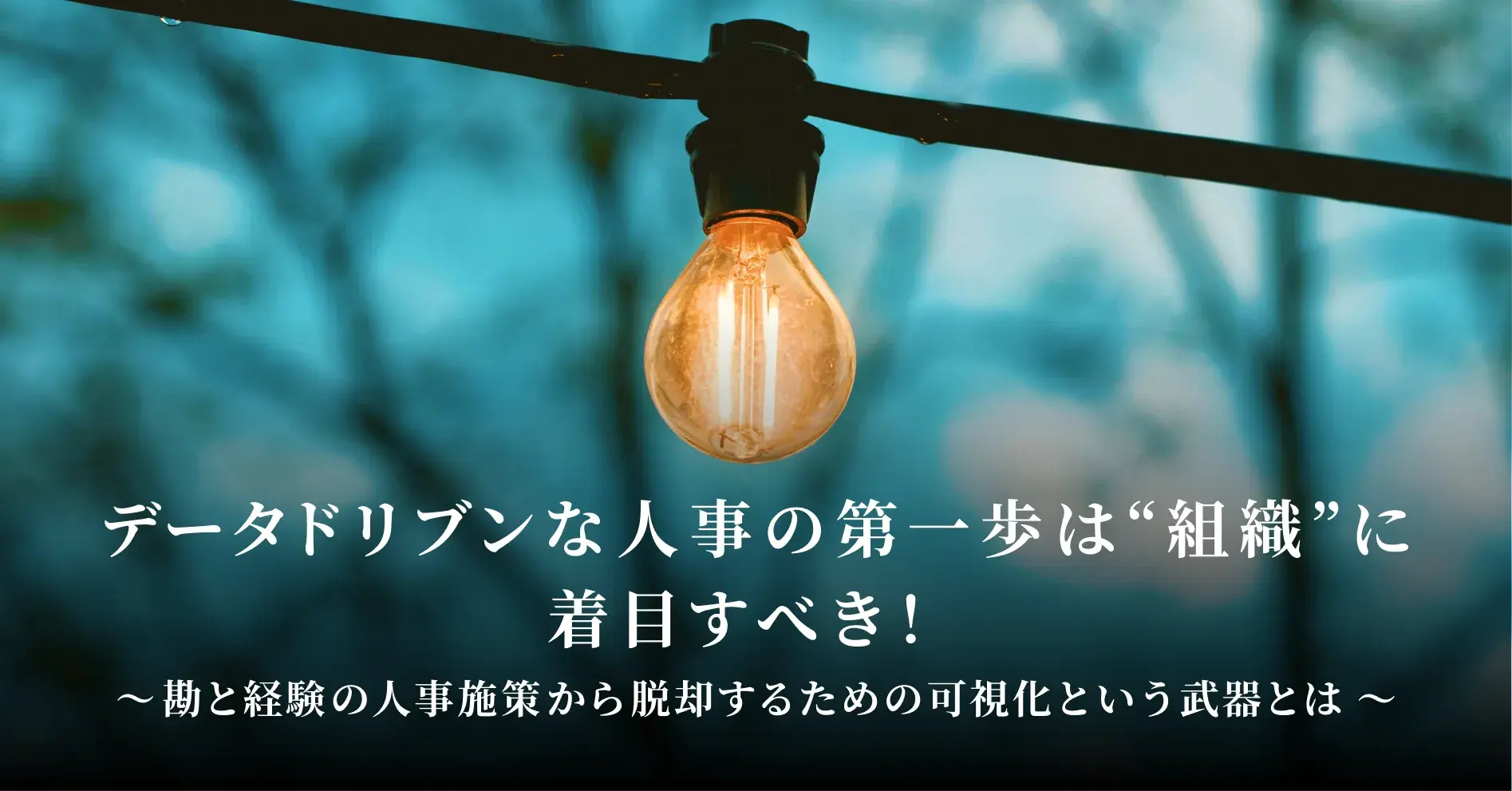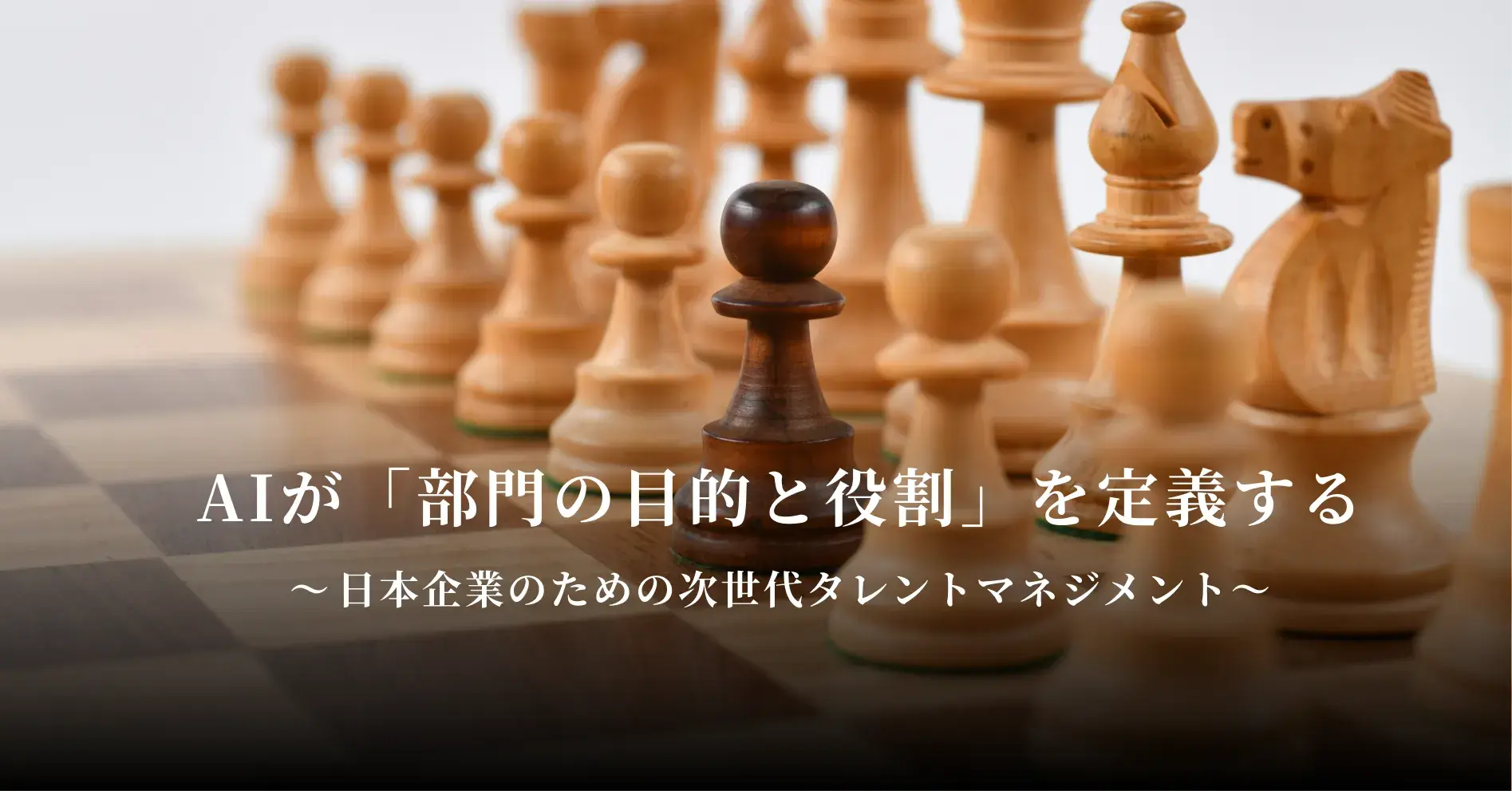第16回
あなたの会社の社員は‟ホンネ”を話していますか?
~思わず本音で回答してしまうサーベイ設計のコツとは~
2025/10/24
人事・マネジメントの方々は、「社員が本音で話してほしい」と願いつつも、「果たして社員は本音を出せているのだろうか? 」と疑問を持つこともあるかと思います。
一方で、人事やマネジメントという「役割」がある自分自身も、「社員やメンバーに弱音を吐いてはいけない」と思い込み、苦しい場面であっても虚勢を張ってしまったり強がったりすることはないでしょうか。
特に「ジェネレーションギャップ」に代表されるような年齢差がある場合は、本音でのコミュニケーションは難しくなる傾向にあります。
若手メンバーの本音を引き出そうと趣味やプライベートの話を持ち掛けても、違和感がある話題が空回りして、かえって場が硬直してしまうとの声もよく聞かれます。
今回は、そんな状況でも社員が思わず本音で回答してしまうような、生成AIを活用した最新のサーベイの取り組みについて解説します。
従来型の画一的なサーベイでは、相手ごとに合わせた質問設計ができないため、なかなか社員の本音や率直な意見は引き出せませんでした。
直接コミュニケーションや従来型サーベイだけでは、社員の素直な意見を引き出しにくいとの課題感をお持ちの方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
日本企業での「本音」の状況とは
前提の国民性として、日本人はあまり自分の本音を周囲にオープンにしない「奥ゆかしい」傾向は強いかと思います。
ただ他者との集団で働く企業人という立場上、周囲とコミュニケーションを取らないと、業務推進はできないでしょう。
仕事で必要なコミュニケーションはあったとしても、「本音」に着目すると、その状況はどのようなものなのでしょうか。
ある調査では、上司との面談で「全く本音で話していない」と回答した人は41.6%、チーム内の会議では43.0%に上ります。
さらに「本音で話せる割合が2割未満」と回答した人を含めると、過半数以上の従業員が本音をほとんど話していない状況です。
もちろん、仕事上のコミュニケーションや情報共有ができていれば、たとえ本音を話していなかったとしても、問題はないのかもしれません。
一方、マネジメントの観点に立つと、ざっくばらんにコミュニケーションを取ってほしいがために、1on1ミーティングをはじめとする施策をやっているわけです。
それなのに半数に近い割合のメンバーが「本音を話していない」としたら、かなりショックを受けてしまいかねません。
マネジメントとメンバーの認識ギャップに着目すると、さらに興味深い調査結果もあります。
一般職が「上司との面談で本音で話せている」と感じている割合は55.6%ですが、上司側は70.0%と認識しており、14.4ポイントのギャップが存在します。
ではなぜ、メンバーは本音を話さないのでしょうか。
調査結果で上がった意見としては以下のようなものでした。
| 要素 | 具体的な心情 |
| 自分への無関心 | 相手が自分の話に興味を持っていないと感じてしまう |
| 情報漏えいへの不安 | 話した内容が意図しない相手に伝わってしまうことへの不安 |
| 評価への影響 | 本音を話すことで自分の人事評価が下がるのではないかという懸念 |
| 関係性悪化の懸念 | 本音を話すことで相手との関係が悪化するのではないかという心配 |
個々人によって色々な要因があるかもしれませんが、マネジメントとしては上記のようなメンバーの懸念・不安を先回りして解消する必要はあります。
ひとことでいうと「本音で話しても大丈夫」という環境を作り出すことが重要でしょう。
本音が出る職場にはどのようなメリットがあるのか
本音でコミュニケーションがとれる職場では、どのようなメリットがあるのでしょうか。
本音で話せた方が良いと頭では分かりつつも、具体的なメリットはよく分からないという声もよく聞かれます。
本章では本音で話せる職場の、代表的なメリットを4つご紹介します。
メリットと合わせて「本音のコミュニケーションが成立していないと、どのようなリスクがあるのか」という観点で、本章をお読みください。
1. 心理的安全性が高まり、挑戦しやすくなる
本音で話す環境が整うことで、メンバーの心理的安全性が高まります。
その結果「失敗しても大丈夫」「正直に言っても否定されない」という安心感が、チャレンジ精神・創造性を引き出します。
Google社の研究でも「心理的安全性」は最も成果につながりやすい要素といわれています。
前章で出た「人事評価に関係するのではないか?」という不安をメンバーが抱えている状況では、本音はおろか挑戦して失敗する状況は避けたいはずです。
仕事の性質上、堅実遂行や慎重さが求められる場合もあると思いますが、チャレンジを推奨したいと思っている場合は、まずはメンバーの心を開くことは重要といえるでしょう。
2. 職場課題が早期に発見・解決される
本音を話してもらうことで、不満や問題が隠れたまま放置されるリスクが減ります。
たとえば「この業務は無駄じゃないですか?」「そのやり方だと現場は混乱します」などの声が早めに出ることで、無駄やトラブルを未然に防げます。
昨今はマネジャーのプレイング化が進んでいることもあり、マネジメント一人で業務のすべてを熟知して、適切に管理しきることは難しいでしょう。
そのため、メンバーの意見も取り入れて組織運営していくためには、気軽に本音でメンバーが課題意識を発する環境を整えることの重要性が増しているのです。
3. 社員の離職率が低下しやすい
「話しやすい」「聞いてくれる」「理解されている」と感じられると、職場への信頼感と愛着が高まり、人材流出が抑えられます。
特にZ世代以降では、共感・対話・透明性が重視される傾向があります。
「3年3割現象」に代表されるような若手社員の早期離職は、コミュニケーション不足やすれ違いに起因していることも多いはずです。
離職だけでなく、メンタルヘルスによる休職防止にも、本音コミュニケーションは効果があります。
愚痴ではなく「本音として整理された気持ち」を言えることで、ストレスの内在化を防ぐことができるからです。
上司が「大丈夫?」と気軽に声をかけられる職場の雰囲気が、早期のメンタルケアや支援につながるでしょう。
4. 意見交換が活性化しチームの信頼関係が深まる
本音でのコミュニケーションが進めば、表面的な「忖度会議」から脱し、率直な提案や現場の本音が出てくるようになります。
マネジメントにも「耳が痛い話」が届くようになり、組織長として建設的な判断ができるようになります。結果的に、組織の判断の精度が上がることにつながるのです。
本音を話す状態になるためには「信頼」が前提です。
「話す→受け入れられる→安心する→もっと話せる」という良い循環が生まれます。
上司との一対一のコミュニケーションだけでなく、組織的にこの風土が浸透することで、チーム内での協力・助け合い・相談のハードルが下がるでしょう。
本音を引き出すはずのサーベイが逆効果に!?
前章で紹介したような状況を作り出すためには、マネジメントの努力が重要なのは言わずもがなです。
一方で、上司に任せきりにするのではなく、人事としてサーベイをする企業も増えています。
定量的に社員のコンディションが確認できるだけでなく、上司が声をかけるきっかけとなったり、優先的にフォローするメンバーを決めたりすることに役立つからです。
ただし現状の「本音を言わない」状態を考慮すると、果たしてサーベイなら社員は本音で回答をするのでしょうか。
2022年のある調査によると、社員満足度調査などのサーベイで「本音以外を回答したことがある」と答えた人は全体の約77.6%にのぼります。
本音で回答しなかった理由として、「人に見られていそう」が45.9%、「面倒くさい」が37.3%と挙げられています。
参考:社内アンケートは本音で回答されず意味がない!?従業員の本音が出ない理由と対策を実施方法・質問別に解説【Colere】
本音が出ない理由としてはサーベイ実施そのものに対する抵抗感がまずは挙げられます。
| サーベイ実施そのものに関する課題 |
|
これらは人事として社員への理解促進のアナウンスや、結果や分析結果を開示することで対策できます。
一方で、サーベイの設計に対する不信感を上げる声も一定数ありました。
| サーベイ設計に関する課題 |
|
目的の設定とも連動してくるのですが、「何となく社員の意見を聞いてみよう」という曖昧な状態では、どうしても質問項目は幅広くなります。
結果的に、回答者の負荷が上がってしまいます。
同様に「離職意向が高い社員を見つけたい」などピンポイントな意図のみでのサーベイ設計も注意が必要です。
誘導的・意図的な質問ばかりになり、健全に働いている社員の不信を招くだけでなく、淡く離職を考えていた社員の意向を一気に顕在化させかねません。
AIなら自然に社員の「本音」を引き出すことができる
前章の最後に触れた「不自然なサーベイ設計では、本音を引き出せない」と述べました。
ただしサーベイ設計に長けている人事の方は、それほど多くないのではないでしょうか。
大半の企業でのサーベイ実施は半年や年に1回程度で、決して頻度が高い人事イベントではありません。
また、一度サーベイを作ると、結果の経年比較も考慮して、数年間同じ項目を使い続ける企業も多いようです。
つまり「どうやったら本音を引き出せる質問が作れるのか」という点で、不安がある人事の方も多いのではないでしょうか。
そんな場合は、最新の生成AIの技術をサーベイ設計に取り込むことがおすすめです。
従来型のサーベイでは、人事や経営が「この質問なら本音で回答してくれるだろう」など、ある意味仮説を決め打ちして、回答を収集していました。
しかし、社員のコンディションは一人ひとりで異なるため、全社員の本音を引き出せるような質問は、現実的ではないといえます。
むしろ、その仮説があてはまらない社員の場合「なんでこんなことを人事はヒアリングするのか?」と、モチベーションダウンになってしまいます。
一方、AIの技術を活用すれば、個別の職場や社員に最適化した質問が作成されます。
例えば、「こんにちは、〇〇さん。〇〇さんは入社8年目で今の部署に来て1年経ちましたね」など、社員個別の状況を踏まえた挨拶でアイスブレーキングをしてくれます。
さらに「今日の調子はどうですか?」と軽いファーストノックをしたうえで、その回答結果に応じて、その次にふさわしい質問を自動で作成します。
「自分のことを分かってくれている」という安心感から、社員も自然と本音での回答がしやすくなるのです。
さらに回答終了時に、AIが本人のインサイトをもとに、カウンセラーのように個別のアドバイスもしてくれます。
リアルの場で本音が言えずモヤモヤしていた社員の、心理的なフォロー効果が期待できます。
もちろん、社員コンディションは人事やマネジメントも把握できるので、回答後の個別フォローにもつなげられます。
AIを取り込めば、ルーチン化・形骸化したサーベイでは引き出しきれなかった、率直な社員の意見や状態の可視化が進められるでしょう。
| 生成AIによって社員の本音を可視化し、 風通しが良い職場に向けての第一歩を! |
|
・JOB Scopeは、エンゲージメントを可視化する『生成AIワークバリュー・スコア分析』をリリース
▶▶『生成AIワークバリュー・スコア分析』の詳細はこちらをご覧ください |
※当連載では、なぜ現代マーケットで生成AIによるエンゲージメント把握が有効なのかについて、今後もお伝えしていきます。
従来型の従業員エンゲージメント把握サーベイでは限界を感じている経営・人事部門の方は、ぜひ引き続き今後も記事をお読みください。
まとめ:サーベイとコミュニケーションを組み合わせるのがポイント
今回は職場における本音のコミュニケーションに注目し、解決策の一つとして生成AIを活用したサーベイを紹介しました。
ひとことで「本音」と言っても、国民性や性格特性も影響し、本音を離さない要因は人それぞれです。
さらには役割や業務特性が影響し、自分では「本音を話している‟つもり”」と勘違いしているケースもあるため、解決策はなかなか複雑です。
今回紹介したようなサーベイで仮に社員の本音が引き出せたとしても、その本音がネガティブなものであれば、最終的には人によるフォローが必要となります。
仮に本人もサーベイ回答によって自分のネガティブな本音を知ってしまった、実感してしまったようなケースでは、放置しておくとむしろ組織への悪影響が広がってしまうからです。
そのような場合は、本音を引き出すことがゴールではなく、ネガティブを解消するスタート地点となります。
人事やマネジメントが、そのネガティブの要因を「どんな場面で感じたのか」や「どの程度解決が必要なのか」などのフォローをしないといけません。
サーベイは社員の本音を探るための「きっかけ」と位置づけ、より深いコミュニケーションをとるための武器として活用するようにしましょう。
※JOB Scopeは、デフィデ株式会社の登録商標です。
※生成AIワークバリュー・スコア分析は、デフィデ株式会社の登録商標です。
新しい働き方、DX環境下での人的資本経営を実現し、キャリアマネジメント、組織変革、企業強化から経営変革するグローバル標準人事クラウドサービス【JOB Scope】を運営しています。