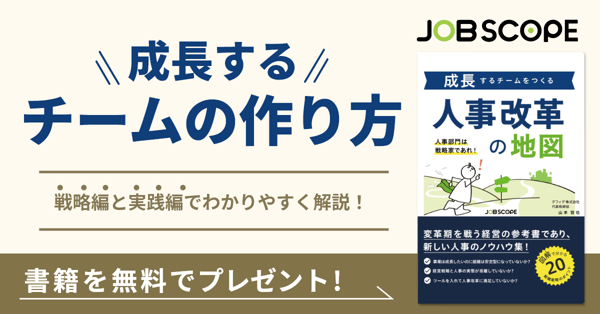バブル崩壊後の1990年代、「失われた10年」という言葉がもてはやされた。しかし、その後も日本経済は以前の成長を取り戻せていない。もはや、気づけば「失われた30年」と称されるほどだ。この間、経済のグローバル化はますます加速しており、日本企業の組織構造を大きく変えつつある。
そうした流れの中、日本企業の良さであった共同体意識が希薄化しているだけでなく、人材を長期的に育成する力も削がれてきているのではないかと危惧しているのが、神戸大学の上林憲雄教授だ。経営学の視点から個人的幸福と社会的善の合一のあり方を追求する上林教授に、今日本企業の人事部が直面する課題を聞いた。前編では、人的資本経営やジョブ型雇用に対する見解を語っていただいた。

01短期思考に走りがちな
日本社会を危惧する
昨今の人事を取り巻くトレンドで何か気になる点がございますか。
最近の日本社会は、企業も含めて実務に携わる方々が段々と短期思考になっているイメージがあります。根気強く長期の視点で捉えるのではなく、何かすぐに解決策やソリューションを求めてしまう傾向が年々強くなってきている印象です。
その影響は1990年代、あるいは2000年代以降もずっと脈々と続いてきています。いわゆる、米国スタイルの市場主義ですよね。私はこれを「グローバル市場主義」と言っています。今のDXもそうですが、グローバリゼーションとマーケットオリエンテーションが混在化したような技術の革新があって、グローバル市場主義への傾倒が加速化しています。そういう視点だと、人事の担当者に限らず誰もが短期的なスパンで物事を決着しようとしがちになります。そうした視座、ものの見方が普通になってきてしまっています。
先ほど市場主義という言葉で申し上げましたが、もちろん市場主義自体は悪いことではありません。今では死語となりつつあったりしますが、かつては「日本的経営」という言葉が話題になっていた時代がありました。日本のいわば、共同システムとか、みんなで一緒に働く協働の良さですよね。いわゆる共同体、コミュニティのもとで一緒に皆で協力しながら仕事をしていく、そういう意識が急速に衰えていて、その狭間で皆が苦しんでいる、そんな状況ではないかと考えています。
それが、職場における世代間の断層やギャップに繋がっているのではないかという印象があります。
マーケットは需要と供給のバランスですぐ答えが出ます。だから、それですぐ決着をつけて、「これはこうだ」ということでどんどん進んでいってしまう。そこに納得できないと思うと置いてきぼりにされてしまうところがあります。これまでは、モノ・カネ・情報という資源が市場の原理で動いていました。しかし、もはや最後の砦であった「ヒト」のところもずいぶん変化を遂げてきている気がします。ジョブ型の人事も当然関係してきますよね。

02人的資本情報の開示は
日本企業にとって
追い風となる
戦略人事や人的資本経営がバズワード的に取り上げられています。どうご覧になられていますか。
実は、「人的資本」(ヒューマンキャピタル)という言葉自体は古くからありました。私からすると、ヒューマンキャピタルはもう一旦終わった話です。なのに、最近になって、特に「人材版伊藤レポート」以来ですが、バズワードと化しています。ただ、これは別に悪いことだとは思っていません。正直言うと、「今さらなぜ」というのはありますがね。
人材が大事だという考えは、日本企業ではもう昔から理解していました。その後、グローバリゼーションの影響で、海外からさまざまな人材が日本にやってきて働くようになりました。価値観も多種多様ですから、自分たちの会社や組織が一体どういう人たちから成り立っているのかをしっかりと外部に示す必要性や要請が、経営者の側から恐らく出てきたのだと思います。それがあって、私たちの会社ではこういう人員から構成されています、バックランドはこうです、ダイバーシティも確保しています、といった中味を開示しなさいということになったわけです。なので、日本企業にとってはむしろ追い風だと思います。日本には、そもそも人を大切にしてきた土壌があるわけですから。
だから、別に恐れる必要はないんです。堂々と開示をすればいいわけです。なのに、どの会社も様子見といいますが、どこかしら二の足を踏んでいるところがあります。私のところにも、開示に自信がない会社から「どうしたら良いか」という相談が結構来ています。自ら人的資本経営を実践しているところを正直に示せば良いだけなのです。
これも、要は自信のなさの現れです。「人事は流行に従う」ところがあります。周りがやっているから、自分たちもその流行に合わせよう、そのチャンスを逃してはいけないといったスタンスです。皆と一緒にいれば安心する、まるで護送船団方式みたいなところがあって、そこに明確な戦略はないわけです。
米国の経営史学者であるアルフレッド・チャンドラーが、「組織は戦略に従う」と言いました。それをもじり、人事面ではそうではないよという意味で「人事は流行に従う」という言い方が使われることがあります。本来、組織は戦略に従うべきなのに、組織の中で人事に関することは、とりわけ戦略に従うことがありません。流行に従ってしまっている。そのことを示したがこの言い回しなのです。
「戦略人事」はそこを変えていこうという表現です。なので、私はこれをポジティブに捉えて良いと思っています。まさに人の配置や育成ですよね。人をいかに育成するかということが非常に重要な課題だと捉えています。それがまさに経営のあり方であったり、戦略の立案にも関わってきたりするはずなので、大事にしないといけません。
「戦略人事」も「人的資本経営」もバズワードとなり、今その重要性が一般にも知られるようになって来ていると私は理解します。かつて「人的資源管理」の前は、人事管理であるとか、労務管理という言葉で呼ばれていました。しかし、そういう時代はむしろ戦略だとか、あるいは組織全体のパフォーマンスにとって、ヒトはマイナスのブレーキをかけてしまうという認識が一般的でした。経営側からしても、労働者には当然賃金を支払わないといけませんしね。
ただ、人事労務管理という用語が人的資源管理という用語に置き換わっていくことで、ヒトはみんな一緒じゃなくて、一人ひとり個性や能力が違い、場合によってはヒトに投資することで、莫大な富を企業は得ることができるかもしれない、という発想になってきたわけです。まさにヒトは企業にとって役に立つ存在なんだという認識が高まってきた。ヒトはコストではなくむしろ資本として見てお金をしっかりと払う。そして育成していく視点が重要だということが、最近になってよく言われるようになってきたわけです。遅ればせながら、そのこと自体は非常に良いことだと私は捉えています。

03日本企業が
ジョブ型雇用を
進める上での課題とは
ジョブ型雇用に関してはどのような見解をお持ちですか。
ジョブ型雇用も言葉が先行していると思います。ジョブとは職務と訳されます。これまで日本企業では職務給を導入しようとしてきたものの、結構失敗をしています。遡ると、1950年代や60年代ぐらいに、一度やろうとして失敗しました。それから、成果主義の議論の中でも、成果をしっかりと測定するためにはジョブという基本単位があった方が良いという議論もありました。しかし、そこでも結局うまくいかず、成果主義を少しアレンジして日本のコンテキストに合った人材育成型成果主義がいいんだ、ということになりました。それ以降は良くなっている感があります。
だから、ジョブという概念は日本にこれまであまりなかったと言えます。実際、私は授業で学生に対してこう説明しています。「英米圏であれば『What’s your job?』と尋ねたら、職務内容を答えてくれます。だけど、君たちのお父さんお母さんに、『仕事は何ですか』と聞いても明確には答えてもらえないと思います。色々な業務に就いていて、これが私のジョブ、というものがないからなのです」と。それは裏返して言うと、さまざまな仕事を広く浅くやっている、ジェネラリストということです。
これは非常にネガティブな言い方をすると、専門がないということです。なので、ジョブ型雇用を導入することで専門性をきっちり身に付ける、あるいは自分の専門はこれだと決めて、そのスキルを深めていく――このこと自体はすごくポジティブに捉えて良いと思います。
他方で、ジョブ型雇用の採用にあたって注意しないといけない点もあります。それは何かと言えば、一つは担当業務をとても限定的に狭く捉えてしまい、それ以外のことは一切やらないという意識になってしまいがちなことです。専門性を持って入社してくるので、会社との契約も当然ながら、そのジョブが中心になります。専門に特化するあまり、少しでも専門でないことをやらないといけない局面になると、「それは私の仕事ではありません」という対応になってしまうことがある、というのです。「特に若い人に多い」と複数の会社の方からお聞きします。「契約上そうなっていますよね」と言われると確かにそうなのですが、これは今までの日本企業の仕事の進め方とはかなり異なってしまっています。
話は逸れますが、タレントのタモリさんの名言の中にこういう一節があります。「やる気のあるものは去れ」。彼曰く、「やる気のある人はそれしかやろうとしない。他の作業だとか、あるいは将来的には自分の成長の糧に繋がるようなことも一切断ってしまう。だから、やる気のある人は来なくていい」ということです。非常に逆説的な表現ですが、ジョブ型雇用で注意すべき点は、イメージ的にはそれとよく似ています。そういう側面があることを忘れてもなりません。
もう一つの注意点は、将来管理職に昇格した際のマネジメントスキルの不足です。特に若いときは専門性に特化して良いのですが、いずれ管理職になったときに全社的にどういう問題が起きているかは把握しておく必要があります。そのためには専門外のことにも幅広く関心を持つ姿勢が必要です。ジョブ型雇用で採用されると、そのことを認識しないまま、管理職になっている人が多いので、自分の経験したジョブ以外のことは理解できず、コミュニケーション自体がうまくいきません。結果的にそこに非常にコストが掛かってしまう、そういう問題点があります。だから、専門性を高めるのは良いことではあるものの、同時に非専門のことについてもある程度は学ぼうという意識がないと、会社という組織の中では難しいと思います。ですから、専門性だけでなく、それほど深くなくても良いので非専門のところも広く知っておこうとする努力は必要になってきます。この二つの点がジョブ型雇用をこれから進めていくにあたっての課題だと思います。
「蛸壺に入るな」ということですね。
「針の穴から天覗く」という言い回しがありますね。そういうふうになってもらいたいのです。つまり、専門性を深めれば深めるほど、蛸壺に収まるのではなく、その一つの点を深めることで、逆にその深さから非常に幅広くさまざまなことが見えてくるのです。ジョブ型雇用でもそういうことを目指していかないといけません。最近良くいわれるT型人材の育成の議論とも関係しますね。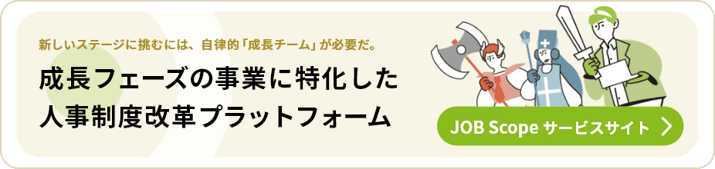

04個と組織のバランスが求められている
不透明さがますます増す時代において、人事マネジメントを行う上での人事やマネージャーの役割がどう変わりつつあるとお考えですか。
社員の自律性や主体性を引き出すような人事制度ももう長年ずっと考えられて来ています。成功しているとは言えないのですが、そういう自律を喚起する仕組みは考えられています。ただ今の若い社員さんたちに、そのことが本当に伝わっているかどうかは微妙なところがあります。下手をすると組織全体のことを考えずに、自分勝手にわがままな行動を取ってしまうようです。若い人は自分勝手な行動をとり勝ちだ、といった悩みの声を、特に中小企業の経営者の方々からよく伺います。
だから、そういう主体性や自律性を引き出す仕組みと同時に一見矛盾するような組織としての団結力、協調性を引き出せるような、そういう両面をバランス良く考えることが日本の企業社会には必要だと言えます。
欧米では、個人主義というのは、決して個人のわがままを通すことではありません。むしろ、周囲や全体のことがわかっていて、しかも、「これは人の迷惑になるからやってはいけないことだ」と理解した上での個人主義なのです。一方、日本は今まで文化的にそういう土壌があまりありませんでしたから、個という単位の理解が社会全体でまだまだ浸透していないと思っています。特に若い人には体感として理解ができていない気がします。
だから、主体性や積極性を引き出すような仕組みと同時に、組織全体が一丸となって協力しあうという、一見矛盾するかのようにも見える双方のバランスを取るような役割を、人事やマネージャーに担っていただきたいと思います。
欧米と日本における個人主義に対する認識の違いは、何に起因しているのですか。
非常に本質的なご質問だと思います。やはり、文化的なところが非常に大きかったと思います。やはり、歴史的に見てムラ社会にどっぷりつかって生活してきた日本人には「個」の概念が難しいんですよ。欧米人にとって、個人を大切にすることは他の人も大切にすることです。だから、自分がされて嫌なことは、他人も当然されたら嫌であると考えます。だから、他人を尊重する。他人を大切にすることと自己主張をすることが同一平面上に両立している。そこがもうベースとしてきっちりあるからこそ、個人主義の社会なのです。単なるわがままや自分勝手とは全然違うわけです。
我々の年輩世代も「そうだ」と思うものの、理解しきれていない人もいます。今の若い人たちも、親世代の背中を見て育つせいか、なかなか理解できていません。もう少し時間が経つと変わってくるのかもしれませんが、今のところの日本は、残念ながらまだそういう感じですよね。

上林 憲雄氏
神戸大学大学院経営学研究科/経営学部 教授
1989年神戸大学経営学部卒業。1991年同大学院経営学研究科博士前期課程修了。1992年神戸大学経営学部の助手に就任。1999年英国ウォーリック大学経営大学院よりPh.D.を取得。2005年神戸大学大学院経営学研究科教授、現在に至る。この間、神戸大学大学院経営学研究科長・経営学部長、日本労務学会会長、日本経営学会理事長、日本学術会議会員等を歴任。2021年より経営関連学会協議会理事長、2023年より神戸大学大学院経営学研究科人的資本経営(HCM)研究教育センター長を務める。著書に『SDGsの経営学』(千倉書房、共編著)、『経験から学ぶ人的資源管理』(有斐閣、共著)、Japanese Management in Change (Springer、編著)などがある。