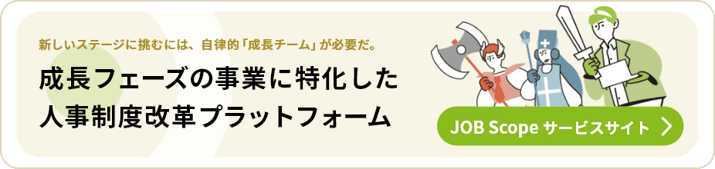バブル崩壊後の1990年代、「失われた10年」という言葉がもてはやされた。しかし、その後も日本経済は以前の成長を取り戻せていない。もはや、気づけば「失われた30年」と称されるほどだ。この間、経済のグローバル化はますます加速しており、日本企業の組織構造を大きく変えつつある。
そうした流れの中、日本企業の良さであった共同体意識が希薄化しているだけでなく、人材を長期的に育成する力も削がれてきているのではないかと危惧しているのが、神戸大学の上林憲雄教授だ。経営学の視点から個人的幸福と社会的善の合一のあり方を追求する上林教授に、今日本企業の人事部が直面する課題を聞いた。後編では、働きがい・モチベーションに対する取り組みの重要性や今後人事が果たしていくべき役割を語っていただいた。(前編はこちら )

01人々の幸せを追求する
経営学を極める
上林先生は、多種多様なテーマを研究されています。それらに共通する軸は、「働く人たちが組織の中でハッピーに過ごせる」ようになることとお聞きしています。その意味あいを教えていただけますか。
私は神戸大学経営学部に入ってそのまま大学院に進み、そこで研究者としてやってきました。なので、ずっと経営学畑です。経営学というのは、割と誤解されやすくて、一般の人々は会社が儲かるための仕組みを考える学問だと理解しています。そう言われるたびに、私はがっかりしてしまいます。もちろん、儲けるために努力するのも重要なのですが、それだけではないというのが根本にあります。もう一つ、実は学術的な言葉で言うと経済性や利益に対して社会性という視点があります。社会の中で組織や人に軸足を置いて、人々の幸せを追求したいというのが、私自身の根幹なのです。
残念ながら経営学の道に進んだ頃は、そうした方向性は王道ではありませんでした。しかし、最近は幸いなことにSDGsやサステナブルという言葉がクローズアップされ始めていて、割と社会や組織、人間などに注目が集まりつつある時代になってきています。だから、私のテーマにも追い風が吹いている感じです。昔から経営学一筋ではあるものの、学術的な言葉で言うと私が研究しているのは、社会科学としての経営学ということです。
その一番の根本は、どういう人間、あるいは社会になると良いのかという点です。そこが根底にあるわけで、会社の利益を皆で配分して終わりというのとは一線を画していると思っています。
儲けるための経営学は一面に過ぎないということですね。
そうなんです。もちろん、株式会社にとって儲けることはすごく重要です。ですが、それだけだったら学問ではなくなります。世の中、お金だけではハッピーになりませんからね。だから、お金以外のところも含めて、「これは良い人生を送れたな」というふうに、社会で生活している皆が最後に思えるような、そういう社会にしたいというという想いを持っています。

02「ワーク・ライフ
・バランス」はまだ道半ば
上林先生は、近年経営学の視点から「ワーク・ライフ・バランス」に関して講義や執筆を積極的にされています。その意図をお聞かせいただけますか。
「ワーク・ライフ・バランス」が、特に言われ始めた当初の頃は誤解が多かったです。「ワーク・ライフ・バランス」はワークとライフのまさに「バランス」を意味する言葉です。これを振り子や天秤で示されるような二律背反、トレードオフ思考で捉えてしまうと、ライフつまり私生活を充実させるためには、仕事を少し緩めないといけないという発想になります。果たして、論理的に本当にそんな発想で良いのですかというのが、経営学者である私の問いかけです。
初めから仕事は辛いものだからと捉え、それを少し緩めてライフの比重を上げるというのは間違っていると思っています。目指すべきは、ワークとライフの間の好循環です。ワークとライフを完全に分けてしまうのではなく、ワークがライフに好影響を及ぼし、ライフがワークにも影響を及ぼしていく、これを私は「ワーク・ライフ・ハーモニー」、あるいは「ワーク・ライフ・インテグレーション」と呼んでいます。インテグレーションというのは統合、合体という意味です。
単純に仕事時間を減らす、長時間労働を減らすであるとか、それは第一歩としては必要なのかもしれませんが、そればかりに集中していると良い結果は出て来ません。しかも、経営者にとっては「ワーク・ライフ・バランス」が割と受け入れにくい概念のようです。政府も産業界からの反発があったためか、ある時から「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を使わなくなり、働き方改革という言葉に置き換えられています。改革するのは良いことだと思うものの、やはりその中身が問題なのです。
今は労働時間や休暇日数など、数値で測れる側面の改革ばかりです。それで、平均労働時間が減ったから、あるいは休暇日数が増えたから「ワーク・ライフ・バランス」を達成しましたといった話になっているわけです。これではおかしいのです。人々がいかに働いて楽しい、幸せだと感じるかが一番重要なのに、そこまで議論が全然いっていません。数字として目に見える側面、測定可能な部分だけがことさら強調される嫌いがあります。
だから、私はこれでは本来の「ワーク・ライフ・バランス」ではなく、まだまだ道半ばだと思っています。そういう誤解を解くというと、偉そうな言い方になってしまい恐縮ですが、それもあって私は「ワーク・ライフ・バランス」に関しては結構いろいろな媒体を通じて発信してきているつもりです。
上林先生が所長を務めておられる、神戸大学人的資本経営研究教育センターとはどのような研究機関なのですか。
神戸大学大学院経営学研究科には、3つの研究センターがあります。その一つが、人的資本経営の研究教育拠点として開設された「人的資本経営研究教育センター」です。実は産業界から「人的資本に関する研究をしてください」と結構な額のご寄附を大学を通じて頂くことになり、私一人で使うよりも、関連する先生方も一緒に使える方が良いということで、このセンターを2023年4月に立ち上げました。
目下、センターでは三つの大きなプロジェクトに重点的に取り組んでいます。第一に、見える化促進プロジェクト。これはそれぞれの企業で働く人々の実態を科学的に測定・開示するプロジェクトです。第二は働きがい向上プロジェクト。先ほど申し上げた通り、見える化や指標策定だけでは人々のハピネスは追求できませんから、その背後に隠れている、働く人々の個人的悩みや課題を解決し、働きがいを向上させるプロジェクトです。これは、最近の言葉でいうとワークエンゲージメントやウェルビーイングの追求プロジェクトと言い換えてもいいです。そして、第三にその2つを長期的にドッキングして真の人的資本経営を追求するプロジェクトです。これらを通じて、働く人たちが生き生きとハッピーな人生を送れるよう支援しています。第一と第二は相互に両立しにくい側面もありますから、それを時間をかけてドッキングし、本当の意味での人的資本経営、働く人々にも経営サイドにもハッピーな経営を実現していきたい、――こうした私自身の理想が、これらのプロジェクトに体現されているのです。

03長期視点で
人材を育成する必要がある
ここからは、日本企業の課題についてもう少しお聞きしたいと思います。まずは、前篇で「近年日本企業が短期思考になってきている」と指摘されていました。その理由や打開策をお聞かせいただけますか。
日本企業では長らく、社員同士が相互に信頼して尊敬し合いながら、一緒に仕事をする仕組みを維持して来ました。そこに、米国式の市場ベースの仕組みがどんどん入ってきて、共同体ではなく個人間の競争になってしまいました。競争すること自体は、それほど悪いことではありません。だけど、あまりに競争ばかりしているとお互いに疑心暗鬼になりますし、日本企業がこれまで大事にしてきた共同力の基盤であったチームワークも確実に乱れると思っています。競争が行き過ぎてしまうのは日本にはむしろ合わないと捉えており、組織として協調しながら皆で一緒に一丸となって頑張るという仕組みが構築できるよう、バランスを取ることが重要だと考えています。
やはり、長期視点で人を本当に育てるんだという気構えを持つべきです。人の育成は短期でできるものではありません。1年、2年研修を行ったからそれでOKとはいかないのです。5年ぐらいで少しずつ変化の兆しが見出せるようになり、ようやく行動が変わってきます。1人の人間を変えようとすれば、やはり10年くらいは先を見据えないとだめですね。ドンと構えて覚悟を決めて取り組まないと成長過程を見届けることもできないのではと思います。
今、若い社員が3年以内に退職してしまうという話が良く聞かれます。もう少しで成長できるのに、そこまでもたないんですよね。もうどこの会社の人も「若い人が定着しない」とものすごく悩んでおられます。本当に、リテンションには苦労されています。まずいちばん重要なところは、自分の会社を好きになってもらうこと。お金をもらえるから仕事をすると考えるのではなく、この会社に入って本当に良かったと思ってもらえるようにすることです。顧客だけではなく、従業員にも会社のファンになってもらう。単純なことですが、意外と今その視点が欠けている気がします。
古い言い方で言うと、「社員は家族」です。そういうことを言うのは今やイマドキではではないという雰囲気になりつつありますが、これから会社に入ってくる人に、「この会社に入ってよかった」と思ってもらえるような仕組みを考えるのがリテンション施策のいちばんのベースとして必要だと思っています。
日本企業において人的資本経営に向けた取り組みを推進するためには、何が重要であるとお考えですか。
いちばん重要なのは、人的資本経営というコンセプトの正確な理解でしょうね。それが何故必要になって来ているのか、どうしてわざわざ人的資本の中身を開示しないといけないのか、開示した上でどうするのかを、人事担当者自らが経営者と一緒に考えていくことが大切になってきます。

04人事部こそ
長期戦略の礎と認識すべき
その推進を担う人事部門に何を期待されますか。
人事部は社員に給料を支給したり、福利厚生といったルーチン業務も担ったりしますが、それに加えて人材を育成する、ひいては戦略の立案・策定の基礎になることを実際手掛けています。人事部こそ長期戦略の礎となるんだという認識を持って、自分たちが会社の長期プランを考えるポジションだと理解すると、それだけで随分と変わってくると思います。
人事担当の人は人柄も良い人が多いです。謙虚で控え目な方たちです。だからこそ、自分たちこそが会社の長期プランを作っているんだと積極的に再認識していただくことが重要になってくるのではないでしょうか。
短期視点になりがちな経営者に、意見を言える人事であるべきだということですね。
そうです。人事担当役員が役員会で発言しやすい環境にある会社は、結構そういうことができていると思います。人事職能が混然一体となっていて分離していない中小企業の方々はもとより、人事に携わっている人たちが、会社のトップと頻繁にコミュニケーションを取り合うことは非常に重要になってきます。経営者も営業成績は気にするものの、社風や制度、仕組みなどなかなか変えにくいものは等閑視されがちです。経営者はそこにも気を配り、目配りしなければいけないし、そのように促していくのも人事の役割になってきます。
本コンテンツのメイン読者である中小、中堅企業の経営者や人事責任者へのメッセージをお願いいたします。
端的に言えば、日本企業、特に人事はもっと自信を持てと言いたいですね。日本企業は自信を喪失してしまっているようなところがあります。だから、周りばかりを見てしまい、人事は流行に従ってしまうのです。
それから、日本という国自体の問題かもしれませんが、「外国は正しい」と思い込んでいます。そんなことはありません。今のコーポレートガバナンスの仕組みもそうです。何ら中身を議論することもなく、米国ではこうなっているから、我が国でもこうすべきだ、という論調があまりにも多いですよね。「米国や英国がこうしているから、日本も遅れずに取り組むべきである」といった意見は、正しい場合もありますが、日本という国のコンテキストをもっと考え、日本社会にマッチした制度や仕組みを考えていかないといけないと思っています。
国レベルだけでなく、それと同じようなことが会社レベルでも言えます。他の会社でうまくやっているからといっても、自社でそれが成功する保証はありません。その前に、自社の内部環境や外部環境を分析することが非常に重要となります。私も神戸大学でのMBAで、自社の置かれた状況を冷静に分析することが重要だと、学生さんたちには教育するようにしています。自社から少し離れた目線で客観的に分析するべきだと。今までの我が社の強みを全否定してしまうのではなく、良かったところも踏まえながら、もちろん修正すべき部分はきっちり変えて、新しい改革を進めていくべきなのです。割と日本人は何でもかんでも全否定しがちですよね。基本的に謙虚なのでしょう。
あまりにも忙しくて、自社でやってきたことを振り返る機会すらないのかもしれませんが、経営層、特に人事や組織に携わる人たちは、これまで歩んできた道を見返し、分析して、これから進むべき方向を真摯に考え、皆で議論するという時間を設けないといけないと思います。

上林 憲雄氏
神戸大学大学院経営学研究科/経営学部 教授
1989年神戸大学経営学部卒業。1991年同大学院経営学研究科博士前期課程修了。1992年神戸大学経営学部の助手に就任。1999年英国ウォーリック大学経営大学院よりPh.D.を取得。2005年神戸大学大学院経営学研究科教授、現在に至る。この間、神戸大学大学院経営学研究科長・経営学部長、日本労務学会会長、日本経営学会理事長、日本学術会議会員等を歴任。2021年より経営関連学会協議会理事長、2023年より神戸大学大学院経営学研究科人的資本経営(HCM)研究教育センター長を務める。著書に『SDGsの経営学』(千倉書房、共編著)、『経験から学ぶ人的資源管理』(有斐閣、共著)、Japanese Management in Change (Springer、編著)などがある。