近年は、人的資本経営の重要性が叫ばれている。加えて、人的資本の情報開示要求も高まっており、多くの企業は右往左往している。
こうした中、人的資本経営の本質を見極めず、ただ形だけを追い求める経営や人事の在り方に疑問を呈するのが明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科の野田 稔教授だ。「人的資本経営のその先を見据えていく必要がある」と熱く語る。前編では、開示ありきの流れへの見解や野田教授が提唱する「Convivial Company」の概念、カイシャ・トランスフォーメーションへの取り組みなどを伺った。
目次

01人的資本経営を流行り物
として捉えるのは間違い、
原理原則が重要
人的資本経営や人的資本の情報開示への流れが加速しています。
現状をどうご覧になられていますか。
我々人事の専門家からすると、人的資本経営は戦略的人事管理(Strategic Human Resource Management:SHRM)ということで、もう昔から考えてきましたし、ずっと主張していた概念です。今喧伝されてるのは、その開示というところです。
これは、まさしく統合報告書の流れの中で言われてきたことです。ただ、世の中の潮流として今は開示に目が向いてしまっていて、2023年3月期決算から義務付けされようとしています。本当に大騒ぎと言っても良いのではと思うような状態です。
しかし、本当に原理原則を考えるとそれはおかしな話です。開示というのは、あくまでも結果の話です。結果を見せるということです。本質的には、自分たちが戦略の実行に向けて人事管理(Human Resource Management:HRM)なり、組織管理 (Organization Management) をどれだけ正しくしているか、ここがまずあって初めて始まります。その結果を統合報告書の中で開示しましょうという順番にならないといけないのです。
ところが、そうならずに今どうなっているかというと、「とにかく女性管理職比率を出そう」「女性管理職の比率が低いから女性を無理やり管理職にしましょう」とか、「女性役員が全然足りないから、取りあえず社外取締役に女性を入れましょう」とか…そういう開示項目がまずありきの議論になってしまっています。
確かに、開示ありきの印象が強いです。
「なぜ女性管理職比率を開示することが、自社の戦略実行にとって意味があるのか」。この質問に答えられる経営者はほとんどいないのではないでしょうか。
一歩進んで女性管理職比率の増加はダイバーシティ&インクルージョン(D&I)が目的である、と答えられるまでには至るものの、「そもそもD&I推進の目的は何なんだ」と尋ねるともうお手上げです。ダイバーシティ&インクルージョンを進める一番重要な意味について、テキサス・インスツルメンツの社長が「イノベーション能力を高めることだ」と昔言っていました。まさに、それが究極の目的なのです。実際には、その前にリスクマネジメントがあったり、マイノリティの人たちを押し殺さないようにしようという順番があります。
この一連の流れをしっかりと捉えた上で、そもそもの基本戦略をよりイノベーティブになることと置き、その実現の一助としてD&Iを推進する。「さらにその第一歩としてジェンダーに目を向けました。だから、女性管理職比率を高めようとしていますし、社外取締役への女性の起用を推奨しています。この推進により我が社における視点の拡大が一層進み、イノベーションの確率が高まります。併わせて、副次的効果としてさまざまな視点から自社の状況を観察することにより、リスクマネジメントにも繋がります」という説明ができて、初めて指標に意味が出てくるわけです。
多くの会社では、そういったストーリーを全部取り払って、「取りあえず社外取締役に女性を入れましょう」になってしまっています。
戦略的とはとても言えませんね。
だから、戦略的人事を真剣にやりましょうと言いたいんです。もちろん、そのためには原点として、自分の会社のパーパス(存在意義)は何か、それを一体どんなドメイン(領域)で実現しようとしているのか、競合を見ると今どのようなストラテジーが必要で、それを実現するためにはこういうHRM組織が必要になるというロジックが立たないといけません。
ちなみに、いつも私が学生にこの戦略的人事の話をする時に、「必ず考えなければいけない」と言っているのが、役割行動(期待されている役割に相応しい行動)という媒介変数(パラメータ)です。
全ての戦略実現は行動から起きます。社員の行動に注目しなくてはいけません。その役割行動を引っ張り出すための道具として制度が複数あり、それが全部バンドル(束ねる)されて強いメッセージを社員に与えるのです。
実は、これは昔からある話です。何か流行り物のように人的資本経営を捉えるのは全く間違いです。原理原則をしっかりとやってくださいと言いたいです。

02会社への隷属状態から
解放されなければいけない
野田先生ご自身は「Convivial Company」を提唱されています。どのような経緯で、この概念に注目されたのですか。
私はライフシフトジャパンという会社と一緒に、人生100年時代にどう生きるかという、ライフシフターの研究と育成にずっと取り組んでいます。ライフシフターとは、キャリア自立している上に、自分におけるウェルビーイングが良くわかっていて、それに向けて自立的に動いている人を言います。
その活動をしている中で、ある時にどうも会社員はライフシフターになっていないと気がつきました。そうはいっても、会社の中でキャリア自立しながら自らの幸せをしっかりと追求している、そんな人が多い会社は本当にないのだろうかと、今から4、5年ぐらい前に探し始めたんです。
結論から言うと、ありました。有名なところでは、中小企業向けにグループウェアを提供しているサイボウズ。同社は100人100通りの人事制度を謳っています。他にも、軽井沢にあるビール製造メーカー・ヤッホーブルーイングなど、極めて社員セントリック(社員主体)の経営をしている会社が結構見つかりました。
そうした会社にインタビューをして、働きぶりや生産性などを見たり、イノベーションの輩出率を調べたりすると皆さん物凄く優良でした。
一見すると人に甘い会社に見えてしまうものの、甘いのではなく、実は本質を捉まえているんだなと理解しました。そこから、打ち出したのが「KX」なる概念です。「KX」は、カイシャ・トランスフォーメーションを指します。
会社ではなく、カイシャなんですね。
敢えて我々は、昭和の会社をカタカナで書いています。要するに制度が古くさくて、人間を道具扱いしている会社です。そういう古臭い昭和のカイシャをトランスフォームして、新しい会社に生まれ変わらせましょうという「KX運動」を3年前ぐらいから始めました。
この活動を仲間と共に進めるうちに、カイシャというものが極めて呪縛的存在だと気がついたんです。人の能力がもっとあるのに、逆に会社が人の能力の発揮を限定してしまっている。この隷属状態から解放することが、KX運動の本質です。
言い換えれば、人が人らしく、全社員の全能力を発揮することが重要ではないかと言うこと。研究を進める中で、昔読んだイヴァン・イリイチの本を思い出しました。
どんな方なのですか。
イヴァン・イリイチは、「産業は人間を無能化している」と言った思想家・文明批評家です。我々は自分が便利になり、かつ快適に過ごすために色々な産業やテクノロジーを作って来ました。ところが、1回作り上げると産業も社会も技術も人を隷属させる傾向があります。そして、隷属した挙句の果てに、人はそれがないと生きていけないというように無能力化されてしまうと主張しています。
私はイリイチを読み返した時に、一番人を隷属させているのは会社ではないかと思ったんです。
会社は1人ではできないことを皆で集まって成し遂げようとして作ったものです。なのに、今はその会社が独り歩きし、やれルールだ、制度だ、これがうちの決まりだ、価値観だなどと、人が生き生き働いていけない状態にしてしまっています。これは、会社本来の在り方ではありません。本来の意味の「Convivial」 な状態に戻さなければいけないと考え、「Convivial Company」という言葉を使い始めました。

03社員を主語とする「Convivial Company」を目指そう
「Convivial Company」とは、どのような概念なのでしょうか。
「Convivial」という単語には、ほとんどの方が馴染みがないと思います。英語の辞書を引くと、「パーティなどが愉快で楽しい」という意味が出てきます。元々は、ラテン語に由来しており、conは「共に」、vivialは「生きる」を指します。要は、live togetherなんです。なので、社会学では「自立共生」と訳されています。
ですから、「Convivial Company」とはまさに自立共生型の会社を目指そうということです。社員と会社とがもっと自由度を高める、そんな関係性を作り上げてはどうか。何なら、共有すべきものはパーパスぐらい。後は、相互作用の中で皆にとって一番効率が良いところを、それぞれが主体となって作れば良いのです。
良く考えてみると、これはティール組織(社員それぞれが意思決定し、目的を実現していける組織)そのものです。だから、ティール組織とか、その一つの具現形であるホラクシー組織(全社員が意思決定権を持つフラットな組織)は、実は「Convivial」な状態であると認識できます。
簡単に言うと、「Convivial Company」とは会社を主語にする経営から脱却し、社員を主語にする経営をすることです。全社員が全能力を発揮するように、制度が充実している。さらに言うと、社員はその中で極めて高いレベルで自由と自己責任を享受している会社だということです。
社員を主語とする経営をしていく会社だということですね。
ただし、これは言うは容易く行うは難しで、そう簡単には実現できません。経営陣にとってみると、かなり大きなパラダイムチェンジが必要になってくるからです。
我々がコアメンバーと称している有名企業のHRエキスパートと呼ばれる方々と2年近くに渡り議論を重ね、これが社員セントリックの構造ではないかという、5つのコンセプトと25のゴールをまとめました。

04社員セントリックの
構造を5つのコンセプトに集約
具体的にはどのようなコンセプトなのでしょうか。
一つ目が、「想いドリブン」です。誰か偉い人が作ったパーパスの押し付けではなくて、一人ひとりが想いを結集させた形で作り上げているといった話です。
二つ目が、「つながりリデザイン」。会社とのつながりがかなり違っていて、会社の一員という包摂関係ではなくて、必要だから繋がっている。そういう緩やかな、かつ主体性のあるつながりになっているということです。
三つ目が、「旅の仲間バラエティ」。色々な人がいるということです。本当にダイバーシティが進んでいます。しかも、一人ひとりが会社に対してハブアンドスポーク(中心に拠点を設ける仕組み)型につながっているのではなくて、人と人とが全部つながっている状態になっています。それぞれに対して非常に主体的に関わりあっているのも特長です。
四つ目が、「わがままセントリック」です。これは、セルフィッシュ(利己的)という意味ではなくて、我がまま(自分らしく)だということ。皆が自分の想いを口にしてお互いにそれを応援しあっている状態を意味します。
それによって、非常に自己効力感が高くなり、会社全体として変化を恐れなくなるというのが、五つ目の「変態インフィニティ」です。コアメンバーの一人であるカゴメCHOの有沢正人さんは、主権在民という言葉を使っています。
この5つのコンセプトで表現できることがわかり、実際にこれを指標化しました。その結果を「KX Score」(各指標の到達度=会社の未来度)とし、今の日本の会社がどの程度社員主語になっているのか、社員主語の職場で働く人たちの意識は一体どのようなものかを明らかにすべく、「カイシャの未来度実態調査」を昨年夏に実施しました。対象者は、一般の会社員1500名余です。この調査の結果は大変興味深いものでしたが、その結果についてはまたいずれ詳しくお話ししましょう。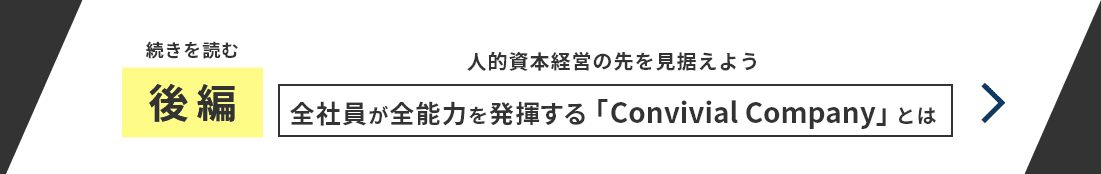

野田 稔氏
明治大学大学院
グローバル・ビジネス研究科 教授
リクルートワークス研究所 特別研究顧問
1981年一橋大学商学部卒業 株式会社野村総合研究所入社。1987年一橋大学大学院修士課程修了。野村総合研究所復帰後、経営戦略コンサルティング室長、経営コンサルティング一部部長を経て2001年3月退社。多摩大学経営情報学部教授、株式会社リクルート 新規事業担当フェローを経て、2008年4月より現職。リクルートワークス研究所 特任研究顧問を兼任。著書:『組織論再入門』(ダイヤモンド社)、『中堅崩壊』(ダイヤモンド社)、『二流を超一流に変える「心」の燃やし方』(フォレスト出版)、『野田稔のリーダーになるための教科書』(宝島社)、『あたたかい組織感情』(ソフトバンククリエイティブ)など多数。

