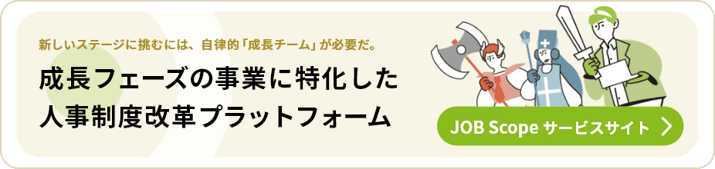世の中には、流行廃りがある。ましてや、スピード感が加速する現代では、そのサイクルが劇的に短くなってきている。それは、経営や人事の領域でも同様だ。「人的資本経営」や「ジョブ型雇用」などの言葉がもてはやされ、その本質や何故今重要なのかを理解せず、盲目的に追随していないだろうか。こうした中、「トレンドとして定着しつつある段階こそ、深い洞察が必要だ」と指摘するのが、早稲田大学 大学院経営管理研究科の竹内 規彦教授だ。組織行動論の第一人者として国内外で広く知られている同氏に、企業経営者や人事責任者が今留意すべきポイントを聞いた。前編では、人的資本経営が重要な背景やジョブ型への見解などを語ってもらった。

01今、「人的資本経営」が求められる背景とは
「人的資本」に基づく経営が、世界のトレンドとなっています。その背景をお聞かせいただけますか。
大きくは、二点あると思います。一つは、企業の株主価値を最大化することを目的とする人材マネジメントのあり方を疑問視する声が高まってきた点です。経営者からすれば、いかに会社の業績を上げて利益を出すかは重要なことですが、それだけを目的とする人材マネジメントのあり方に限界を感じている研究者や実務家が増えてきたことが背景としてあると思います。平たく言いますと、業績至上主義で人事施策を展開して行くと、短期的には財務的な数値指標は改善するものの、長期的には組織の内外に弊害が出てしまうことに徐々に気づき始めてきたのです。そのことを表現するのに、「人材」という言葉をこれまでのヒューマンリソース(人的資源)ではなくて、これからはヒューマンキャピタル、言い換えれば、より個々の価値を扱う「人的資本」として捉え直していこうというムーブメントが高まったことが、背景の一つだと思います。
もう一つは、人の働き方において何が最適解なのかがわかりにくい時代になって来たということが背景にあるでしょう。つまり、何か新しい、そして効果的な人材マネジメントのメソッドを、より強く求める人の心理が影響していると思います。長いコロナ禍を経て、企業や職場の働く環境は大きく様変わりしました。デジタル化も相まって、リモートワークや非接触型の人材管理が、今や当たり前となっています。1on1などの個別的な支援や管理に象徴されるように、個を重視したマネジメント、ないしはリーダーシップが今まで以上に求められるようになってきました。人材を集団として捉える人的資源よりも、一人ひとりの能力や価値というメッセージ性を含む人的資本の方が、人材マネジメントのあり方を表す中核概念として、よりしっくりくるのだと思います。

02「人的資本経営」の導入を目的としてはいけない
日本においては、人的資本経営がバズワード化しつつあります。この状況をどう捉えておられますか。
経営学の分野にも様々な学者がいます。個人的には、人的資本経営という言葉がバズワード化することで、経営学者全般が経営における人の価値により注目するようになったという点で、少なからぬ意義があったのではと思います。例えば、「経営においては人材よりも戦略やビジネスモデルの方が重要だ」という議論が少なくなかったりします。そういう意味では、人的資本経営というものが経営実務、あるいは経営学に一石を投じることができたという点で、意義があったと思っています。
ただし、どのような経営手法や考え方でも言えることですが、ある特定の経営や人事の手法・考え方が流行していく段階では、より注意深い洞察が必要だと思います。大切なのは、本質を見極めることです。
ところで、経営学の議論に「マネジメント・ファッション理論」というものがあります。新たな経営に関する手法や考え方を、メディアに影響力のある経営者やコンサルタント、学者、最近ではインフルエンサーなどが紹介したり、推奨することで、急速に社会に広まって熱を帯びていく、そういうプロセスがあります。しかし一旦、流行のピークを迎えると、今度は一転して人々が一気に関心を失っていきます。これがマネジメント・ファッションのサイクルです。
平たく言えば、世の中に新しい経営手法や、パスワード的に流行になるような言葉や概念が出てきては、一時的に人々は注目しますが、ピークを越えるとスーッと消えていく、それが社会で連続的に繰り返されていく現象のことを「マネジメント・ファッション理論」が説明しているのです。
特に注意しなければいけないのは、流行の初期段階です。この段階は、「これが新しい」とか「最新だ」とか、「今来ている」と煽られる、そういう状況です。この初期段階において人々は冷静さを失いがちになり、「流行の罠」にはまってしまう経営者や人事担当者も少なくありません。人的資本経営に関して例を挙げると、表面的な理解で人的資本経営という言葉を社内で多用し、現場で混乱を招いているケースはよく耳にします。また、社内で人的資本経営の何が重要なのかについての議論もなく、導入すること自体が目的と化して、本来追求すべき自社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスを見失ってしまうことにもなりかねません。その結果、社内リソースを著しく無駄遣いしてしまうこともあるでしょう。最近は、人的資本経営という言葉が一人歩きをし、その名の下に、あれもこれもと新たな取り組みや制度が推奨されるという状況になっていますが、注意が必要だと思います。
人的資本経営の本質は何かというと、「人材に投資をすることで人材の価値を高め、中長期的な企業価値を向上させる」ことです。平たく言いますと、中長期的に自社のありたい姿、自社がこうありたいという姿を実現するには、現状をどう変えていくのかに真摯に向き合って取り組むことが大事です。つまり、ありたい姿に近づける、実現させるためには、どういう人材を採用し、どのような人を評価し、そのためにはどうやって育てるか。これは、人材マネジメントの基本中の基本ですが、ここを愚直にやっていくことが、人的資本経営の本質だと思います。

03経営者や株主だけでなく多様なステークホルダーからの企業価値へのシフト
ところで、人的資本経営と90年代以降の戦略的人的資源管理では、考え方がどう違うのでしょうか。
まず、戦略的人的資源管理ですが、これは実務の世界では戦略人事と呼ばれているものです。戦略人事を理解する上で重要なのが「フィット」と「ベスト・プラクティス」、この二つの考え方です。「フィット」というのは、文字通り、適合や整合性を指す言葉です。戦略人事では、事業戦略と人事施策の適合性や整合性を指します。事業戦略とは、企業の事業レベルでの戦略です。例えば、コストを削減しながらも市場を拡大していくとか、あるいはイノベーションを中心として事業を推進していくといったことです。一方、人事施策とは採用や評価、報酬、育成など取り組みや制度を言います。その二つが適合している状態が、企業の業績を最大化するという考え方です。
例えば、コモディティ化した市場でローコスト戦略をとる企業では、人件費を抑制するために、非正規社員を有効活用したり、表彰制度などの非金銭的なリワード(報酬)を使って社員の動機づけを促します。このような戦略と人事の最適な連動を図ることによって、企業業績の向上につながっていくという見方が戦略人事における「フィット」という考え方です。
一方で、「ベスト・プラクティス」いう考え方は、企業が採用する戦略如何に関わらず、企業業績を普遍的に高める特定の組み合わせ、人事施策の組み合わせがあるというものです。特に、組織への従業員の帰属意識(組織コミットメント)や職務への従業員の積極的な関与(ジョブ・インボルブメント)を高める施策が業績を向上させるという前提のもとで、例えば従業員を意思決定に積極的に参画させたり、また公平な処遇を担保する施策を導入するなどの施策を組み合わせたものが「高業績人事施策」として戦略人事の研究では提起されています。つまり、人材のコミットメントやインボルブメントを高めるのに一定の効果がある人事施策は、戦略や文脈の如何に関わらず、企業業績に貢献するというのが「ベスト・プラクティス」という考え方です。
この「フィット」と「ベスト・プラクティス」、両者の共通点は何かというと、いずれも企業業績へのインパクトに焦点が当たっていることです。つまり、人事制度や施策がうまく機能しているか否かを企業の財務的な指標のみで評価すること、戦略人事ではここをすこぶる強調しているのです。もちろん、営利の追求は企業の重要な目的ですから、それ自体は否定されるべきではありません。ただし、企業の財務的なリターンを最大化する目的のみで、人事の制度設計や運用をしてしまうと、経営者や株主は利益が増えて喜ぶかもしれませんが、実際の働き手である従業員が楽しく働く環境を提供できないケースも出てくるようになります。
少し前に「社畜」や「ブラック企業」という言葉をよく聞きました。まさにその状況になるわけです。要するに、人事の制度設計や運用を企業側が短期的な財務リターンに重きを置いて考えると、例えば、100%会社都合の配置転換や長時間残業の横行など、個々の従業員の意思や希望を極端に軽視した運用であっても、財務的なリターンがあるのであれば、それはやるべきだという発想のもとで展開されていました。それは、戦略人事のフレームワークの中では、是とされていたとまでは言いませんが、少なくとも許容されていたと思います。つまり、株主価値を最大化させるために人材を酷使するマネジメントが、ある意味横行してしまったというのが、戦略人事がもたらした負の遺産だと思います。
一方で、「人的資本経営」で何が前面に出ているかというと、多様なステークホルダー(利害関係者)から見た企業価値の向上です。つまり、経営者や株主のみならず、従業員や顧客、取引先、地域社会、一般市民、もしくは行政関係者など、企業に直接あるいは間接的に関わる多様な人々(ステークホルダー)から見て、総じて評価される企業になるためには、どのような経営を進めていくべきか、そういう点から人材のマネジメントのあり方を考えましょうというのが、人的資本経営で強調されている部分です。
日本では人的資本経営という言葉が先行していますが、世界の人材マネジメント研究では、この人材マネジメントの考え方を「サスティナブルHRM」と言っています。もちろん、ヒューマン・キャピタル・マネジメント(注:人的資本経営の直訳)という言葉もあるにはあります。しかし、今日本で広まっている人的資本経営は、ヒューマン・キャピタル・マネジメントよりも、このサスティナブルHRMに近い概念だと思います。サスティナブルHRMは、組織内外の多様なステークホルダーのニーズを満たすことが目的です。人事が上手く機能しているか否かを、財務的なKPIだけでなく、従業員の幸福度、あるいは環境に配慮したグリーン行動の実践度、労働市場での企業ブランディングやレピュテーションなど、多様な指標から評価していくこと、これがサスティナブルHRMで強調されています。
先ほど人的資本経営の本質は、「人材に投資することで人材の価値を高め、中長期的な企業価値を向上させること」と申し上げました。ただし、この企業価値は株主価値に限定してないことがポイントです。従来の戦略人事の枠組みでは、企業価値は株主価値や財務的なリターンに限定されていました。今言われている人的資本経営ではこれを多様なステークホルダーから見た価値に置き換える、ここが重要なポイントだと思います。
人的資本経営において、例えば人材版伊藤レポートでも強調されているのが“As-Is”と“To-Be”のギャップを埋め合わせるという視点です。“As-Is”が自社の現状で、“To-Be”が自社のありたい姿です。ここの埋め合わせを強調しています。まず大事なことは、ありたい姿を描くことです。経営者や株主だけではなく、従業員や顧客、地域社会などが何を望んでいるかをしっかり把握し、それらを踏まえた“To-Be”像を描いていく必要があります。そこに向かって、どういう人材が必要なのか、そして、その人たちをどう評価し、どう育てていくのかが最大の課題になってきます。
サスティナブルHRMは、日本の人事メディアではなかなか聞かない言葉です。
確かにそうですね。10年ほど前だったと思うのですが、海外で開かれた学会で「戦略人事、ストラテジックHRM」の話題をしたら、「それはもう古い。Sはサスティナブルだよ」と言われてしまいました。昨年、組織行動研究者が集まるヨーロッパで最大の国際学会で研究発表をしたのですが、そこでは各論文がSDGsのどの目標に関連し、その課題解決にどう貢献するのかが重要な評価基準になっていました。欧州ではサスティナビリティやSDGsも本気度が違うなと改めて痛感しました。標語としてSDGsを掲げているのではなく、本当に心底からやらないといけないと理解し、SDGsの考え方や行動規範を社会に組み込んでいます。日本ではサスティナビリティ、あるいはSDGsを行動レベルにまでまだまだ落とし込めていない気がします。

竹内 規彦氏
早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授
名古屋大学大学院国際開発研究科博士後期課程修了。博士(学術)学位取得。専門は組織行動論、人材マネジメント論、および職業心理学。東京理科大学・青山学院大学准教授等を経て、2012 年より早稲田大学ビジネススクールにて教鞭をとる。2017年4月より現職。2022年より京都大学経営管理大学院にて客員教授を兼務。
米国Association of Japanese Business Studies会長、経営行動科学学会会長、Asia Pacific Journal of Management副編集長、 欧州Evidence-based HRM誌編集顧問等を歴任。組織診断用サーベイツールの開発及び企業での講演・研修等多数。