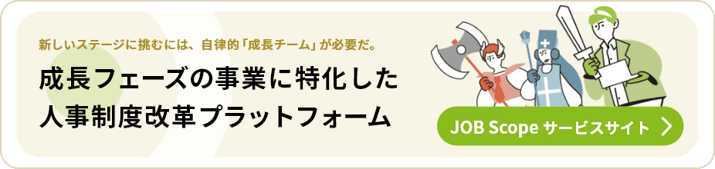生産年齢人口の減少が加速する日本。どの企業も人材確保が喫緊の課題となっている。特にこの先、5年・10年を見越すと若者世代を何とか迎え入れたいところだが、採用はもちろん、せっかく入社に至っても定着が厳しいとあって経営者や人事の悩みは尽きない。こうした中、「マーケティングや社員の採用・育成などの企業活動にアップデートが必要だ」と提言するのが、産業能率大学 経営学部 教授の小々馬 敦氏だ。今後はZ世代に次いでα世代へと主役が切り替わっていく。企業としてどう向き合っていけば良いのかを聞いた。インタビューの前編では、Z世代の行動特性と早期退職の現状などを語ってもらいました。
目次

01社会に対する貢献意欲が旺盛なZ世代
Z世代にはどのような価値観や行動特性が見られるのでしょうか。
Z世代(1997年~2009年に生まれた世代。約1500万人)は、年齢幅が大きく、一番上が今年で27歳ぐらいからですが、2、3年ごとにその特性は変わっていきます。その背景には、学生時代から常に手元にあるスマホで常時ネットにつながり、SNSが生活情報のプラットフォームとして浸透していく過程に成長してきたことがあります。
世代に共通する価値観は、爆発的に膨大していく情報環境に暮らす中で、「情報に惑わされて失敗や後悔をしたくない」という気持ちがあります。また、「社会貢献意識や利他の想いが意思や行動の前提にあることも共通しています。これは、中学高校時代からエコやSDGsをテーマとした授業が受けていて、「周りの人や社会に役に立てたら嬉しい」という感覚が常識として備わっているからです。この意識は年齢が下がるほどに強い気がしています。就職する会社を選ぶ際にも前提となっていて、そうでない生活環境をなんとなくでも選択肢から外すスクリーニング(ふるいわけ)を行うことが仕事を選ぶ際の特性として顕著です。
Z世代が貢献意欲を重視すると伺いました。それは誰に対して貢献することなのですか。
今つながっている仲間以上、自分からは少し距離感のある社会ではないでしょうか。今はまだ、そこに繋がっていないけれど、この会社に入って、この人たちと一緒に働けるのであれば、自分も社会に繋がり何か貢献することができるという自己有用感を実感したいという想いがあり、また自身の成長を感じるのだと思います。
Z世代が「成長」のイメージを絵にすると、彼らは私たちのように階段や山を登っていく、上昇志向の絵を描かないですね。人の繋がり(ネットワーク)が水平的に広がっていくような絵を描きます。中学や高校より大学生の時がつながるネットワークは広くなり、できることが増えた。これから社会人になるともっと多様な人とつながり、できることがもっともっと大きくなっていく。そのように感じていると思います。だから、会社に入ってどんな人と一緒に過ごすのかということを大切に考えています。

02Z世代にとって働くことは優先順位の一番ではない
Z世代における働きがいはどこにあるのでしょうか。
上の世代との違いは、働くこと(会社での時間)が優先順位の一番には来ないということです。私たち世代は、自分や家族の生活のために働く時間を第一に考えて、以外の限られた時間を「余暇」として、その時間を大切にして楽しみたいという生活をしていました。「仕事が1番で、家族との時間・余暇が2番」という優先付けの時代だったと感じます。
Z世代とその下のα世代になると、そもそも、親の世代にワークライフバランス意識や育休制度などが浸透していて、家族と過ごす時間が多くなっていて、「家族と過ごす時間が1番」という意識が高くなっています。
「生活するために、働くことは重要」という認識は昔から変わりませんが、自分にとって最も重要なのは、家族であり友人たちと過ごす時間であり場所、この環境が居心地の良いファーストプレイスであり、会社での時間、人とのつながりも大事ではあるけれど、セカンドプレイスなのだということを会社側(経営者)が理解尊重することが必要だと感じます。
Z世代にとって理想の上司像を教えていただけますか。
「理想の上司像は?」という問いにピンとこないかもしれません。これも、下の年齢層ほど傾向が強いと感じますが、普段からSNSのアプリやオンラインゲームの環境で、性別や年齢、社会的身分などを機にすることなく好きなことが似ている人と緩く繋がることに慣れていますので、「ヒエラルキー(階層や階級)があるピラミッド組織」が苦手に感じます。他者からマウントや圧をかけられることにストレスを感じるので、「上司」というワードからしてネガティブになるかもしれません。
先ほどもお話ししましたが、どういう人たちと一緒に働けるかに興味があり、誰の下につくか、理想の上司という感覚は持ちにくいかもしれません。学生を見ていての感覚ですが、全体の1割、2割は昔ながらの上昇志向が強い子たちはいます。学生たちは「バリキャリ」と呼んでいます。そういうタイプの学生の方が、理想の上司というワードに反応すると思いますが、全体的にはピンとこないままに、自分がリスペクトできる人を答えている気がします。
それと、Z世代はロールモデル(キャリア形成の模範)を信じません。恐らく、親世代の影響も受けています。X・Y世代にあたる親世代は、就職氷河期を経て、所謂、平成の失われた20-30年に働き、成功体験が少ない世代です。上の団塊世代(1947年~1949年に生まれた世代。約690万人)は、40-50代で役職が付き楽しそうにやっていたものの、それが自分たち世代には降りてこなかったという感覚がありロールモデルを信用していないと聞くことが多くあります。学生に聞くと、家庭でこのような親の体験を聞いていて、同じような意識を持っていると見えます。

03ヒエラルキーや押し付けを嫌うのもZ世代の特徴
Z世代はヒエラルキーを好まないということですね。
そうですね。完全なフラットな状態を望むということではないのですが、上下関係から降りてくる、大学の授業で扱う伝統的なカスケード型組織を知ると、「圧がありそう。」と感じている気がします。
押し付けられる、決め付けられることをとても嫌います。それは、会社の組織だけではないですね。広告やPR案件でのメッセージに関してもその反応を頻繁に耳にします。例えば、「この商品は、あなたにピッタリな商品です。」「あなたが今、選ぶべきベストな商品です」というメッセージは、「それって、誰が決めたの」と最初からはね付けられてしまいます。
Z世代は就職活動にあたり、親の意見を重視するのでしょうか。
多分、これからもっと強くなると思います。Z世代の下のα世代(2010年~2024年に生まれた世代。約700万人)、現在の中学生以下には如実に現れると思います。どういうことかというと、この世代は幼少の頃からたくさんの習い事に通っています。それは、親が子どもたちの好きなことを見つけてあげたい。興味を持ったらなるべく沢山やらせてあげたい、自分も子供と並走して好きなこと得意なことを見つけて伸ばすことを支援してあげたいという気持ちが強いです。
就職活動にしても、親が「この会社が良い」と強く口を出すことはしないものの、親子は一緒に過ごす時間が増えていて仲が良く、子供も親に就職のことを話し意見を聞きます。親も、会社のことを色々と調べて共有して応援する関係性の中で会社選びをするようになっています。現役の大学生でも年々強くなってきます。

04Z世代の親は子どもに並走し、支援したいと願っている
人事担当者としては、就活生はもちろん、その親とも何かしらの関係性を構築しないといけないということでしょうか。
来年、2025年ぐらいからこの傾向が目に見えて強まっていく気がします。数十年前ですと親の興味は会社の知名度、規模、社会的地位にあり、その量的な印象から子供の生活の安定を確信していたのでしょうが、現在はネットを調べれば会社の中のこと、もっと深い定性情報が見えるので、親子で一緒に調べてみることがあるようです。
Z世代でも、これから就活を行う現役の大学生はネットリテラシーがより高くなっていきます。自分で詳細な情報をすぐ調べてしまいます。自分がこの会社に入って1〜3年目ぐらいは、どのような生活ができそうかとリアルに調べます。OB・OG訪問の際には、ネットではわからない情報を確かめに行きます。就活に親がバーンと入ってきて意見をいうわけではないと思いますが、子供の意向を尊重しつつ親も調べてみて「大丈夫!」と背中を押して応援する関係なのかと思います。
そういえば、昨今は内定者の親を対象とした企業訪問を実施する会社もあると聞いています。
そうした親への気遣いよりも、子供がその会社との縁が近くなった時に、親が調べても子供が調べても、安心できる企業情報がしっかりと伝わる企業広報が準備されていることが重要だと思います。中の人とか、裏を見たいと情報を取りに行った際に、知りたい情報が見つかることに安心感や信望を認識すると考えます。親が期待する優先は、授業参観のように実際に職場を見たいということではないと思います。

05若者の早期退職は今後さらに増えていく
昨今は、Z世代を含め若者の早期退職が目立っています。中には、退職代行サービスを利用する人も増えていると言われています。どう捉えておられますか。
この件は、メディアが限られた現象をとても頻繁に起こっているように伝えているのではないかと思います。恐らく退職代行サービス(従業員に代わって会社に退職の意思を伝えてくれるサービス)の利用者は、新卒よりも上の年齢の方が多い気がします。新卒の場合、環境が合わなくて辞めたくなった時に身近に相談できる相手がいなくて、自分でも言えない方が利用しているのではないでしょうか。
新卒で会社に入ったものの、思い描いていた環境と違ったというギャップは誰でもあるはずです。中でも、一番深刻なのは職場で一緒の人と合わないことでしょうね。会社のことは大体理解して入っているはずです。やりたい仕事や成長の機会があることにも向き合えていると思うのですが、一緒に働く人とそりが合わないということのストレスが大きいようです。人事部に掛け合って、他部署に異動をさせてもらい解決することもありますが、多くの場合、それは難しいので転職を選択するしかなくなります。人とのケミストリー(化学反応、化学現象)みたいなものを、すごく重要に考えています。それが原因で辞めていることが多いと思います。
もう一つは、高校時代の友だちや大学の友人たちが同じ時期に会社に入り、どんなふうに過ごしているかがSNSで全部見えてしまうことの影響もあります。どちらかというと羨ましく思うシーンが見えてくるので、発火点になり自分が行動を起こすきっかけになりやすいんです。昔と違うところだと思いますね。
若者の早期退職に企業はどう向き合っていけば良いとお考えですか。
そうですね。早期退職は社会全体としては止められず今後もっと増えていくと思っています。人材の流動性、それを推す社会の空気が高まっているからです。企業側としては、自社の社風、経営の信念に関して実直に伝えて、共感する学生とのマッチング度を上げていくしかないと思います。家族的な経営、体育会系のかっちりした社風、オープンな働き方など、働き方の好みに対する価値観は、Z世代ではより多様になっており、社風を若い世代に合わせていくよりも、割合は少なくても、自社が大切にしている社風や姿勢に共感し支持する学生は必ず見つかると感じるからです。Z世代は共感力が高いので、会社の考え方をしっかりと伝えることが大切なのではないでしょうか。
もう一つは、日本の企業にこれを直ちに求めるのは難しいと理解していますが、人材は社会を流動するものと割り切って考えることも必要です。私自身が外資系企業の経営者を長く勤めました、数年間で全体の3分の1程度が入れ替わることを良しとしていました。新しい従業員は、具体的に「このプロジェクトをやりたい」と入ってくる。そのプロジェクトに数年間携わり達成感を味わえると、次の成長機会を求めて次の会社に移っていく。人材が、好きなこと、やりたいことのプロジェクトを目的として社会を流動していきます。経営者の視点からは、常にプロジェクトに最適な人材が集まり、モチベーションが高いチームによる課業が進む。プロジェクトが達成すれば、チームは解散し、それぞれ次のプロジェクトに移っていくというポジティブな人材流動となります。私の会社はコンサルタント業でしたので、このような捉え方ができました。もちろん、業界・業種・職種によっては難しいのかもしれませんが、経営者の考え方次第だと思います。

06ポジティブに卒業していける会社が逆に話題を集めている
企業経営者やマネージャー、人事担当者からは、「せっかく手塩に掛けてここまで育てて来たと思ったら辞めてしまう。何なんだ」という愚痴も聞こえて来ています。
「あの会社はすばらしい」と評判の会社は、辞めていく方も結構多いのではないでしょうか。ただ、退職後に色々なところで活躍されています。「あそこの卒業生は良いよね」という評判が生まれると、その評判を聞いて、その会社を目指して人がどんどん入ってくる。そんな、ポジティブな流れに持っていけている会社もあると思います。
「自分が成長できたのは、この会社での経験や同僚のおかげ」と実感してポジティブに卒業してもらう関係が後に効いてきます。そうすると、「うちの会社で活躍できるように教育や支援をする」という考え方だけでなく、「他の業界業種に行っても活躍できるような人材を社会に輩出しよう」という想いから、個人の才を見つけて伸ばすタレントマネジメントを打ち出すことが従業員を求心することにつながると思います。従業員の才は社会資本で、あり、経営とはその社会資本を借りて、社会価値をつくり社会に還元することという経営の本質に立ち返ることが、タレントマネジメントの起点になります。
Z世代は、会社を選ぶ時に、企業の理念をしっかりと見ています。「経営理念に共感して応募しました」と面談で良く言っていることと思います。しかしながら、企業の方は、学生の言葉をあまり信用していないようで、「ホームページをぱっと見てきて、言っているよ」みたいな感じで対応されることが多いと聞きます。学生は「この会社、社員に理念が伝わっていないのでダメな会社」と感じています。
Z世代の大学生は、理念に共感して、そういうことを信条としている経営者、同僚と一緒に仕事がしたいと感じます。しかしながら、理念は抽象的な言葉の世界観なので、一方で具体性を求める傾向があります。自分のミッション(使命感)を感じながら、今、自分が従事している仕事がしっかりとこの理念の実現に貢献できていると実感できるように、プロジェクトベースで経験させてあげることが求められます。スキルをどれくらい高められたかを測ることは難しく、むしろ、どのようなプロジェクトを経験できたかの自覚が大切なのかと思います。1年間で1つ、2つずつでも増えていくこと実感させてあげることは、結果的にその企業に長く勤めることにつながると思います。

小々馬 敦氏
産業能率大学
経営学部 教授
1983年青山学院大学経営学部卒、第一広告社(現I&SBBDO)やインターブランドジャパンにて戦略プランナー、事業開発、経営企画に従事。その後、米国のブランドコンサルティング企業数社の日本法人代表を歴任し、国内外企業の無形資産価値経営、パーパス経営とブランディング、マーケティングの連携を支援。2013年より産業能率大学 経営学部教授を務める。