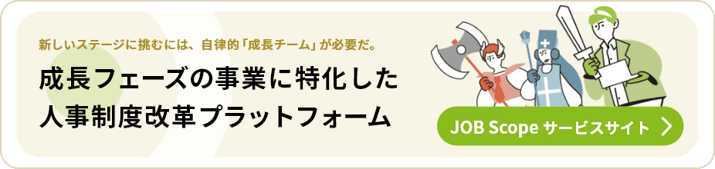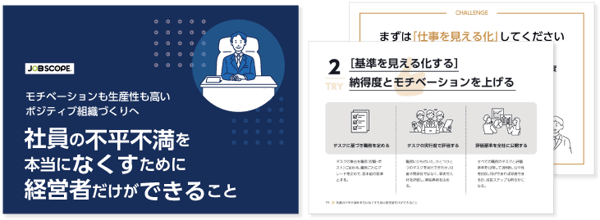今から170年ほど前、黒船の来航が日本の近代化への扉を開いた。そうした動きは、時代を経た今も変わっていない。グローバルな圧力に日本がどう対応していくのかが、問われている。その一つに制度的な圧力がある。常に主導権を握っているのは欧米。日本は、右往左往しているのが実態だ。人的資本経営やそれを巡る情報開示のトレンドもその一つかもしれない。企業としていかに対応し、業績向上につなげていくか。世界の投資家が、その動きを注視している。こうした中、国際経営の視点から日本企業に価値ある提言をしているのが、東京大学大学院経済学研究科・経済学部 准教授 大木 清弘氏だ。特に今回は、日本企業において圧倒的な割合を占める中小・中堅企業をメインに、あるべき姿を語ってもらった。前編では、人的資本経営がトレンドとなっている背景や製造業における人づくりの実態などを聞いた。

01日本の製造業における
「人づくりは大事」との
発言には疑問
まずは、研究者としての大木先生のバックグランドを教えていただけますか。
私自身は、元々国際経営を専門としています。主に日本の製造業の海外展開、それもマーケティングというよりも製造拠点を中心に、どうやれば海外製造子会社のパフォーマンスを向上できるかを研究していました。多くの方にお世話になり、これまで数百の現場を拝見してきましたが、現地で数千人、一万人もの従業員を抱える工場において、パフォーマンスを高めるために必要なことは、当たり前ですが、現地の組織がしっかりしていることでした。もちろん、他にも技術移転など様々な要因があるのですが、拠点の運営に関しては、現地にいる駐在員の方やナショナルスタッフらのチームワークが大事で、よい組織の状態を作るために本社はどうあるべきか、人材育成をどうするべきかを研究していました。そう言った文脈で人材育成に触れる機会をずっと持っていたわけです。
そうした研究を通じて、多くのものづくり企業と接点を持ってきたのですが、ものづくり企業は海外だけの文脈でなく、国内のものづくり現場という点でも、人材育成を非常に重視していました。ただその半面、2000年ごろから派遣であるとか、短期雇用などが増え、人を固定費と捉え、悪く言えば使い捨てにするような動きも出てきました。結果、現場の方々は、長期的な人材育成が難しくなり困っていたのですが、本社側からすると費用が削れるということで、一部の企業はそうした動きを進めてきた背景があります。そうした状況があるため、多くの製造業の方々が「人づくりは大事だ」と言うものの、個人的には「実際には違うのではないか」と思いながら研究をしていました。
そうしたもやもやとした思いがありながら、私が東大に戻って来てから数年後、2016年ぐらいに、とあるものづくり企業の方からご紹介を受けて、人事の方が出席する勉強会などに顔を出させていただきました。そこで勉強させていただく中で、逆に本社の人事の方々はホワイトカラーに寄った議論をされている印象を抱きました。当時は日本の人事システムを否定し、米国西海岸の人事システムを評価する風潮もあり、「日本企業はどうするべきか」といった議論を幾度も交わしていました。
こうしたご縁の延長上から、2019年くらいに「人的資本の情報開示の流れが来ている」というお話を逸早く伺いました。そのため、2020年や21年ぐらいから、人的資本に関する議論に加えていただきまして、書籍なども出すことができました。今日のようなトレンドになる前から、さまざまな方々から人的資本経営に関して教えていただけたというのは、大変幸運でした。

02投資家は、新たな要求に
敏感に反応できる
会社であるかを重視
「人的資本」に基づく経営が、世界のトレンドとなっています。その背景をお聞かせいただけますか。
人的資本に基づく経営がなぜ世界のトレンドになっているのか、私なりの理解を少し説明したいと思います。株主の視点に立った時、株主はよい企業に投資をしたいと思います。本当に昔は、その企業がどんな資産を持っているか、どのような不動産を持っているかなどに注目して、「この企業は良いよね」と判断していました。次に、「利益率など数字が良い企業に投資しよう」という風になっていくのですが、企業の会計不祥事も起き、そもそも会計情報は現時点の状況であり将来を保証するものではないことが段々とわかってきました。そうすると、やはり良いビジネスモデルを作れる会社であるとか、新商品や新技術を生み出せる会社が良いと考えるようになってきました。
一般に投資家と言うと、我々にはどうしても2000年代のハゲタカファンド的なイメージがあります。そうした短期的な投資をする方々は今ももちろんいるのですが、中長期保有を前提として、企業の健全な成長を期待する投資家が少なくありません。そうすると長期的に保有する中で伸びる企業とは何かを知りたくなります。しかしこれは、数字だけの情報ではわかりません。現時点の情報だけでも不十分ですし、一般的に世の中に出ている情報だけでは、これから先その企業がどうなるかは不明瞭でした。そこで「将来のパフォーマンスに影響を与えるものは何か」を改めて考えた時に、「人的資本」が一つの解として、現在提示されています。
長期的に成功する企業は新しい知識や新しいビジネスモデルを生み出せる会社です。それを生み出すのが人である以上、人に投資をするということは、将来的に事業が成功する可能性が高い企業である、という考えです。しかし今まで、企業の人への投資情報は定量的には示されていなかったので、投資家が企業に外部に見せるように要求しているというのが、人的資本の情報開示のトレンドの背景であると考えています。
特に日本でこの点が強調されるようになったのは、岸田政権の「資産所得倍増プラン」だと思います。要は「株価を上げていきましょう」という話ですので、人的資本経営を推進していけば、海外を含め多くの投資家からの覚えが良くなると考え、政府も注目しているのではと推察しています。
ただ、私自身は別の観点からも解釈しています。皆さんからすると、ESGや人的資本の潮流は「やらされ仕事で面倒くさい」と思われると思います。ここがポイントです。こういう面倒くさい外圧に対して、逸早く動ける企業とそうでない企業がいたら、投資家はどちらを評価すると思いますか。それは前者です。なぜならば、逸早く動ける企業というのは、新しい要求に対して敏感に対応できる会社であるということで、世の中のトレンドを理解していたり、新しいトレンドにスピーディに対応できる意思決定の仕組みを持っていたりすることを示すことになるからです。平場では甲乙つけがたい企業をあえて揺さぶることで、投資家が良い企業と悪い企業を見極めようとしているとも受け取れます。
ですから、人的資本が良いかどうか別として、「人的資本経営をやります」と言ったら、いち早く動ける会社、言い換えれば環境変化に強く信頼できる会社と評価してもらえます。つまり、本当に人的資本が大事かどうかはまだわかっていなくても、それに対応できるということは、組織として外にアンテナを張っていて、スピーディーに動けることを示せるわけです。これ自体は、恐らくVUCAと言われる世の中で求められる能力です。もしかすると人的資本にこだわりはなく、投資家の発言に逸早く動く企業を見極めようとしているだけかもしれません。
以上をまとめますと、投資家側からするとより長期的に儲けたいと思った時に、長期的に企業の成長に繋がる要因として、人的資本への注目が集まっている、というのが第一の背景です。加えて、「日本で人的資本経営が流行っているのは何故ですか」といえば、資産所得倍増に向けて株価の上昇をアピールしようという政治的な背景があったということになります。また、人事コンサルが次のネタを見つけたというところで盛り立てているところも背景にはあると思います。
日本では、ものづくりは人づくりという言葉が良く聞かれました。果たして人を大切にした経営ができていたのでしょうか。
難しいですね。私は製造業を中心に見てきたので、製造業のホワイトカラーの方やブルーカラーの方を念頭に置きながらお話をさせていただきます。
ある研究にもとづいた話をさせていただきます。日本では戦後復興の中で、人材が不足する局面がありました。その際、人材を確保するために、高卒の方を工場のオペレーターとして雇うということになりました。それまで、高卒の方は事務職で働く方が多かったため、高卒で工場の現場で働く方の待遇も、そういった事務職の方と近づけることが求められました。その結果、ブルーカラーの方とホワイトカラーの方の「待遇的な近接性」が生まれたとされています。実際に、日本はホワイトカラーの方とブルーカラーの方の賃金格差が、世界で見ても非常に低い国です。例えば手元にある2020年のジェトロ(日本貿易振興機構)のデータですと、日本では現場の方と課長の賃金格差が2倍以下なのに、タイのバンコクでは9倍であるというデータがあります。ブルーカラーの待遇という意味では、大切にしてきたとは言えます。
戦後基本的に人手不足だったため、従業員にはなるべくやめて欲しくなかったのです。それで、いわゆる終身雇用や年功賃金という形を取って、会社にずっと在籍してもらえるような経営をすることになったわけです。結果、多くの人は就職すれば、一定の生活ができるし、家族を持てるとなり、いわゆる1億総中流みたいな状況となったわけです。辞めて欲しくないので長期的に囲い込む中で最低限度ではなくて、それなりの生活を担保しながら、それぞれの方の暮らしを守って来たという側面はあると思います。
これが、人を大事にしていると定義できるのかどうかは非常に難しいです。恐らく、日本的経営の中では、非常に頑張る方も頑張らない方もいたと思います。実際、私の父は70代なのですが、「俺は頑張ったけれど頑張らない奴もいた。でも別にそれはそれでよかった。組織とはそういうものだ。その分、自分が頑張って会社が成長するのが喜びだった」と口にしています。そういう価値観を持っている方からすると、皆がハッピーという状況が理想だったと思います。ただし、今は違います。成長が止まり、企業に余裕もなくなっているので、頑張っている人が働いていない人と同じような待遇であったりすると「おかしい、頑張っている人が報われない」という声が増えています。
すなわち、過去は「頑張る人も頑張らない人も一定の待遇を受ける」ということが人を大事にしているという風に考えられてきたのですが、価値観や社会情勢が変わった今では、「頑張った人が報われていない」ことが人を大切にしていないことであると捉えられるようになったのです。
このように人を大切にしているかどうかの判断は、価値観によって変わってくると思います。今のうちの学生に聞いても、終身雇用でそれなりの生活ができるのであれば、仕事の面白さもあると思うし、日本的経営の企業もOKでいう学生も少なくありません。しかし、今の日本企業は採用人数も絞っているし、終身雇用かどうかもあいまいです。そのため、スキルや専門性が身に付きそうな外資系企業に行く、という選択もしている学生も多いです。大切にするという定義が変わって来ているので、答えるのは難しいなと感じます。
人づくりができていたのかという点に関しては、人づくりを積極的にしていたのは事実だと思います。それが意図としてどうだったのかわからないですし、そのやり方が今日にも通用するかどうかはわかりません。ただ、いわゆる当時のやり方は、今で言うパワハラみたいな鉄拳制裁も多かったと伺っています。人格的なところまで含めて色々な育成の仕方をしていたと思います。なので、今ほど体系立った育成はしておらず、個人差がある状況だったと思います。しかし、当時はそれでも、転職が今ほど普通ではなかったので、会社を辞めることへのハードルは高く、皆残りました。かつてのやり方は間違っていたかもしれませんが、結果的に皆その企業の中に残らざるを得ず、その中で個人が成長し、会社全体も成長したのです。
ただし、当時の日本企業は色々と失敗の機会も沢山あったのだと思います。近年駐在員から良く聞くのは、「1990年代に中国の工場に若手が行くのと、今の中国の工場に若手が行くのでは、得られる経験値が全く違う」という話です。「若いうちに海外に行く方が良い」という話はよく聞くのですが、1990年代の中国に行くのと、今の中国に行くのではそこで得られる経験の質が違います。1990年代のまだ工業化途中の中国で現地のナショナルスタッフと汗をかきながら工場を立ち上げた20代と、現在すでにある程度完成し、ナショナルスタッフだけでほぼ回せている中国の工場で働く20代では、前者の方が様々な修羅場を経験できるのは間違いありません。下手をすると、全部ナショナルスタッフの方が回しているので、お客さん扱いになってしまいます。
もちろん、当時の教育の仕方が本当に最善のやり方だったかはわかりません。そこは比較できないのですが、「生活の保障があったこと」「その会社に長期的に残ることが前提だったこと」「失敗の経験ができたこと」の三つが揃うことで、人材育成が一定のレベルで行われたと解釈できます。
また、もう一つ挙げるならば、そういう中で良くも悪くもコミュニティ意識が生まれていたことも見逃せません。企業に対する愛社精神とでも言ったら良いでしょうか。特に地方だと自分が勤務する会社や工場はその地域を支えています。社内の運動会や地域での色々な活動も含め、自分と会社が一体化するような政策が行われていたので、会社の成長のために自分も成長する意識が高まり、結果的に人づくりができていたと言えます。それを意図してやっていたかどうかはわかりませんが、当時の状況は、人が育ちやすい環境にあったのは間違いないと思います

大木 清弘氏
東京大学大学院
経済学研究科・経済学部 准教授
1985年神奈川県生まれ。2007年東京大学経済学部経済学科卒業。2011年東京大学大学院経済学研究科博士課程経営専攻単位取得退学、2014年関西大学商学部助教。同年10月から東京大学大学院経済学研究科講師。2019年から現職。博士(経済学)(東京大学)。『多国籍企業の量産知識:海外子会社の能力構築と本国量産活動のダイナミクス』(有斐閣、2014年)(国際ビジネス研究学会「学会賞(単行本の部)」受賞)の他、著書・論文がある。
【無料Ebook】
「社員の不平不満をなくすために経営者だけができること」