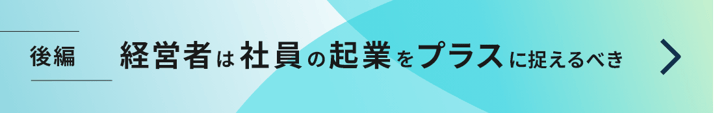>経営者は社員の起業をプラスに捉えるべき(前編)
働き方が多様化し、副業を解禁する企業も増えて来ている。ただ、実態として見ると、それほど社員に広がっているとは言い切れない。働きやすさをアピールするために掲げられたアドバルーンに過ぎなかったりする。そうした中、副業どころか社員の起業を推奨し、将来的には自社のビジネスパートナーとしての関係性構築を目指してみてはどうかと提言する経営学者がいる。東京都立大学大学院 経営学研究科 准教授の高橋 勅徳氏だ。今や社会も変わり、起業のスタイルも多様化してきている。昔のように一度失敗したら人生がジ・エンドとなるのではなく、敗者復活もできるようになった。高橋先生が提案するのは、もっとハードルが低い「ライフスタイル起業」だ。どんな起業の概念なのか、『ライフスタイル起業~ちょっと働き、ほどよく稼いで、ごきげんに生きる。』(大和書房)の出版を記念してインタビューしてみた。前編では、高橋先生が起業研究に着手した経緯やライフスタイル起業の特徴などを聞いた。
目次

01会社に頼らない生き方に興味があり、企業家研究に取り組む
高橋先生が、企業家研究に着目された経緯をお聞かせください。
僕は学生時代、神戸大学大学院で金井 壽宏先生(神戸大学大名誉教授、立命館大学食マネジメント学部教授)のゼミに在籍していました。1997年頃ですから、金井先生がキャリア研究を日本に大きく広めていらした時期でした。当然僕の先輩や後輩は、金井先生と関連するようなテーマを掲げて研究に取り組んでいました。キャリアの研究や働く人のモチベーションの研究などが多かったんです。
そんな中で、僕は起業というテーマに注目しました。もちろん、当初は金井先生の研究テーマに寄せて色々と考え、さまざまな経営学の文献を読み込んでいきました。ただ、そうしているうちに、「あれっ」と気づいたことがありました。周りの院生には、大学生の進路選択のような研究を手掛けていた方がいらっしゃったのですが、その多くが大学を卒業して就職活動し会社や役所に勤めるという選択肢を基本的な前提として研究していました。確かに、当時は日本人の大多数がそういう流れで就職活動をするのが、当たり前といえば当たり前だと思います。
しかし、僕がそういう会社で勤める人のキャリアやモチベーション、働きがいなどといった研究をやりたいかと、改めて思い直してみると、ある意味、経営学者としては致命的な問題を抱えていることに気づいてしまいました。僕自身、会社とかサラリーマン生活に全然興味がなかったんです。
それはなぜかと考えてみたら、親族がほとんど自営業だったからでした。まず、僕の父親は大工ですし、父親の男兄弟が7人いる中で、父親を含めて6人が職人だったんです。さらに、父の交友関係も基本的には自営業か会社の社長。子どもの頃から高校・大学を卒業するまでに出会った大人も大半が自営業で、会社に勤めている人がレアでした。おかげで、人のキャリアを研究テーマとして考えた時に最初に思い浮かんだ疑問が、「どうして自営業の人が経営学では対象にならないのか」でした。
職人の世界では独立と言いますが、会社を辞めて自分で仕事を取るようになるのは、あの世界では普通です。たまたま親方が工務店を経営していて、そこで従業員として雇われるケースもありますが、実際には弟子入りという形で働きながら、適当なタイミングで独立する。それが一般的なのに、彼らを対象にした研究がほぼ皆無だったんです。
とはいえ、キャリア研究では、米国の心理学者であるエドガー・シャインのキャリア・ダイナミクス(個人の生涯を通してキャリア形成の過程とその変化を説明する概念)では、起業や専門家として生きていくみたいなものも、人のキャリアとしてモデル化されていました。ただ、起業や独立を専門に研究している研究者は、今から30年くらい前はごく稀だったのです。「これはおかしいのではないか」と思ったのが、まず一つのきっかけでした。
やはり、自分に関心があるのは、そういうふうに起業したり、自営業をやったり、会社に頼らない生き方をしている人たちでした。そういう根本的な問題意識と同時に、学問として考えた際に「フロンティアではないか」と思ったんです。
研究をしている人たちが少ないということは、可能性としては二つ考えられます。一つは、独立や起業の研究は、やる意味がないと判断されている。でも、そうではないとしたら、たまたままだ誰も手を付けてない。基本的に多くの研究者は皆が取り組んでいる、一番ボリュームゾーンの研究をやりたがります。そうすると、人と起業の問題は、たまたま見落とされているだけかもしれないと考えたのです。
僕が修士論文を書いた1999年頃は、折しも日本でITバブルが起きていて、色々なところでベンチャーが誕生していました。日本ベンチャー学会ができたのも1999年です。まさに、社会的にも学術の世界でも起業して生きるという選択肢が注目された時期であったわけです。ということもあって、僕は起業を研究テーマとして取り上げました。どうやったら人は起業することができるのかを考え、経営学として取り組んでいくことに意味があるのではないかと思って始めたのです。
今、日本ベンチャー学会という組織名をお聞きし、以前法政大学の総長・理事長をされていらした故・清成忠雄先生のことを思い出しました。
清成先生は、ベンチャー企業、ベンチャー・ビジネスという用語を日本社会に定着させた方です。「中小企業の中にベンチャー企業がある」と説いていました。元々は国民生活金融公庫(現在は解散し、日本政策金融公庫に業務が移管)の調査部(現・総合研究所)に在籍されていたのですが、1972年に学問の世界に転身してからは、企業家研究の振興に大きな貢献をされました。清成先生が、「企業家が日本の産業をリードするような存在になり得る」と発信していただけたことが、まさに日本におけるベンチャー研究の始まりになったと思っています。
高橋先生も、2009年には日本ベンチャー学会清成忠雄賞本賞を受賞されています。ご縁がありますよね。
そうなんです。いただいてしまいました。

02低投資・低成長・低関与にこだわるライフスタイル起業に着目
ところで、「ライフスタイル起業」とは何かを教えていただけますか。
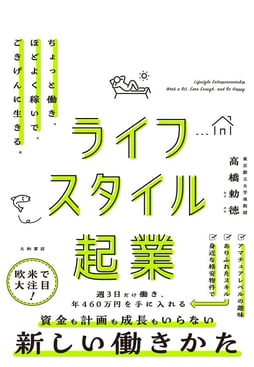
ライフスタイル起業は、英語では「Lifestyle Entrepreneurship」と表現します。2000年代初頭に、ニュージーランドのマッセイ大学などの研究者たちが中心に提唱され始めた新しい起業スタイルの概念です。
この概念は、主にニュージーランドやオーストラリアの小規模な観光業を対象として生み出されました。ベッドアンドブレックファスト(英語圏各国で見られる、宿泊と朝食をセットで提供する小規模な宿泊施設)の経営者や観光ガイドをしている人たちに注目して分析していくと、ある意味すごく非常識な行動をされている方が多かったりします。成長を目指さないし、大きく稼ごうともしない。しかし、自分たちのライフスタイルやワークライフバランスは大事にしていて、自分一人ができる範囲で、言うなれば自分たちの家族が幸せになる規模で会社を経営しています。
実はオセアニア地域で観光ガイドの事務所やベッドアンドブレックファストを経営している宿は、固定客が多くついていて、「あそこには良いガイドがいる」、「あそこには面白い宿がある」というのが地域の魅力になっています。その経営者たちは、基本的に常連さんたちを相手に小規模で自分たちが無理なく働ける水準の働き方しかしていないんです。
以前の経営学や観光経営学(観光に関連する経済的な事象を研究していく学問分野)と言われる分野では、そういう経営者は非常に未熟な経営者と見なされ、非難の対象でした。そうした人たちにこそ、経営学的な専門知識、それこそマーケティングや会計とか投資の仕方をきっちり学んでもらい、経営者としてもっと優秀になってくれたら、この地域の経済的な規模も雇用状況も向上するだろうというのが、2000年代までの考え方でした。
その考えが徐々に見直されてきたということですか。
そうなのです。2010年代ぐらいからむしろそちらの方が正しかったのではないのかという意見が出て来ました。事実、自分たちの常連さんを中心に、無理のない範囲で経営している人たちの方が、結果だけ見ると、長持ちしています。逆に、投資をして自分たちのベッドアンドブレックファストの宿を改装したり、従業員を雇ってという、自分が経営する会社を大きくするため、成長させるために経営的に常識的で正しい選択を行った会社は、ある日突然パタンと倒れるということが非常に多かったりします。それに対してマイペースで自分たちの常連さん中心に経営をしているガイドサービスやホテル業は、しぶとく生き残っています。
さらに研究者たちが調べてみると、継続的にオセアニア地域に来てくれるお客さんは、そういうマイペースなガイドや宿の店主に会うことを楽しみにしていて、それが地域の魅力になっていたんです。このような調査や現実を踏まえて、そういう人たちの働き方や経営スタイルから、起業を改めて見直そうじゃないかという中で出てきたのが、ライフスタイル起業という概念です。
その特徴として言われているのが、低投資・低成長・低関与です。まず彼らは、例えば観光客が沢山来ていても、銀行からお金を借りてホテルを大きくしよう、改装しよう、きれいにしようとはしません。なぜかいうと、お金を借りると借入金になって、月々返済をしていかなければならないからです。当然その返済をしていこうと思ったら、継続的にお客さんを増やしていかないといけません。借金をしたがために、経営の規模を維持していかないといけないという気持ちになってしまうのです。
で、そういうときに、例えばコロナ禍となり観光客が急に来なくなってしまうと、銀行から借り入れをして設備投資し大きくしたホテルから潰れていくわけです。それに対して、自分たちが持っている住宅を改装して始めたような、日本で言うと簡易宿泊施設と言われるレベルのものや、空いている土地にトレーラーハウスをポンポンと置いていってはじめたような、すごく低投資で作っているベッドアンドブレックファストの宿は、小さな規模だからこそコロナ禍でも耐えて継続していけます。
儲かるからといって積極的に投資をして、ホテルの規模を大きくしていくと、当然のことながら従業員を雇わないといけません。そうなると、借入金の返済に加えて、その分人件費もかかってきます。ということは、増やした人員と部屋数の分だけお客さんの数も維持しなければならなりません。経済や社会環境が安定している時はそれで上手く回るのですが、定期的に不景気が来ますし、自然災害や疫病などで経済活動が止まることもあります。そうなったときに、一番脆弱なのが経営学が今まで対象にしてきた、あるいは企業家研究という学問が対象にしてきた、成長を前提とした一般的な経営スタイルなのです。要は、私たちが当たり前と考えてきた、目指すような常に会社の規模を大きくするための経営スタイルは非常に脆弱であるということになるのです。
だとしたら起業は低投資・低成長のほうが、生活を成り立たせるという観点からはすごく良いのです。現状維持で十分だと。自分の体力や観光客の数に合わせて経営規模を縮小していっても、会社がパタンと資金繰りが崩れて止まることはありません。
低関与とは、どういうことでしょうか。
会社がある程度大きくなり、地域の中で有名になってくると、行政であったり、地元の政治家や経営コンサルタントが、色々な形で関与してきます。「この地域を活性化させてもっと儲かるようにしませんか」「補助金をつけますよ」「こうすれば会社を大きくできます」などと言ってくるわけです。それに乗ってしまうとどうなるかというと、当然のことながら銀行からお金を借りて設備投資をするだけでなく、補助金を行政からもらうことになります。そうなると、今度は責任が発生します。同時に、行政の支援の計画の一部に組み込まれていって、やりたくない仕事ややらなくて良い仕事もやらないといけなくなって来てしまいます。
それが、最終的に巡り巡って首を絞めることになっていくので、ライフスタイル企業家は自分のビジネスに直接関係のないことは、極力やらないようにしています。他者から協力を依頼されても、地元行政から業務を依頼されても断固断わります。もちろん、全く非協力的なわけでもなく、例えば自分たちがガイドしている山や海のように、観光資源として利用していて、観光客も目当てにしているような自然環境に対して政府や企業が開発計画をぶち打ち上げて大きく変えようとするときには、環境保護活動を主導したりします。しかし、あくまでも、自分たち中心。要は自分のライフスタイル、生活圏をいかに守っていくのかを中心に据えた起業スタイルがライフスタイル起業というものなのです。

03父親の生き方にヒントを得た「ゆる起業」という概念
最近良く聞く、「ゆる起業」という概念と似ていますね。
実は「ゆる起業」は、僕自身も今から10年前ぐらいから、次はこれが来ると言っていた概念であり、ライフスタイル起業に該当する概念といえます。この「ゆる起業」という概念に私がたどり着いたのは、私の前著『なぜあの人は好きなことだけやって年収1000万円なのか?異端の経営学者と学ぶ「そこそこ起業」』(集英社)の序章のところで書かせていただいたのですが、僕の親父がモデルだったんです。
僕の父親は、いわゆる団塊の世代の生まれです。大工として一人前になって独立したときは高度経済成長期。バブルの時には関西圏で流しの大工をやっていて、結構稼いでいました。一方、父親の同世代の大工さんの多くは、独立した後、好景気の波に乗り会社組織を作って、結構地元では大きな工務店を経営し始めていました。もう皆、ベンツを乗り回していましたね。
ところが、僕の親父の愛車は軽のバンとトラックで、身の周りのことにも無頓着でした。しかし、自分の趣味はすごく大事にしていて、釣りとソフトボールをしっかり楽しみながらマイペースに大工仕事に精を出していました。周りからは、「節税対策も含めて会社を作った方が良い」「弟子も沢山取って工務店にしたらどうだ」と言われていたようです。僕もその件を親父に聞いたことがありました。そのときにポツンと「そんなのは面白くない」と言ったんです。
「自分が社長になったら、現場に出て家を建てる場面がどんどん少なくなる」「従業員を雇い、彼らに給料を払わなければいけなくなるので仕事を選べなくなる」と。大工には、建てていて面白い家と面白くない家、儲かる案件と儲からない案件があります。父親が基本的にやりたいのは、面白くて儲かる家でした。当然ながら、そんな案件はほとんどありません。ならば、どういう案件を受けるか。それが自由に選べるのは一人でやっているからでした。だから、「会社は作らない。社長にもならない」というのが、父親の考えでした。それを改めて思い出したのが、2010年ぐらいですね。
「仕事を自由に選ぶためにも会社は作らない」というのは、強い信念が伝わってきます。
自営業の人は、誰もが会社を大きくして一獲千金でタワーマンションを買うという、IT企業家みたいなキャリアを目指しているのかというと実はそうではないんです。僕が好きなラーメン屋さんも意図的に支店を出したりしません。どんなに行列ができてもお店を大きくしようとしません。支店を作ったら現場から離れて会社経営に専念する場面が増えます。当然、店の規模を大きくしたら、その分だけリスクが増えます。それが面倒だからやらないのです。この世の中には、そうした成長を求めない企業家もいるということです。あくまでも、自分がやりたいこと、好きなこと、あるいは得意なことでそれなりに生活していけたら十分。あるいは家族を支えられたら十分だと。いかに楽しく人生を送れるかを目的として起業している人が少なくないのです。

04ライフスタイル起業が目指すのは、充実した生き方の実現
楽しい人生、自由な人生を送るための起業ですね。
良く良く考えたら、僕のところに「起業したいんです」と相談に来る学生に、その理由を聞くと9割ぐらいは、「会社勤めをしたくない」「もっと自由な生活がしたい」と答えます。
しかし、現在発刊されている起業の教科書やマニュアル本は、基本的に会社を立ち上げて事業計画や財務計画も作り、銀行から融資も受けて会社をどんどん大きくしていき、上場させてキャピタルゲイン(資産を売却して得られる利益)を得ることを前提としたITベンチャー起業家スタイルばかりでした。でも、ほとんどの人が起業に求めていたのは、そこではなかったんです。大きなズレを自覚していました。
そのタイミングでもっと起業は気楽で緩いもので良いのではないかと思って、僕は「ゆる起業の研究をする」と2015年ぐらいから言い始めました。ちょうどそのタイミングで、オセアニア地域の方でもライフスタイルアントレプレナーと言われ始めて、世界レベルの学会も開かれているぐらい注目すべき大きい概念になりつつあることを知りました。
ライフスタイル起業が目指すのは、会社に振り回されず、マイペースに仕事をしながらも生活を楽しむために十分な収入を得る方法を追求することです。その概念を普及させるためにも、どういうふうに彼らが起業するのか、いかに経営しているのか、マニュアル的な知識を探索しながら研究していくというのが、今僕が取り組んでいることです。
『ライフスタイル起業』がなぜオセアニア地域で誕生したのか。その背景を教えてください。
たぶん一つあり得るのが、起業するときの環境が全然欧米や日本とは違っていたということです。
いわゆるITバブルは何だったのかというと、一種のマネーゲームとしての起業でした。起業してベンチャー企業が未公開株を持つと、それを投資の対象と見做して皆で規模を大きくしていこうとします。それが、ITバブルでした。日本だとジャスダック、米国だとナスダックがありますが、ベンチャー企業向けの投資市場が1990年代に出来上がり、ベンチャー企業が持っている未公開株も投資の対象になっていきました。そうすると、そのベンチャー企業が上場したときに一気に株価が上がり、投資家は大きなキャピタルゲインを得ることができます。ある意味、ベンチャー企業を投資対象として夢を膨らましていきながら、企業家が資金獲得を容易にしていく仕組みで出来上がったのが、あのITバブルだったんです。
当然、ITバブルが起こる条件として必要になるのが、ベンチャー企業向けの投資市場です。先行したのは米国、次にヨーロッパ、その後日本でできて、中国のこの10年、20年ぐらいの経済成長も、そのベンチャー企業向けの投資市場が一つの要因でした。
と考えたときに、いわゆる南半球地域は、そういうベンチャー企業向け金融システムの整備が遅れていたというのが、やはり一番大きいと思います。なので、大学とかで勉強して、IT 分野で起業を目指すようなオセアニア地域出身の人たちは語学力を利かして、米国などに移住してしまいます。

05ライフスタイル起業に類する考え方は、どの国でも存在する
それ以外の人たちは、どうするのでしょうか。
残されている人たち、要は国内で生きている人たちはどうするかと言えば、大抵は農業か観光業に従事します。実際、ニュージーランドの主要産業は、6割か7割が農業。その次が観光業なのです。ある意味、国内における起業に関わる金融システムが未整備の状態だったので、残された人たちはそれを前提に低資本で起業するしかありません。しかも、オセアニア地域には経済的にマーケットも小さく、競合相手になる大きな会社もないので、自分たちがいざ独立して自活していこうと思ったときには、手の届く範囲のスモールビジネスで十分になってしまうのだと思います。それで、小規模な会社を安定的に運営しようとしたら、どうなるのかと試行錯誤を繰り返しているうちに、ライフスタイル起業と我々が今呼んでいる経営スタイルになったんだと思います。
これはアセアニア特有かというと、そうではなかったりします。実は日本や米国でも分野を変えていくと、そういう現象があるのがわかります。例えば、米国だと小劇団やアート系で、ライフスタイル起業が結構多いと言われています。なぜかというと、アート系の会社を作ったからといっても、ナスダックで上場できたりしません。要は金融システムの外にあるわけです。しかも、そういう分野で起業する人たちは、自分たちが好き勝手に制作をしたい、作品を作りたいという想いが強く、そのための環境作りの手段として会社を作ります。なので、自分たちが自由にならないような制作環境になってしまうことをとても嫌がります。だからこそ、一つの選択肢として会社の規模を大きくしないというのが出て来ます。あまり大きくすると皆が不幸になってしまいます。要はやりたいことができなくなってしまうからです。
日本でも同様です。先ほどラーメン屋の例を出しましたけれど、外食産業ではライフスタイル起業的な起業スタイルは珍しくありません。しかしながら、最近少しは変わってきたとはいえ、ITやバイオ、製薬などは、依然として上場して大きなキャピタルゲインを得られるような業界です。沢山のお金が流れ込んで来るので、ベンチャー企業を生き残らせようと思ったら、どんどんお金を集めて会社を大きくして、それこそ見せかけでもいいから成長を演出して、いかにマネーゲームを勝ち抜くという経営スタイルがどうしても必要になってきます。
日本でも似たような事例がありますか。
あります。特に、沖縄は顕著です。沖縄は非常に離婚率が高い地域とされています。離婚後、母子家庭になってしまい、お母さんは子供を抱えたまま生活していかねばならなくなります。そうなったときに沖縄の人は、身内が中心となって合計で百万円単位ぐらいのお金を分担して出し合って、そのお母さんのために食堂を作ったりします。そこに皆で食べに行くわけです。地域の食堂であれば、常連さんが10人ぐらいできたら、母子家庭が何とか生活していけるぐらいの稼ぎになりますからね。沖縄の食堂文化は、こういう「ちょっと生活に困ったら、助け合って食堂を出そう」というサイクルが回っているんです。しかも今沖縄では、おばぁの味が食べられるということでこういう食堂が観光名所になっていて、観光資源として捉えられています。これこそが、日本で生じているライフスタイル起業だったりするわけです。まさに、オセアニア地域と似た仕組みだと思います。
もちろん、沖縄の中にも海外や本土から投資を受けて大きいベンチャー企業を作ろうとする企業家もいますが、このように金融システムから外れたところに食堂やダイビングショップ、小さな民宿、今だと民泊のように気軽に起業して、週3日働いたら十分生活できるみたいなライフスタイルを手に入れている人たちが数多くいます。

高橋 勅徳氏
東京都立大学大学院
経営学研究科 准教授
神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了、博士(経営学)。沖縄大学法経学部専任講師(2002‐2003年度)。滋賀大学経済学部准教授(2004‐2008年度)。首都大学東京大学院社会科学研究科准教授(2009年‐2017年度)を経て現職。専攻は企業家研究、ソーシャル・イノベーション論。第4回日本ベンチャー学会清成忠男賞本賞受賞。第17回日本NPO学会賞優秀賞受賞。『ライフスタイル起業~ちょっと働き、ほどよく稼いで、ごきげんに生きる。』(大和書房)、『アナーキー経営学:街中に潜むビジネス感覚』(NHK出版)、『なぜあの人は好きなことだけやって年収1000万円なのか? 異端の経営学者と学ぶ「そこそこ起業」』(集英社)、『婚活戦略 - 商品化する男女と市場の力学』(中央経済社)、『大学教授がマッチングアプリに挑戦してみたら、経営学から経済学、マーケティングまで学べた件について。』(クロスメディアパブリッシング)など著書多数。