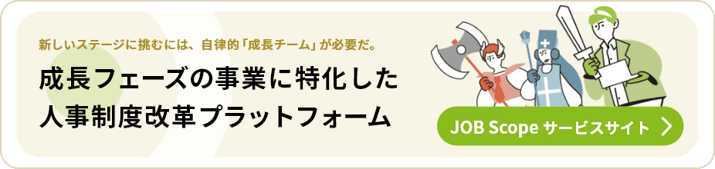人的資本経営がクローズアップされる昨今、日本でも人的資本や情報開示への関心が高まっている。ただ、果たしてどれほどの人がその本質を把握しているのであろうか。「言葉だけが先行しているのではないか」と疑問を呈するのが、30年余に渡り人的資本理論と人間行動の経済学的なアプローチを研究し続けたきた一橋大学大学院経営管理研究科の教授・小野浩氏だ。今こそ、人的資本の意味や人的資本投資の必要性をしっかりと理解すべきだと説いている。インタビューの前編では、小野氏と人的資本理論との出会いや人的資本理論が社会にもたらすインパクトなどを語ってもらった。
目次

0130年もの長きに渡り、人的資本を核とする実証研究に取り組む
2020年9月の「人材版伊藤レポート」の公表以来、人的資本の重要性が大きく高まっています。その背景をお聞かせください。
今は情報開示が日本でも少し浸透してきています。ただし、人的資本経営の背景は、投資家と後は会計学から入ってきているということです。例えば、透明性とかですね。投資家が企業価値を判断する時の材料の一環として、人的資本の開示が必要になってきたと思っています。
改めて、人的資本や人的資本理論とは何かをご説明いただけますか。
私自身は人的資本経営にはほとんど関わっていません。繰り返すようですが、人的資本経営は投資家目線や会計学から入って来ています。経済学者プロパーで人的資本経営を研究してる人はいないでしょう。基本的には、そこら辺りから噛み合っていないところがあります。なので、経済学者に「人的資本経営に対してどのような見解をお持ちですか」と聞いても、回答が上手く返ってこないと思います。
私は、いわゆる人的資本理論を研究している立場です。そもそも、人的資本とは人間の持つ能力、技量、才能、知識、体力などを指していて生産性を高めるものであるわけです。また、人的資本理論とは人的資本に投資すれば生産性が高まり、収益も高まるという考え方です。
しかし、今求められている開示項目は、実は直接的な人的資本の指標ではありません。経済学で言う人的資本は、あくまでも人が有する資本なのです。生産性を高めて収益を上げることができる能力が人的資本となってきます。
小野先生は、どのような経緯で人的資本理論に出会われたのですか。
私自身は元々理系出身です。大学では機械工学を専攻していました。シンクタンクに勤めてからコンサルティング業務を手掛けている中で、「社会科学も面白いな」と好奇心が湧いてきました。それで辿り着いたのが、社会科学研究の世界最高峰である米国シカゴ大学でした。
私がシカゴ大学大学院社会学研究科に留学したのが1992年9月でした。入学して間もない同年10月に同学で教鞭を取られていらしたゲーリー・ベッカー先生が人的資本理論の発展と経済理論を人間行動の分析に応用した功績によって、ノーベル経済学賞を受賞されました。そこから、私も何となくヒューマンキャピタルという言葉に関心を持ち始めたわけです。実際に私がベッカー先生の図書『Human Capital』を手にしたのは1993年でした。それを読んでいるうちに、人間の行動に対して自分がすごく関心があることがわかって来ました。併せて、実は社会科学の中でも数学を使って人間の行動を科学化したり、美しい数式で表現できることがわかり、そこからもう取り憑かれたように人的資本を研究しています。気づいたらもう30年が経過しました。ベッカー先生の弟子になったというのが、人的資本理論を核とした私の実証研究のきっかけです。

02人的資本理論は、世界にさまざまなインパクトをもたらしている
人的資本理論は、社会にどのようなインパクトをもたらすのですか。
人的資本というアイデアは、実は古典派経済学の父と呼ばれるイギリスのアダム・スミスが今から250年近く前に執筆した『国富論』でもうかがえます。当時は、人的資本という表現は使っていません。投資をすれば生産能力と収益性が高まる、人も成長するという理論を体系化して、実証化まで結びつけたのが、ベッカーだったんです。1960年代からぐらいから、ベッカーのコロンビア大学時代での同僚であったジェイコブ・ミンサー教授により実証研究が始まりました。そこからどんどん実証化されていきました。何が理論を強くするかと言えば、やはり実証です。理論を実証することができたら、すごいインパクトが大きいんですよね。それはベッカー自身がよく言っていたことです。どれくらい自分の理論に説明力と予測力があるのかが理論を非常にパワフルにしてくれます。
人的資本に関して言えば、この素晴らしいところは、元々ミクロの理論でしたが、それがマクロで応用できるとわかったことです。ミクロの世界で言うと、例えば大学の収益率が計算できると、個人が大学に行く時の意思決定に役立ちます。大学に行ったらそれなりのコストが掛かるというコストべネフィット(費用対効果)分析をすると収益率がわかり、それがプラスになっているとその大学教育は非常に良い投資であるとわかります。ベネフィットが計量化できるわけです。あくまでも一つの例ではあるものの、これをマクロに応用していくこともできます。例えば、人的資本投資と経済成長の関係もわかります。
国において人的資本投資がGDPに占める比率もマクロ統計で出て来ます。それが経済成長率にどれくらい影響しているかというところも出てくるわけです。マクロの研究であれば、例えば人的資本に投資する国は経済成長率も高いという正の相関が綺麗に出てきます。それ以外にも応用範囲はかなり広いです。例えば人口学とかです。今で言う少子化をどうやって説明するかですね。それから、男女不平等の問題や学歴、家庭、結婚、格差・不平等問題など、色々な応用範囲があります。
例えば、2023年にノーベル経済学賞を受賞したクラウディア・ゴールディン先生も、実はベッカーの弟子です。彼女が男女間の不平等や家族の経済学などの分野で実証研究を行いました。彼女の核となっているのは、人的資本とベッカー理論です。本当に今でもすごく応用範囲が広くて、かつ実証で研究をしており、説明力がかなり高く、世界に色々なインパクトを与えていると思います。
例えばですが、ベッカーの理論は世界銀行でも影響力がありました。その際の試みとして、発展途上国の出生率をどうやって安定させるのか、低くするのかという問題を解決するために人的資本理論を応用しました。要は、女性の教育に投資するんです。そうすると女性の人的資本のストックと市場価値が高まります。市場価値が高まると働くインセンティブが高まり、逆に働かないと女性の機会費用が高くなります。女性の機会費用が高まると出産・育児のインセンティブが低くなります。ですから色々な因果関係を考えると、女性の人的資本に投資すると少子化に結びつくという結論が出てきます。特に発展途上国では、女性のヒューマンキャピタルに投資すべきだということが言えるわけです。(ベッカーは、1995年に出版された世銀のワーキングペーパーで、メキシコの場合、1970年代から1990年代に出生率が半減し、同期間に女性の教育投資が強化されたことと強く相関していると論じている)。

03人的資本への理解を広げたい一心で書籍を執筆
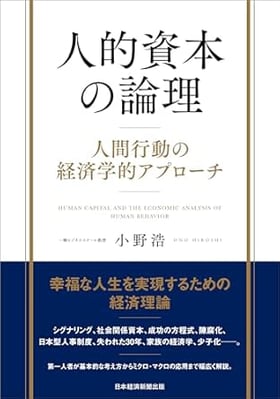
小野先生は、今年4月に「人的資本の論理 人間行動の経済学的アプローチ」を発刊されました。どのような問題意識をもって執筆されたのでしょうか。
色々な背景があって、人的資本理論は今まで経済学の領域に限られていました。経済学者の良くないところでもあるのですが、「経済学理論は一般の人にはわからない」という傲慢さみたいなものがあったと思います。それを私は、この本の前書きにも書きました。私は1992年にシカゴ大学に行った時にたまたまなのですが、ベッカーの理論を知りたくて経済学を専攻している大学院生に「人的資本とはどういう理論なのか」と聞いてみたのです。そうしたら、「経済学を学んだことがない人に人的資本を説明することはできない。私の時間の無駄だ」と言われてしまったのです。
経済学を学んでいる人は合理的なので、そう答えてもおかしくないかもしれません。しかし、「そんなことはない」と思います。人的資本は人に関わる話なので、必ず誰でも馴染めるはずです。それを素人にもわかりやすく説明できないのであれば、説明できない人の方が悪いでしょう。実際、私は大学の教授をしていて、学部生からMBAや博士課程など色々なレベルの学生を教えています。時には、高校で経済学に関して講演することもあります。どんな人でも経済学をわかるように説明できると思っています。なので、人的資本が経済学の範疇に限られてしまうと非常にもったいない話だというのが、私の問題意識の一つです。
また、人的資本経営を語っているのに人たちが、実は人的資本をきちんと理解していません。なので、人的資本についてもう少し理解を深めてもらいたいと考えました。
二つ目は、人的資本に関する本がほとんどなかったことです。実は、書籍化の打診があった時にAmazonで人的資本の分野でどれだけの本が出ているかを調べてみました。人的資本「経営」の本は星の数ほど存在していました。しかし、人的資本そのものに関する本はほとんどありません。唯一あったのは、ベーカーの人的資本理論のオリジナル翻訳本だけです。これは、1976に出版された専門書です。とても読みづらいので、普通の人はまず読みません。なので、人的資本を一般の人にも理解してほしいということで執筆しました。
著書『人的資本の論理 人間行動の経済学的アプローチ』を通じて、小野先生は読者に何を伝えたかったのですか。
私が「人的資本を専門にしています」と言うと、普通の人はもう引いてしまいます。「難しそうですね」と口にしながら…。実際には、それほど難しい話ではありません。誰でもなじめるはずです。例えば、「天才とは何か」とか「努力は必ずしも報われない」とか、そういったことは誰でもわかります。それがわかるのであれば、意思決定ももう少しわかりやすくなると思っています。
私自身は、「人間行動の経済学的アプローチ」というこの本の副題が気に入っています。「人間の行動を説明する時にはこういうフレームワークがあるのか」と、私が本当に1993年にヒューマンキャピタルを読んだ時の喜びを他の人たちにも伝えたいということです。
新刊を読ませていただきましたが、予想以上にわかりやすかったです。難しい計算式もほとんどありませんでした。
その辺りもかなり意識して書いています。微分積分も使わずに二次方程式レベルで説明するようにしました。また、一般的な見解としては経済学は結局、お金の話だと考えている人が多いかもしれません。経済学イコール金融に結びつけてしまいがちです。人的資本の美しさは、経済理論を日常生活に適応したところだと思います。なので、別にお金の話だけではないのです。経済学の原点は合理性です。合理性と言うと、抵抗がある人もいるかもしれませんが、合理的な理論を使うとお金の範疇を離れてものすごく幅広いことが説明できます。
例えば、教育の経済学、労働の経済学、結婚の経済学もありますし、出産や離婚、犯罪など、本当に生活に応用できるような、そういう学問なのです。しかも、ミクロだけではなくてマクロでも説明できるところが、私はこの理論の魅力だと思います。
小野先生の著書「人的資本の論理 人間行動の経済学的アプローチ」

04人的資本理論を知れば幸福を掴むことができる
こちらの書籍の帯には、「幸福な人生を実現するための経済理論」と記されています。意味合いを教えていただけますか。
そこは、合理性に絡んできます。単純に言うと、努力をすれば必ず報われると教え込まれている人が多いと思います。逆に言うと、成果が出ないのは努力が足りないからだと。しかし、人的資本では必ずしもそう考えません。成果が出ないのは、あなたが自分の才能を発見していないからだとも捉えられます。明らかに、どんなに努力してもできないこともあります。例えば、100mを10秒で走れる人はそれほどはいません。中には、努力すれば自分でも10秒台で走れるようになる人もいるかもしれませんが、普通の体格の人ではあり得ないことです。努力とは全く関係ないところで決まってしまっています。そうしたことは、結構人生においてあるものです。その辺りをどうやって見極めるかによって幸福をつかむことができるわけです。
だから、自分が非現実的な目標を定めてしまい、努力すれば何とか達成できると思い続けることは、僕からしてみれば非合理的であり、不幸な人生です。むしろ、自分の適性を見つけて自分が伸びる方に軌道修正することが大事なのです。そうしたロジックが帯には込められています。
例を挙げると、テニス選手のロジャー・フェデラーや作曲家のモーツァルトは、自分の才能を発見して大きな成果を収めた人たちです。他にも作曲家のチャイコフスキーもロックシンガーのミック・ジャガーもそうです。彼らは、ものすごくハッピーだったわけです。自分の才能を発見して、それでもう本当に歴史に残るぐらいの成績を残したわけですから。しかし、皆が皆そうなるわけではありません。自分の才能を発掘して、それが成果に結びついた時に真の幸せをつかめると思っています。
小野先生は、最近では幸福学も研究されておられます。どのような経緯があったのでしょうか。
これも、私自身で社会学と経済学を勉強していて、やはり社会科学の中では色々流行するアプローチがあるわけです。社会学と経済学、経済学と心理学、心理学と社会学を合わせるとか…。2000年代に入って私は経済学にどっぷりはまっていたのですが、お金の話ばかりしていて、非常に偏りがあると感じてしまいました。ちょうどその時ぐらいから出て来たのが、幸福度が計量化できるという研究でした。
統計学では説明変数(何かの原因となっている変数)と被説明変数(結果となる数値)があります。右辺と左辺です。説明変数には、例えばジェンダーや年齢、勤務形態などが来ます。左側には被説明変数として今までは賃金を見ていました。しかし、実は被説明変数に幸福度を入れるだけで、同じような仕組みのモデルになります。すべてが一致するわけではないのですが、賃金と幸福度の決定要因には似たようなところがあるのです。その辺りから、お金と幸福度の関係にすごく関心が出てきて、「家庭内分業と結婚の幸福度」について論文を書きました。男女間で仕事をしているかどうか、誰が家にいて誰が仕事をしているか、そうしたミックスのなかで今までは賃金にどう影響するかという話でした。それを、幸福度にどう影響するかという観点から見ると賃金と幸福度の決定要因の共通点と相違点がいろいろと見えてくるのです。
実は、2000年代にまだベッカー先生が生きている時に、当時ストックホルムに住んでいた私は何回かシカゴに行く機会がありました。それでベッカー先生と良く会いました。ベッカー先生自身は、理論的に幸福度を使ってはいたものの、それまで実証研究で幸福度を見たことはありませんでした。そこで、「ベッカー理論を使って幸福度を見てみたいがどうだろうか」と尋ねてみたところ、「それはぜひやるべきだ」と言っていただき、非常に面白いディスカッションができました。
それで、彼の例えば家庭内分業の理論を使って、それで被説明変数を幸福度として捉えベッカー理論が幸福度とどう関係があるかという検討に着手し始めた。それが出発点です。

小野 浩氏
一橋大学大学院
経営管理研究科
国際企業戦略専攻 教授
早稲田大学理工学部卒。野村総合研究所コンサルタントを経て、シカゴ大学大学院社会学研究科博士課程修了、Ph.D取得。ストックホルム商科大学准教授、テキサス A&M 大学准教授を経て2014年より現職。 2017年スタンフォード大学客員教授。現在、テキサス A&M 大学特任教授も務める。専門は人材マネジメント、人的資本理論、幸福度、統計学。著書に『人的資本の論理 人間行動の経済学的アプローチ』(日本経済新聞出版)などがある。