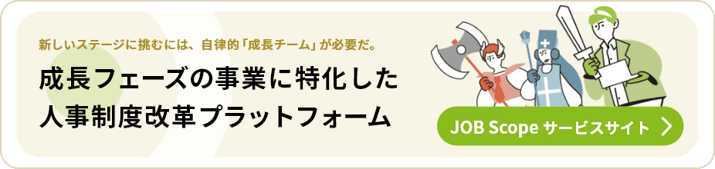これからは、人と組織の時代。チームワークが経営レベルで求められている(前編)
劇的なスピード感で、しかもダイナミックに変わりゆく現代社会。もはや、未来は見通せず不確実となっている。その状況下で、いかに人と組織のパフォーマンスを最大化させていくか。経営者や人事マネジャーの悩みは尽きない。そうした課題を解決するためにも、「人とチームのブレイクスルーを科学する」をテーマに、人的資源管理論・組織行動論の立場から実証的な研究に取り組んでいるのが、立教大学 経営学部 ╱ 大学院経営学研究科 准教授の田中 聡氏だ。経営人材の育成、チームワーク、人事パーソンの学びとキャリアなどに関する専門家としても広く知られている。その田中氏にインタビューの前編では、リーダーシップのスタイルにおける変化や経営人材に求められる経験特性などを聞いた。
目次

01社会的な運動として一定の影響力を持つに至った人的資本経営
日本においては、人的資本経営がバズワード化しています。この状況をどう捉えておられますか。
さまざまなメディアで、多くの経営学者、特に人的資源管理論の研究者らが「人的資本経営のバズワード化」という現象に対して否定的な見解を述べておられます。私の考えもそれらと大きく変わるものではありません。学術的な視点から見ると、既存の概念、あるいは伝統的な日本企業の中にビルトインされていた思想と根本的に何が違うのかと言われると、そこに関してはクエスチョンマークが立つというのが正直なところです。ただ、それで終わらせてもあまり面白くありません。
一つ今回のムーブメントの特徴として私が感じるのは、今回の動きは、いわゆる人事の内側から出てきた声ではなく、ファイナンスの観点、つまりCFO(最高財務責任者)という立場で、人という資本をどう扱っていくのかという問題意識から生まれた社会的な運動だという点です。もっと言えば、株主・投資家の立場から中長期的な企業価値を評価する上で、無形資産である「人材」の情報開示にかつてないほど関心が寄せられているということです。これはメディアによって作り出された一過性のブームとは、質的に異なる社会的な運動だと私は見ています。
具体的な中身がどれだけ新しさを伴う内容であるかはさておき、ここまで社会的に人材の重要性が認知されたというのは、恐らく日本の歴史上初めてのことだと思います。確かに人本主義経営(人が企業経営の根幹を成すと考える経営スタイル)に代表されるように、高度経済成長期以降、これまでも繰り返し日本企業の特徴として「人を大事にする経営」が指摘されてきました。しかし、ここまで社会的な運動として根付いたことはありませんでした。そのような歴史的経緯をやや批判的に捉えると、今回の社会的認知の広がりによって、かつてより喧伝されてきた「人を大事にする経営」がいかにお題目に過ぎなかったのかが露わになったとも言えます。
より具体的にいえば、「人を大事にする経営」の意味合いが、以前と今とでは大きく変わってきたのだと思います。これまでの「人を大事にする」とは、端的にいえば「雇用を守ること」と同義でした。社員の雇用を守るという観点で、日本企業が人を大事にする経営を実践してきたことは紛れも無い事実でしょう。しかし、近年では、経団連元会長やトヨタ自動車元社長らが「終身雇用を守ることは難しい」といった発言をしたことが話題になりました。もはや、一つの会社が社員の雇用を定年まで面倒見るという時代ではありません。いま人的資本経営という文脈で言われている「人を大事にする経営」とは、会社側が責任を持って一度雇用した社員を定年まで雇い続けるということではなく、従業員一人ひとりをきちんと資本として見立てて投資をしていくところに本質があります。
人への投資というと、日本企業にはOJTという伝統的なお家芸があり、以前より社員教育には積極的であったという指摘もあるでしょう。しかし、OJTは決して計画的・戦略的に行われてきた育成手法でも教育プログラムでもありません。むしろ、さまざまな条件が重なり合い、予期しない形で生まれた、いわば偶発性の産物です。つまり、ビジネス環境の変化が比較的緩やかで求められる知識やスキルが、短期的には大きく変わらないという前提の下で、同質的かつ固定的なメンバーのみで構成される職場で、新人は先輩の背中を見ながら学ぶことができ、数年後には同じような仕事ができるように熟達していくという仕組みです。このような認知的徒弟制と言われる仕組みのもとで、人が「結果的に育っていた」わけです。
そのOJTが今機能不全を起こしているのは、色々な政府統計データを見ても明らかです。そもそも数年先のビジネス環境を見通すことすら難しい状況のなか、知識やスキルの陳腐化も急速に進んでいます。また、働き方の変化や雇用の流動性が高まったことで、職場メンバーの顔ぶれも以前と比べてずいぶん多様になりました。このように、日本企業のOJTを支えてきた諸条件が成立しづらくなっているわけですから、いわば当然の帰結です。
こう考えてみると、はたして日本企業が人への投資に積極的だったのか、人を戦略的・計画的に育成してきたのか、という問いに自信を持って「イエス」と答えられるかは甚だ疑問です。ですから、過去への回帰ではなく、未来への進化という意味で「人を大事にする経営」が、今注目を集めて語られているのだと私は思います。
いずれにせよ、人的資本経営がこれほど大きな社会的な運動として日本社会に一定の影響力を持つに至ったことについては揺るぎない事実だと思います。繰り返しになりますが、人的資本経営はもはやブームではないと思います。もう、そのフェーズは抜けたという印象です。
人的資本開示への動きも加速しています。
はい、今行われている人的資本経営の議論は、基本的には情報開示についてだと思います。特に、上場企業だともう法律で義務化されてしまっていますからね。ただ、人的資本開示が、職場の改善になかなか至っていないという問題意識を私は強く持っています。現場の問題として人にきちんと投資をする会社になっていかないと、そこにはお金が集まってこないという切迫した状況の中で、今物事が進もうとしていること自体はポジティブです。そこまではポジティブなのですが、多くの会社が今ある数字でどういうふうに綺麗に見せようかという論点に固執し、本質的に重要な職場をどう改善するかについてまで議論が進んでいないのは、すごく残念な気がします。人は職場で育ちます。ですから、人が育つ職場の改善が1丁目一番地の課題だと思っているので、そこにきちんと今の人的資本経営の取り組みが寄与しているのかは丁寧に検証する必要があるでしょう。ただ、間違いなく時間は掛かりますから,短期的に成果を求めない姿勢も重要です。

02社会システムを変えない限り、部分的なジョブ型移行に留まる。
ジョブ型雇用に関しては、どのような見解をお持ちですか。
ジョブ型は、恐らく有識者によってかなり見解がわかれると思います。個人的には、これが良いか悪いかという議論は会社によって異なるので、総論として良いとか悪いとかの判断はできないという意見です。さらにいえば、このジョブ型雇用は一企業の雇用制度という枠組みを超えて、一種の社会的なシステムとしての性格を持つ非常に広い概念だと私は理解しています。だから、そもそも一企業単体で本当に抜本的に変えられるのかといった疑問を持っています。
つまり,実際にジョブ型雇用が根付くには、個々の会社が持っているOSやカルチャーもそうですが、もっと言うと日本的雇用みたいなもの、言い換えれば社会全体のOSを変えていかないとなかなか難しいと思います。具体的には、報酬の仕組みを一つ取ってみても、今は一つの会社のなかでの役職によって決まっています。例えば、営業の課長が総務の課長に異動しても、ほぼ同じ給料で横滑りできます。このように、部署が違っても基本的には役職によって給料が決まる仕組みなので、部署を超えたローテーション人事が行えているわけです。けれど、ジョブ型雇用の前提は職務の価値やその給与水準はそれぞれのポスト(部署×役職)ごとの市場価格によって決まるという考え方です。
では、そのようなサラリーマーケットが日本の労働市場にあるのかといえば、それは海外と比べるとありません。そういった意味では、どうしても部分的なジョブ型の移行にならざるを得ません。
ジョブ型雇用は今後、日本企業に広がっていくとお考えですか。
いわゆる世の中的に言われるジョブ型雇用は、恐らく今後日本の大企業を中心に広まっていくと思います。ただ、中小・中堅企業はスタンスがきちんとわかれていくことでしょう。グローバルマーケットでビジネスを展開して、外国人雇用者も一定数採用したり、あるいは競合が外資系の企業になるような中小・中堅と、ローカルマーケットの中で、基本的には今後も日本語を中心に日本人を対象としたビジネスを展開していく会社では、取り得る雇用システムは違うと思います。後者の場合、従来からのメンバーシップ型からジョブ型に移行するインセンティブはありません。
先程、私は社会システムと申し上げましたが、例えば本当にジョブ(職務)を中心に企業と従業員が結ばれている関係性を考えていけば、我々のような大学の教育システム自体も大きく変わっていかないといけません。程度の問題はありますが、今まで以上に経営管理やファイナンス、マーケティング、人事などそれぞれのジョブに必要とされる高度に専門的な知識やスキルを習得できる教育システムにカリキュラムを抜本的に変えていく必要があります。このように企業だけでなく大学教育も含めた社会システムのOSがアップデートされない限り、本当の意味でのジョブ型雇用シフトは実現できないと考えています。

03未来が予知できない状況だからこそ、全員発揮型リーダーシップを
VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性という4つの言葉の頭文字をとった造語)の時代と言われて久しい現代、リーダーシップのスタイルは変わって来ていますか。そうであるとしたら、どのように変わってきているのでしょうか。
明確に変わって来ていると思います。いま私が教えている立教大学経営学部の中には、学部創設以来、リーダーシップ教育に力を入れています。そのなかで一貫して大事にしている考え方が「全員発揮型リーダーシップ」というものです。立場や権限、役職に関わらず、そのチームに参画する全てのメンバーが、チームの目標達成に向けて主体的に取り組む行動や他者に及ぼす影響力、これをリーダーシップとして捉えようという考え方です。その対局にあるのが、職場の中の長が権限や立場、役割に基づいて発揮するものがリーダーシップであるという捉え方です。
従来の作れば売れる時代には顧客が共通して抱える課題というものが明確に存在していました。ある程度この戦略でここに投資をすればリターンを見込めるとか、数年先の会社の状態が読めるとか、そういうものが決まっていて何をやれば良いかも予見できる時代です。その時代に求められるリーダーシップとは、「権限を発動して集団を率いるトップダウン型のマネジメント」とほぼ同義でした。
しかし、これだけ不確実性が高い時代になると、いくら優秀な経営層やミドルマネージャーといえども、本当に会社の10年先を見据えて、何がこれから来るのかを明確に予知できているリーダーはいないと思います。みんな答えがわからない中で迷っているし、悩んでいます。そうした中で一部の経営リーダーたちだけに従来型のリーダーシップ像を求めるのはあまりにも無理があります。ですから、ごく自然に考えて、先ほど申し上げたような「全員発揮型リーダーシップ」が求められているわけです。メンバー一人ひとりが職場が掲げる目標をしっかり見据えた上で自分にできる貢献は何かを考え、自分らしいアクションを起こしていく、そういうリーダーシップが今求められているということです。
デジタル化、DXが進む中、人や組織の役割にも変化が見られますか。
はい。より長い時間軸で時代の流れを捉えると、工業化社会から知識基盤社会(新たな知の創造・継承・活用が社会の発展の基盤となる社会)にシフトする中で、これまでの価値創造や競争優位性の源泉がモノやカネから「人やチーム」に変わってきているということだと思います。さらに言えば、人やチームが生み出す創造性こそがイノベーションに繋がり、会社の経営を動かしていくキードライバーだというふうに社会全体の見方が変わってきているように感じます。

04経営人材の育成に役立つ
5つの経験特性とは
田中先生は『経営人材育成論』(東京大学出版会)、『事業を創る人の大研究』(クロスメディアパブリッシング)などの本を執筆されています。経営人材育成において、大切な経験特性を教えていただけますか。
それについては、1990年代後半に米国のリーダーシップ専門教育・研究機関であるCCL(Center for Creative Leadership)の研究者であるシンシア・D・マッコーレイ氏らが提唱した「発達的挑戦課題」と称した5つの経験特性が当てはまると思います。まず端的に言うと、経営人材は放っておいて勝手に生まれるものではないのです。それから経営塾に参加したり、MBA(経営学修士)を取ったらすぐに経営人材になれるというものでもありません。要するに、必要な実務経験を踏まないといけないのです。具体的にそれはどういうことなのかというと、5つの特徴があると言われています。
1.「ジョブ・トランジッション」(異動)
本人がこれまで経験したことがない、全く新しい領域に異動し勉強させることです。
2.「高度な責任」
例えば、子会社の経営を任せるなど、これまでに担ったことがないような責任の重い仕事を経験させることです。
3.「権限がない中での影響力」
これは、二つ目と矛盾するように聞こえるかもしれませんが、責任は重いもののそれに比した権限が与えられていない、そういうジレンマの状況下の中でチームを作っていくことです。
4.「障害」
山積する課題に対処していく、課題を解決していく経験。トラブルシューティングを経験させることです。
5.「変化の創造」
不確実な環境下で変化を生み出す経験をさせることです。しかも、斜陽な業界ではなく、自らの手で新しい変化を生み出す余地がある分野で経験を積むのが良いでしょう。
つまりは、不慣れな仕事環境に異動して、そこでこれまでよりも責任が重い仕事を背負うものの、権限は与えられていない状況の中で、いかにステークホルダーを巻き込みながらチームを作って課題を解決していき、変化を生み出していくか。そういう環境での経験をいかに積み重ねていくか。しかも、それが若いうちから計画的・戦略的に積み重ねさせられるような状況に身を置くことが、経営人材になるためには非常に重要になってきます。ちなみに、先程ご提示した5つの経験特性の詳細は、私が執筆した『経営人材育成論』(東京大学出版会)をご覧ください。
『経営人材育成論』(東京大学出版会)

05構造的な問題があるがゆえに、経営人材の育成が進まない
日本企業における経営人材の育成は、上手く進んでいるのでしょうか。そうでないとしたら課題は、どこにあるとお考えですか。
企業の人事の方たちに、「御社の組織課題は何ですか」と尋ねたら、恐らく1位か2位に入ってくるのが、「次世代経営人材の育成」だと思います。これは、昨日今日に始まったら話ではありません。長らく変わっていないのです。もう10年、20年単位で同じような傾向が続いています。にもかかわらず、状況が何も変わっていないというのは、そもそも十分に取り組んでいないか、取り組みの仕方に問題があるのか、はたまた取り組んではいるもののまだ効果が表にあらわれていないだけなのか、という3つが考えられます。
経営人材育成も先ほどの人的資本経営と同じように、今の20代若手社員に対して戦略的・計画的に投資をしようと色々と仕組みを変えて試したとしても、それが実を結ぶまでには最低でも20-30年ぐらいの時間が掛かります。その人が経営者になって本当に会社のパフォーマンスが上がるかどうかを評価しようとすれば、さらに時間は必要です。それだけに、今日の経営人材育成が上手くいっているのか、いないのかを評価するのは現実的に難しいと言わざるを得ません。
そうした「人材育成の遅効性」という問題がとくに経営人材育成には顕著であることを踏まえた上で、取り組み上の課題に言及すると、まず挙げられるのが構造的な問題として経営人材の在職期間が短すぎます。そもそも経営人材の在職期間がわずか3、4年程度であったりします。神戸大学大学院経営学研究科の三品和弘教授の言葉を借りれば、まさに「短命社長から短命社長へのバケツリレー」をやっているようなものです。そういう構造の中にあって、経営者が在職期間中に自分の任期を全うしたその先の10年、20年をロングスパンで考えて、今手を打たなければならない意思決定や被らないといけない痛みに対して、どれだけ本腰を入れて取り組めるかということです。要は、「在職期間中は何もなく無事に終えたい」というインセンティブが働きやすい構造になっているわけです。これは、逆の側面から見ると、誰が経営者になったとしても会社全体に与えるインパクトは、それほど大きくはなかったということでもあります。
このような構造的な問題が、経営人材育成に対するコミットメントを低下させる一因になり,経営人材の育成がなかなか進みにくいのではないかと思っています。もちろん、最近では選抜人材のタレントプール化や早期抜擢の仕組みを取り入れるなど、それぞれの会社が色々な試みをされています。それらは今後評価を待てば良いと思いますが、現時点での一番大きなネックは、そういう構造的な問題があるということです。

田中 聡氏
立教大学 経営学部 /大学院経営学研究科 准教授
1983年 山口県周南市生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程 修了。東京大学・博士(学際情報学)。慶應義塾大学商学部卒業後、株式会社インテリジェンス(現・パーソルキャリア株式会社)に入社。大手総合商社とのジョイントベンチャーに出向して事業部門を経験した後、人と組織に関する調査研究・コンサルティング事業を専門とする株式会社インテリジェンスHITO総合研究所(現・株式会社パーソル総合研究所)の立ち上げに参画。同社リサーチ室長・主任研究員・フェローなどを務め、2018年より現職。専門は人的資源管理論・組織行動論。人材開発・チーム開発について研究している。著書に『経営人材育成論』(東京大学出版会)、『チームワーキング』(共著:日本能率協会マネジメントセンター)、『「事業を創る人」の大研究』(共著:クロスメディア・パブリッシング)など。