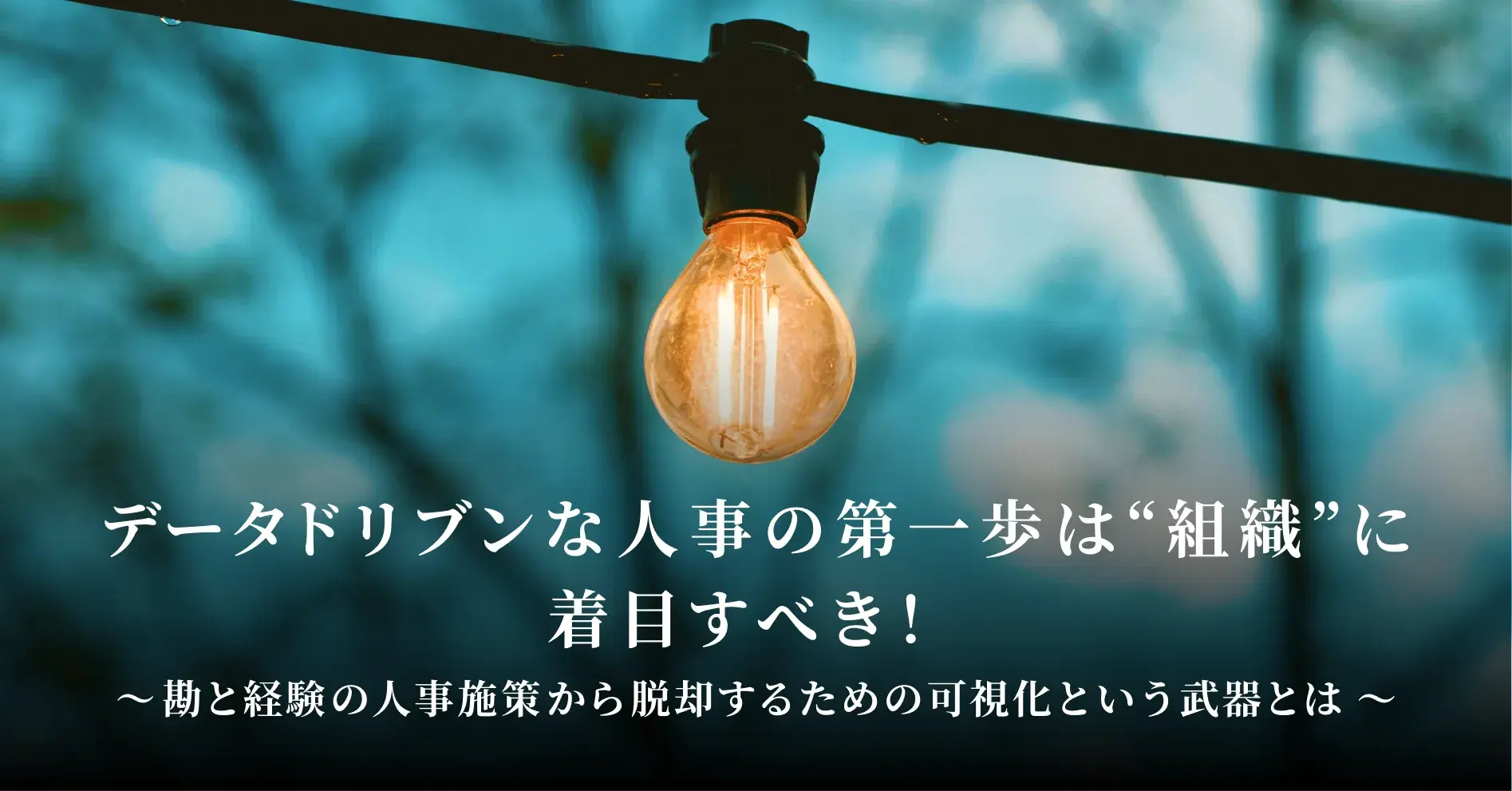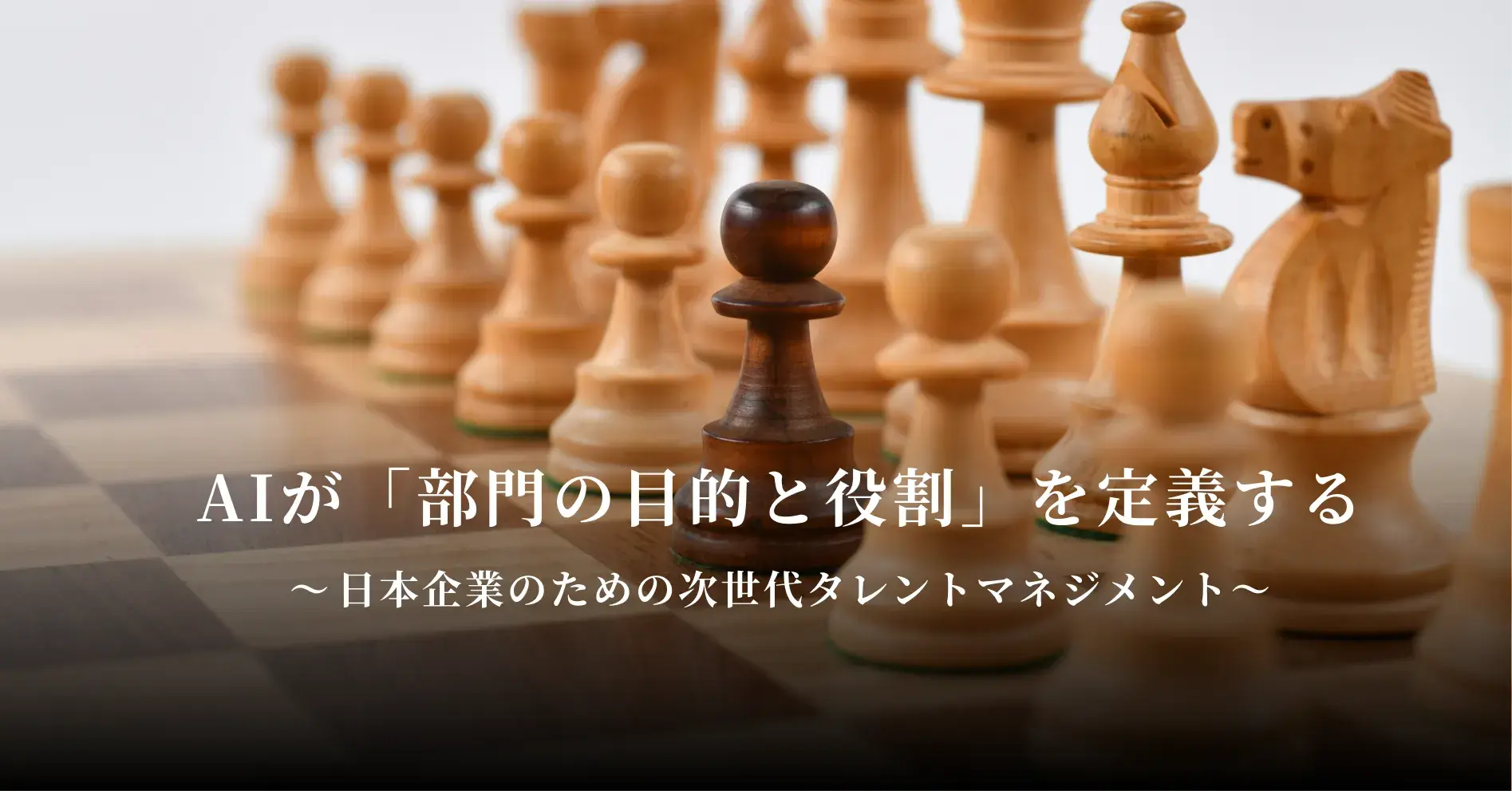第20回
「離職は本人意思に任すしかない」と諦めていませんか?
~AIを活用したサーベイなら、退職意向の芽を早期に摘むことができる~
2025/11/21
「働き方改革」「年功序列制度の崩壊」など、従来型日本企業の働き方の変化を挙げると、枚挙に暇がありません。
それら変化を象徴する現象の一つは、社員の流動化、平たく述べると「社員の離職増加」でしょう。
従来のように、「新卒で入社した会社で定年まで働く」という価値観は、昨今ではもはや当たり前ではありません。
ただし、社員流動化の過渡期にある日本企業のビジネスパーソンは「辞めてしまうのは、今の会社に申し訳ない」というような忠誠心を持つ方も一定数います。
つまり退職意向が芽生えて、すぐに退職をするような行動に移す社員は、日本企業にはそれほど多くないと考えられます。
多くの場合「もし今の会社でこの点が改善されたなら・・・・・・」と、今の会社に残る可能性を模索するでしょう。
このような、離職意向が芽生えたとしても、自社に残る道が残されている段階を察知することが、離職防止には重要です。
今回の記事では、そのようなビジネスパーソンの揺れ動く退職意向の芽を、いかに早期発見するかというヒントをお知らせします。
離職をめぐる構造変化 ~なぜ辞める人が増えているのか?~
経済環境が目まぐるしく変わる状況であっても、人(社員)を礎にしている「企業」にとっては、構成員である社員離職は常に関心事項であるでしょう。
離職率は年々微増傾向にあり、厚生労働省の「雇用動向調査」では、令和5年度の年間離職率が15.4%と、前年より0.4ポイント上昇しています。
昨今の傾向としては、若年層や中堅層の離職が顕著に増加している点です。
背景には、企業におけるジョブ型人事制度の導入、副業やフリーランスといった柔軟な働き方の浸透、そしてキャリアの自己決定志向の高まりが考えられます。
「安定」よりも「成長」や「自律性」を重視する傾向は、ミレニアル世代以降の特徴としてよく指摘されます。
企業が長期雇用や年功序列を前提としたマネジメントを続ける限り、この価値観のミスマッチは解消されず、離職リスクの高まりへと直結するのです。
加えて、ポストコロナ時代の働き方改革やハイブリッドワークの進行により、社員の心理的距離感が変化していることも見逃せません。
「職場の人間関係」や「上司との関係性」を起点とする離職も、従来よりも表面化しにくくなっています。
こうした構造的変化を前提に、企業は「人が辞める理由」を根本から再定義する必要があるでしょう。
離職に関する心理的要因を紐解く
離職に関しては、新卒の「3年3割離職」のような、やや流行り言葉に踊らされている状況もあります。
ただし、本質的に社員離職を考えるためには、「なぜ社員が離職を決めるのか」という心理的なプロセスに注目する必要があります。
本章では、組織心理学や人材マネジメント領域で広く知られている理論をいくつか紹介します。
まず代表的なのが、ハーバード大学のモビリティ研究者エベレット・リーが提唱した「離職のプッシュ・プル理論(Push-Pull Theory)」です。
この理論では、離職を促進する「プッシュ要因(不満・職場環境・ストレス)」と、外部からの「プル要因(より良い条件・転職の誘い)」の相互作用が離職の決断に影響を与えるとされます。
ややマーケティング寄りの考え方ではありますが、人は「ここがイヤだ(プッシュ要因)」と「もっと良くなる(プル要因)」とのせめぎあいの中で転職を決めるのです。
従って、マネジメントがこのようなせめぎあいの機微をどこまで捉えられるかは、今後の離職防止の重要ポイントといえるでしょう。
さらに近年注目されているのが、クレーマーらによる「ジョブ・エンゲージメント」理論です。
これは社員が仕事に対してどれだけ没頭し、エネルギーを注いでいるかを測るもので、高いエンゲージメントは離職リスクを大きく低減する要因であると、多くの研究で実証されています。
これらの理論は、単に「辞めた理由」を後追いするだけでなく、離職に至るまでの兆候や心理的揺らぎを読み解くための、重要な視座を与えてくれます。
いずれにしても「この会社を辞めよう」という決意に至る社員の心理的メカニズムには、一定の法則があるはずです。
その予兆をいかに把握できるかどうかが、離職防止のキーとなるのは間違いないでしょう。
現場でよくある「離職の前兆」—現場が見逃しがちな3つの兆候
前章のような理論的なフレームワークに加えて、実務の現場では「なんとなく様子が変だ」「最近やる気がなさそう」といった違和感を察知する必要があります。
いわゆる‟肌感覚”と呼ばれる領域かもしれませんが、よくあるケースを知っておくことで、離職サインへの察知力が研ぎ澄まされるかもしれません。
本章では、よくある離職前の兆候を3つのケースで整理してみましょう。
| ケース1:無言の定時退社が増える |
|
ある新入社員は、入社後から残業や他部門のサポートも快く引き受けていた。 ですが、ここ数か月は定時になるとそっと席を立つような姿が目に付くように。
定時なのでマネジメントも何も言わなかったものの、以前は「帰ろうと思いますが、何かできることはないですか?」と聞いていたのに、それもなくなったことは認識していた。
その後、その社員は3年目を迎える前に突然の退職に至ってしまった。 理由を尋ねると「入社直後は何でも自分の成長につながっていると感じていたが、3年目以降のキャリアがぼやけてきた」と語っていたそうだ。
マネジメントは「もっと本人のキャリア志向を会話すべきだった」と、肩を落とすしかなかった。 |
| ケース2:社内チャットでの発言数が減少 |
|
これまで活発にコミュニケーションをとっていた、中堅の営業社員。
オンライン営業下であっても、積極的に社内外にコンタクトをして、モチベーションは保たれている様子だった。
一方、チャットツールではコンタクト数の可視化もできるため、少しずつやり取りが少なくなる状況も見受けられた。
結果、その社員はリアルなやり取りを求めていて、その不全感を誰にも相談できないまま退職に至ってしまった。
仕事ぶりに表立った変化はなかったため、いわゆる「見えない退職準備」の典型的な兆候だったと後にわかった。 |
| ケース3:業務に対する興味・関心の変化 |
|
長年エンジニア職として貢献していた中堅社員。
地道に会社に貢献することをモットーとしていたが、昨今はAIの台頭により自分の業務が置き換わることを恐れていた。
そこで新しいプログラミングのスクールに通い始めたところ、もっとチャレンジのしがいがある業務に挑戦したくなった。
社内ではそのチャレンジが叶いそうにないため、転職エージェントからのスカウトで、別の会社に転職することを決めてしまった。
本当は社内でも新しいITプロジェクトが立ち上がり、その社員の活躍を広げる場はあったにもかかわらず、会社は大きな戦力を失うこととなった。 |
こうした事例に共通するのは、「周囲が気づいた時には、すでに本人の意思は固まっている」点です。
つまり、離職の“予兆”は極めて早い段階から始まっている可能性があるといえるでしょう。
なぜ離職を防げなかったのか? 組織側の盲点
前章で紹介したようなケースが発生した際、組織側は「もっと早く気づけていれば……」と悔やむことが多いでしょう。
しかし、なぜ早期発見が難しいのか。ここにいくつかの盲点があります。
本章では本来は組織側で注意すべき点であるのに、手薄になっている盲点を3つ紹介します。
マネジャーの主観偏重
マネジメントやリーダーシップ研修を受けたとしても、結局マネジャーも「人間」なので、メンバーを眺める際に、主観は排除しきれません。
さらに人間には、ものごとを自分に都合の良い方向に考える「確証バイアス」という認知傾向もあります。
そのため、メンバーのため息を「仕事に真剣に取り組んでいるからだろう」や「気のせいだろう」と、マネジャーは自分の主観で判断してしまいます。
メンバーの様子を“感覚”で把握しているのみで、具体的な変化の記録がされていない場合、判断はどうしても遅れがちになります。
心理的安全性の欠如
社員が本音を言いにくい風土では、不満や不安が表出しにくい状態といえます。
初めはちょっとした不満であっても、内在化して蓄積されていくと、ストレスへと変化していきます。
いわゆる「ガス抜きができない」状態です。
そうなると、ある日何かのきっかけで社員は自身のストレスを実感し、「もっと伸び伸びと働ける会社を探したい」と、顕在化した退職意向へと発芽していく傾向にあるでしょう。
タイミングの逸失
マネジメントのフォローが効果を発揮するのは、退職意向が芽生え始めた初期です。
もう社員本人が「辞める決意を固めた」時点で気がつき、引き留めをしたとしても、ほぼ結果は覆らないでしょう。
1on1面談は最近実施率が増えたとはいえ、まだまだ日本企業全体では、実施している企業は少ない状況です。
そのため、日常的に蓄積されていくメンバーのネガティブ感情を捉えるタイミングを逸してしまうケースは少なくありません。
さらにリモートワークが普及したことで、メンバーの顔色やちょっとした様子の変化に気がつきにくい環境変化も影響しています。
こうした盲点に気づくには、やはり「感覚ではなく、構造的に可視化されたデータ」が必要でしょう。
離職予兆を“可視化”するサーベイの重要性
前章で述べた「マネジャーの主観偏重」「心理的安全性の欠如」「タイミングの逸失」を解消するためには、予兆を察知するためのサーベイが効果的です。
サーベイによる可視化があれば、前章の3つの盲点が以下のように補われます。
・マネジャーが主観で見ているメンバーを客観データで補完でき
・定期的に意見を吸い上げることで心理的安全性が保ちやすく
・離職意向が芽生えたタイミングを逸しない
このような効果が期待できるからです。
サーベイの質問内容としては、社員の働きがいや職場満足度、心理的安全性、キャリア展望などが一般的です。
これらを定量的・網羅的に把握できるサーベイ調査は、離職リスクを見える化する仕組みとして多くの企業に導入されています。
とくに「時系列」でのスコア変化を見ることで、個人単位での離職予兆を検知しやすくなります。
たとえば「キャリア展望」スコアが2回連続で低下している社員がいれば、将来的に転職を視野に入れている可能性があると判断できます。
また、部署やチームごとのスコア傾向を比較することで、離職者が集中している職場のマネジメント課題を抽出することもできます。
これにより、対策の優先順位を戦略的に設計できるのです。
生成AIなら社員の淡い退職サインを察知できる
日本におけるESやエンゲージメントサーベイは、2000年代初頭から徐々に広がり、特に、2010年代に入ると、働き方改革やダイバーシティ推進などの影響を受け、多くの企業に導入が進みつつあります。
一方で、欧米企業のように「サーベイ実施が当たり前」にならないのは、日本人の国民性にも起因しているかもしれません。
自分の本音、ましてや退職意向というセンシティブなテーマについて、奥ゆかしくて慎重な傾向がある日本のビジネスパーソンは、たとえサーベイであっても回答に抵抗があるでしょう。
そこで注目されているのが、最新の生成AIの技術で「普通のコミュニケーションの延長線上で、社員の本音を引き出す」サーベイです。
従来型のサーベイでは、社員の状況や気持ちに合わせた項目設計ができません。
しかしAIであれば「今日の調子はどうですか?」と日常的な会話をきっかけにし、その回答に応じた社員のメンタルや心理的状態に合わせて、次の質問を自動生成してくれます。
その上、データは定量化されるため「これまで毎回仕事に前向きな回答をしていた社員」が「数回に1回は、不全感を示す回答を始めた」と、軽微な気持ちの変化を可視化することも可能でしょう。
まさに社員自身も気付いていないかもしれない、気持ちの不全感の初期段階を発見できるのです。
|
生成AIによって社員の初期の離職意向を察知し、 社員が定着しやすい職場に! |
|
・JOB Scopeは、エンゲージメントを可視化する『生成AIワークバリュー・スコア分析』をリリース
・従来型の画一的なサーベイ設計ではなく、社員個々人の立場や心情に寄り添いながら、社員のコンディション把握が可能
・離職防止はもちろんのこと、定期的かつ自然に自分の感情を表出することで、社員自身のメンタルマネジメントにも効果あり
▶▶『生成AIワークバリュー・スコア分析』の詳細はこちらをご覧ください |
※当連載では、なぜ現代マーケットで生成AIによるエンゲージメント把握が有効なのかについて、シリーズ記事でお伝えしていきます。
従来型のサーベイでは限界を感じている経営・人事部門の方は、ぜひ引き続き今後も記事をお読みください。
まとめ:社員の“じわじわ離職”をいかに防止できるか
今回はどのような企業でも無視できない、「社員の離職をどう食い止めるか」というテーマに向き合いました。
「社員の定着率を上げたい」という意向は、どこの企業でも異論はないはずです。
ですが、結局本人の意思に任せきりにして、外部からの手立ては限界があると思い込み、自然に任せている企業も一定数は存在します。
本来は慰留できたにもかかわらず、フォローの手がないことで、本人の中でじわじわとした退職意向の輪郭が、徐々にクリアになってしまっていくのです。
このような“じわじわ離職”は、意図を持って取り組まないと、解決にはつながりません。
実は、社員離職による穴埋めへのコストは少なくはありません。
一般的に、募集コストや教育コストを含めると、採用したい年収額の半分程度が発生するのが常です。
例えば年収500万円の社員が辞めたら、新規採用には平均して250万円程度のコストが必要となります。
その他、社員が辞めることでの職場の雰囲気の悪化などを考慮すると、コスト以上のネガティブ影響もあります。
確かに、サーベイの実施には一時的なコストはかかります。
しかし、「辞めた後のコスト」を見据えたとき、社員リテンションへの本気の取り組みこそが、中長期的な企業価値を支える本質的な選択だと言えるのではないでしょうか。
※生成AIワークバリュー・スコア分析は、デフィデ株式会社の登録商標です。
新しい働き方、DX環境下での人的資本経営を実現し、キャリアマネジメント、組織変革、企業強化から経営変革するグローバル標準人事クラウドサービス【JOB Scope】を運営しています。