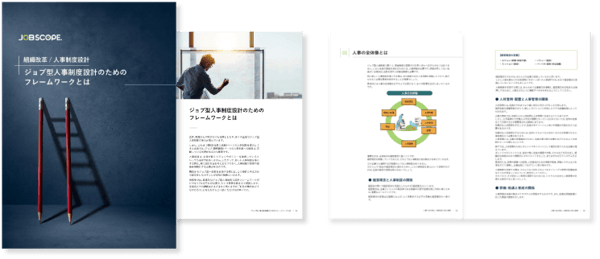独立行政法人中小企業基盤整備機構の発表によると、日本の中小企業数は約336万社(令和3年経済センサス 活動調査)。実に日本における全企業数の99.7%をも占める。また、中小企業で働く従業員数は約3310万人。全従業員数の69.7%を占めるに至っている。まさに、日本を支えているのは中小企業と言っても良い。そんな中小企業が時代の荒波を乗り越えて成長していくためには、どうしたら良いのか。そのメカニズムを検証しているのが、大阪経済大学の江島 由裕教授だ。近年では、実践的な起業教育にも取り組むなど、さらに活動範囲を広げている。インタビューの前編では、コロナ禍を経て中小企業は何を学んだのか、人手不足や後継者不足にどう向き合っていけば良いのかなどを聞いた。

01コロナ禍が自社の存在意義を内省する機会となった
江島先生は、中小企業の経営や政策の研究を手掛けておられます。コロナ禍を通じて中小企業は何を学んだのでしょうか。
これは非常に大きなテーマです。私は、コロナ禍の初期とその真っただ中で、経営者の方々とお話することが何回かありました。また、時々雑誌の原稿依頼もあり、いろいろと考えさせられる機会を頂きました。それらを振り返り、少し俯瞰してみたいと思います。
これは特に中小企業に限らない話なのですが、一般的に外部環境の変化が経営に与える影響が大きい、ということは、もう皆さんご存じのことかと思います。ただ、そこで言う外部環境の変化とは、物価高、円高/円安、少子高齢化、税額や金利など、まさにどの企業にも当てはまる一般環境要因が想定されます。また、自社のビジネスに直結する、競合他社の動向、消費者・ユーザーのニーズの変化、規制など個別環境要因の変化も、とても心配で、なおさら影響は大きいでしょう。
しかし、こうした変化は、一定程度、予見可能ではないでしょうか。逆に、予測が困難な環境の変化もあります。それは、大地震や山火事など、想定困難な自然災害です。その一例が、東日本大震災でした。思い出してください。その被害は尋常ではなく、ビジネスや経営への影響にとどまらず、ライフラインが分断され、従業員、家族、コミュニティへの深刻な被害は長期に渡り、それは想像を絶するものでした。日本、いや世界経済にも影響を及ぼしました。不確実性の高さから、ショックの大きさは図りしれないものでした。
そして、これを超えるものとして襲ってきたのがコロナ感染症です。もう説明する必要もないですよね。誰が、これほどまでの状況を想像できたでしょうか。目に見えない相手との闘いです。単に企業経営への影響に留まらず、人の生命に関わり、そして対処の仕方もわからない状態が長く続きました。不安しかありません。
そういう中で、企業もいろんなことに取組んでいました。例えば、小さな飲食店では、売り上げがあがらず、学生バイトから順に辞めていってもらってました。生き延びるために必死だったのです。一方、仕事がなくなった学生バイトも、生計を立てないといけないので、学業と生活がじり貧状態で必死でした。そんな中で、犠牲者が犠牲者を支援するという動きがありました。営業自粛中の飲食店が、アルバイト先をなくした大学生に無償のお弁当を配布したのです。また、休業した高級フランス料理店が、医療従事者にお弁当を無料で提供しました。
これは、犠牲者が犠牲者や支援者を助けるお互い様の精神、いわゆる利他的行動です。私のつたない調査研究成果ですが、2009年2月7日に発生したオーストラリア南東部ヴィクトリア州での大規模な森林火災や2011年3月の東日本大震災からの復興プロセスでもみられた光景です。
片や、ある雑貨屋では、店においてある商品が全然売れなくなり、もうとにかく売れるものは何でも売ろうということで、タピオカを売り出したと言います。業種とかは一切関係なく、生きるためには何でもやらないといけない緊急事態でした。
現状、コロナ禍は少し落ち着いてきたのですが、そこで経営者は何を学んだのでしょうか。当然学んだことは沢山あると思いますが、私が考える一番は、内省(振り返り)の価値です。これまでにない危機的状況の中で、自社にとって、最も大切なことは何か、創業から守ってきたものは何か、について真剣に考え、生き抜くため、一つずつ事業規模を縮小し/そぎ落とし、自社の原点に触れることができたのではないでしょうか。
自分の会社は一体何のために存在するのか。近年、理念経営、パーパス経営などキーワードが飛び交い、真剣に議論している会社は多いと思いますが、危機の中で、リアルに、その問いの意味を噛みしめる体験は、あまりないような気がします。この経験は、経営トップの頭の中に強く刷り込まれ、今後の経営の糧になったのではないでしょうか。コロナ過から経営者は、会社の根幹にかかわる存在意義を問い直す内省の機会を得て、新たな一歩を歩み出しています。

02中小企業こそ企業家的志向性が大切
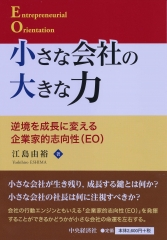

コロナ禍での学びを今後どう活かしていくべきであるとお考えですか。
外部環境の変化への対応について、予想し難い変化の波が連続して打ち寄せる時、大きな波を避けながらも、うまく波に乗るアジリティ力や、危機に対応しいち早く回復するレジリエンス力の大切さは、言うまでもありません。また、危機を想定したBCP(事業継続計画)やBCM(事業継続マネジメント)などの準備も必要です。
但し、自社が一番大切するものは一体何なのかという点については、それは危機的な状況の中でこそ浮かび上がってくるのではないでしょうか。新たな道がかすかでも見えてきた、ウイズ/アフターコロナ過の今、次は、まさに突き抜ける力が、必要になってくるはずです。それは、会社の成長エンジンとしての企業家的志向性(Entrepreneurial Orientation:EO)です。
これは、経営トップを中心に企業組織が、市場に対して革新的で一歩先取りのリスクを恐れない行動と思考様式のことを指し、会社の成長に欠かせない戦略概念とされています。実践面では、守りではなく攻め、分析より行動、既存より新規、行動の正確さよりスピードということになります。
この30年程で、世界中で企業家的志向性(EO)の研究が進み、それが中小企業の成長の鍵を握ることがわかってきました。将来の不確実性は依然として残る一方、コロナ過で市場特性は変わってきた今、動くチャンスです。これまでとは異なる市場ニーズやウォンツが生まれ、そこに事業機会(ビジネスチャンス)が見出されています。そのニッチな領域への企業家的志向性(EO)の発揮が、今後の中小企業発展のポイントになってくるのではないでしょうか。企業家的志向性(EO)にご興味がある方がいらしたら、拙著『小さな会社の大きな力―逆境を成長に変える企業家的志向性(EO)』(中央経済社)や『創造的中小企業の存亡: 生存要因の実証分析 (大阪経済大学研究叢書/東京白桃書房』をご一読ください。

03多様な人材に応じた活躍の場を提供すべき
中小企業は人手不足や後継者不足が深刻です。どう対処していけば良いのでしょうか。
中小企業は本当に多種多様です。規模も違うのでなかなか一様には、「これだ」と決めつけられません。確かに人手不足はあることはあります。ただ、先日、ゲストハウスを運営している社長さんと話をしている時に、「うちでは幸い人手不足問題はない」と言いきっていたのに驚きました。別に給与などの条件が良い訳ではなく、他のゲストハウスとの明確な方針の違いを示せているだけで、どうもそれが、「ここで働きたい」とか、「共感を抱くことができた」と言って、どんどん人が来てくれている理由になっているそうです。
実は、こうした会社は珍しくなく、昔からどんな時代でも小さくて地味な企業だから見えにくいだけで、しっかりと存在し今回もそのことを改めて示してくれたようです。もちろん、常に人手不足がなく、良い人材をほしいだけ採用できているということはないでしょう。良い時と、悪い時はあると思います。ただ、良い会社はどんな状況でも、自社の魅力や違いをぶれずに打ち出し、そこに共感する人に来てもらうという考え方を貫いてきたのではないでしょうか。そこが基本中の基本です。
とは言っても、一般的に中小企業も大企業も人手が不足していることは、マクロでみると間違いないでしょう。では、これにどう対応したら良いのでしょうか。当然のことですが、業務の効率性を一定程度高めるためには、機械化やDX化が必要なことは言うまでもないでしょう。その上で、付加価値の高い仕事を人間が担い、そういう人材が不足しているという前提での次の話になります。
対策として人口減少が続く中、様々な方面から広く人を募集することが、当たり前のことかもしれませんが、大切になると思っています。外国籍の方、シニア、主婦層、障がい者などへのアプローチはあるでしょう。これは、単に企業の人手不足問題の解消だけに留まらず、ダイバーシティ、働きがい、生きがい等、社会課題にも直結し、実は国としても関心を寄せていることなのです。最近は経済産業省がニューロダイバーシティ(脳や神経、それに由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを多様性と捉え、相互に尊重し、社会の中で活かしていこうという考え方)を推進しています。
実は健常者よりも障がい者の方が、業務内容によっては、優れた能力を持っているケースがあります。今後、仕事の仕方が、ジョブ型にシフトしてきた場合、まさにドンピシャになってきたりします。ただ、だからと言って、障がい者が全てそこに当てはまるかというと、必ずしもそうでないかもしれません。健常者同様、適材適所にマネジメントすることで、組織のパフォーマンスが高まるのではないでしょうか。加えて、障がい者を適切にマネジメントできている会社は、そうでない会社と比べて企業パフォーマンスが高いのでは、という感覚をもっています。さらに言うと、そうした会社は、健常者にとっても非常にホワイトで働きやすい、良い組織になっているとみています。
ただ、どうマネジメントするのかは知見が必要で、そういうことをコンサルティングしている方も結構います。重要なことは、業務効率を上げ、付加価値を高めていくためにも、業務の細分化、適材適所の人材配置、きめ細かなマネジメントが必要で、これまでの考え方の枠組みではなくて、外国籍の方、シニア、主婦層、障がい者などの思考、関心、行動様式に合わせていく必要がある思います。
私のつたない経験から、外国籍の方や留学生は、日本人とは異なる発想、創造性、行動力があり、独立志向も強く、知識や技術習得の意欲が高いと感じています。また、最近の日本人大学生は、言われたことはきちんとこなす一方、個人と会社との切り分け、社会問題への意識の高さ、仕事の内容より職場の雰囲気、自分のライフスタイル重視、の傾向が強いように思います。こうした点を踏まえて、ある中小企業では彼らの思考、関心、行動様式に合わすため、社内ではファーストネームで呼び合う、仕事とプライベートを分ける、褒める、怒らない、業務を明示的に示すなど工夫を凝らしているようです。
これまでは、彼らが会社に合わせていくという考え方でしたが、これからは会社が彼らに合わせていくように人事や組織が変わっていかないと、企業間競争に勝ち残れない、そんな時代が、もうそこまでやってきていると感じています。そして、それは避けられないと私は見ています。人材不足は問題ではなく、豊富で多様な人材をいかに社内で登用し、いかすのかという企業側のマネジメントの問題と捉えられるのではないでしょうか。
後継者不足に関してはいかがですか。
中小企業の大半は同族経営です。そして、そこで必ず出てくるのが、事業承継の問題ですね。古くて新しい議論で、学術的にも長きにわたって議論が続いています。日本の9割以上が中小企業であることを考えれば、後継者不足で経営が成り立たなくなれば、日本経済に与える影響は決して少なくはないでしょう。しかし、これは単に中小企業の後継ぎが見つかれば、それで問題解決という数合わせのことではありません。組織を任せ、発展させられる能力をもった事業承継者が必要とされているのです。後継者は見つかったけれど、会社がつぶれては意味がありません。
とは言え、それも難しいことはご承知の通りで、よく、スーパースターの創業者の後を継ぐのは至難の業と言われます。そして、世代が変わると組織のパフォーマンスは必ず落ちるようです。ですので、大切なことは組織全体の活力が低下することをわかった上で、その程度をできるだけ抑え、そのためにしっかりと準備をすることではないでしょうか。
何百年と続く長寿企業は必ず後継者問題に直面します。後継者は、先代から受け継ぐ暖簾や家訓など、守るべきものについて伝え聞きます。同時に、家業を途絶えさせてはいけませんので、守るだけでもいけません。経営に対してとても不自由で、がんじがらめの状態ですが、墨守ではなく何か新しい付加価値を生み出さないといけない、そんなプレッシャーとの闘いです。
こうしてみると後継者不足というのは、後継者の経営能力の問題として捉えられがちですが、果たしてそれだけでしょうか。事業や会社というバトンを受け取る側がいれば、それを渡す側もいる訳です。そこに責任がないとも言えないでしょう。実際、昔から、次世代のことを考えて、子供が幼少の頃からダイナスティ経営を刷り込ませたり、家業を途絶えさせないために養子を迎え入れることもあります。
一方、現代において何より大切なことは、事業承継のかなり前から、経営の委譲者と後継者とが相互に強く関わり合いをもっておくことではないでしょうか。意外と、現代のファミリービジネスは、この点が課題に見えます。語り合える場をつくり、お互い、それぞれの考えを理解し、学び、関係性を築いておくことが大切ではないでしょうか。
事業や会社というバトンをもって今走っている経営者のスピードと、後継者の走るスピードは異なるし、どのタイミングでバトンを渡すのか、どの部分を渡すのかで、バトンを落としてしまうかもしれません。準備こそが後継というレースの勝敗を分けるといえるでしょう。

04起業家社会を作る社会的な土壌が整備されていない
江島先生は、アントレプレナーシップ論でも第一人者でいらっしゃいます。日本においてアントレプレナー人材は着実に輩出されているとお感じになられてますか。
アントレプレナー人材は確実に増えてはいます。但し、海外と比較すると、必ずしもそうではありません。ユニコーンやメガコーンのような急成長型のアントレプレナーは、依然として少ないことは間違いありません。社会を変えるイノベーションの量や質も同様です。そうしたダイナミックな事業を創り出すためには、欧米諸国のようにリスクマネーの存在が欠かせませんが、その規模が海外並みにドラスティックに増えたかと言えば、まだまだと言わざるをえないでしょう。
実際の起業の実態をみても、日本は相変わらず起業も廃業も少ない少産少死型で、英米は逆に両方多い多産多死型です。但し、それは必ずしも良い、悪いというものではありません。歴史、文化、地域、制度の違いによるところが大きく、そこには日本特有のあり方があっても良いと思っています。一方、近年リスクマネーも着実に増え、また、資本金1円で起業もできるようになり、失敗のリスクも減り、格段とアントレプナーが生まれる環境整備が進んだことは間違いありません。
日本の場合、いきなり会社を起こすというよりは、どこかの会社に入って、そこで経験を積み、スピンオフあるいはスピンアウトという形で会社を立ち上げたり、家業を継ぐため会社を辞める人が多いと思います。欧米諸国のように、独立起業の割合は比較的少ないですが、一旦会社を立ち上げたら、その後、倒産や廃業する割合は高くありません。むしろ、欧米諸国の廃業率の方が高いんです。そういう意味では、日本では安易に焦って起業せず、石橋をたたいて、しっかりとしたアントレプレナーが生まれているといえるかもしれません。
全体として、日本のアントレプレナーが増えているのは事実でしょうが、その趨勢は未だ漸進的で、周囲の反応も冷ややかなところがあるように思います。一般的な認識からすると、「なぜ、起業なんかするの」「就職して組織人として成長する方が良いのでは」という見方が根強いでしょう。ビジネスの失敗や再挑戦に対する社会の寛容性も同様です。せっかく優良企業に就職したのに、なぜ、わざわざ辞めて会社を立ち上げるのか、どうしてそんなリスクをとるのか、家族、同僚、知人の反応、近隣住民の見る目も、成功したならともかく、一度失敗などすれば、さらに挑戦への否定的な空気感が漂ってくるのではないでしょうか。
一方、国内や海外で多数のロールモデルが出てきたからか、少しずつ起業に対する意識に変化が生まれ、大学生の中にも、就職せず自分が好きなことに挑戦しビジネスを展開する人も出てきました。高専や大学で学生の起業を積極的に支援し、インキュベーション施設やファンドを準備するところも増えています。また、企業の中には若くして起業に挑戦し失敗した人を評価するところもあります。企業内での社内ベンチャー制度や副業制度も充実しています。こうした挑戦や支援のムーブメントは、確実に根付き始めているでしょう。後は、周囲の人や組織やコミュニティが、自然に挑戦者と失敗者を応援し続ける起業家社会への進化です。待ち遠しい限りです。
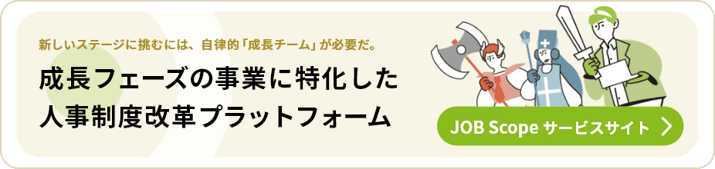

江島 由裕氏
大阪経済大学 経営学部
経営学部 教授
米国ピッツバーグ大学大学院公共・国際事情研究科 修士課程修了。公共・国際事情修士(MPIA)。上智大学 博士(経営学)。専門分野は、アントレプレナーシップ、中小企業経営、中小企業政策。日本ベンチャー学会清成忠男賞など受賞多数。