>組織経営の一丁目一番地は、人的資源管理の理解なり(前編)
人口減少が加速する日本。どの業種・企業でも人手不足に悩んでいる。ただでさえ、採用難であるのに、転職も一般化。せっかく入社したとしても、数年後には辞めていくケースが珍しくない。「人材は貴重な経営資源」と理解していても、その人材が確保できないでいるのが実状。せめて、今働いている社員にできるだけ長く勤務してもらわなければいけなくなってくる。それが、昨今「リテンション」という用語が注目される背景なのかもしれない。
その「リテンション」にいち早く着目し、16年前に研究書である『人材定着のマネジメント』(中央経済社)を執筆されたのが、青山学院大学名誉教授の山本 寛氏だ。その後も、人的資源管理論やキャリアデザイン関連の著書を立て続けに世に送り出してきた。さらに、2025年には2冊の書籍を出版。その知識探求欲は留まることはない。今回も新たな論点を提示してくれた。インタビューの前編では、「働く人のキャリアおよびキャリア意識の研究」を手掛けた経緯やこの四半世紀における人的資源管理論の変化などについて伺った。
目次

01働く人のキャリアやキャリア意識の研究に専念
そもそも、山本先生が「働く人のキャリアおよびキャリア意識の研究」を手掛けるに至った経緯をお聞かせください。
私は大学では政治経済学部に在籍し、ずっとマクロ的なことを学んでいました。実は、昔から選挙が大好きでした。特定のグループができたり、離れたり、人の足を引っ張ったり…、そういう下世話なネタも含めて面白かったです。
キャリアの研究に至った動機は、自分自身への強いこだわりです。就職活動への不安から大学3年頃、社会に出て自己実現していくためには、自分がどのような職業や会社が合っているかという適性に対する強い関心がありました。それで何をしたかと言えば、職業適性検査や職業興味検査、ハローワークでの職業相談(キャリア・カウンセリング)を受けまくっていたのです。
その後、自分の適性へのこだわりが他の人の適性へと関心が移っていきました。それで、カウンセリングに関心を持ちようになり、学問的にいうと臨床心理学(人間の精神的な問題を調査・研究し、心理療法やカウンセリングを用いて解決する学問)に強い関心を抱きました。ただ、ある臨床心理学の大家に「君の方向性は違うのではないか」と指摘され、それ以降はノイローゼや鬱などが関係する分野ではなく、人の職業の選択や適性、人間関係の悩みなどといった分野に絞るようになりました。さらには、当時転職が増加しつつあったことから、職業(組織)の選択だけでなく、選択後の適応も含むキャリア(意識)に関心を広げるようになりました。
それをきっかけに、自分がどんな仕事をしていきたいのかと考えていたのですが、私は長男なもので超安定志向でした。とにかく、安定して昇進ができるところが一番良いと思っていて、「ならば大学教授になるのが良いのでは」と考えました。時間が経てば、助教・准教授・教授と上がっていくからです。
それで、大学院に進学し、職務満足(修士論文のテーマ)、労働観等一貫してキャリア(意識)の研究に携わり、博士論文としてキャリア・プラトー(キャリアの停滞)現象をテーマとしました。
ただ、私が最初に勤めたのは銀行でした。銀行には3年いました。次に、市役所に行き、そこでかなりの年数仕事をして、最終的に34歳で大学教員の道に入りました。
要は、なぜキャリアの研究に至ったのかというと、職業への適性をずっと研究していくうちに、職業への適性は入り口の選択、具体的にはどんな組織を選ぶかだけではなくて、もはや転職が当たり前の時代なので、組織に入った後、その職業や組織にどういうふうに適用していくか、つまり選択と適用の繰り返しだということが分かってきました。
そうすると、入り口の適性だけではなくて、その後会社の人間関係や仕事にどのように適応していくのか、さらに自己実現やキャリア目標を達成していくときに、どうしていくかということで、時間軸が段々伸びていきました。
ただ、キャリアの研究といっても、キャリアには主観的キャリア(仕事のやりがいや達成感)と客観的キャリア(職歴・経歴)があります。普通言われるのは、客観的キャリアです。要は履歴書に書いてある、大学を卒業した後、いつどういう会社に就職をして、そこでどんな仕事に就いたみたいなものです。その背景にあるのは、その人が就職して、それから転職してどういうふうに思ったかという、キャリアの意識の問題だと思っています。私はその両面から追いかけています。
『転職とキャリアの研究 改訂版: 組織間キャリア発達の観点から』(創成社)や『人事労務担当者のためのリテンション・マネジメント』(日本法令)などの著書でも述べましたが、職業選択の自由もあり、転職するのは従業員の自由であることは当たり前です。ただ、組織の側からすれば、できれば優秀人材には長くいてもらいたいわけです。その合わせ鏡なのです。
なので、組織の側から見ればリテンション(人材定着)というような形で、従業員に対するキャリア支援をするみたいなことも含めて、今は割とキャリア(意識)研究の一環として、転職によるキャリア発達やリテンション、専門性(意識)も研究するようになっています。

02この四半世紀で人的資源管理論に大きな変化が起きている
山本先生は、2001年に青山学院大学経営学部に着任され、助教授・教授として人的資源管理論の授業を一貫して担当されて来られました。この25年で人的資源管理論にどのような変化が見られるとお考えですか。
これは、五点あると思っています。
一番目が集団管理から個別管理への移行です。つまり、以前の人的資源管理では、いわゆる春闘でモデル賃金を巡って交渉が繰り返されました。その会社や業界で何歳の人が、幾らもらうのかみたいなものがあって。それにベースアップとか、全体をどうするというような感じだったと思います。それが今は、従業員一人ひとりで大きく変わっています。極端なことを言うと全部違います。もはや、入社年次が同じだから同じような考え方をする、就業形態が同じだから給料も同じということはありません。全然違います。極端な話、価値観や考え方まで配慮に入れないと、上手く行かなくなっています。それが、一点目です。
二番目が、戦略的観点から経営戦略との適合の重視です。一般的には戦略人事と言うと、大体これが出てきます。経営戦略と人事戦略を一体化させないといけないということです。それまではどうだったかというと、人事部門は人事について専門知識を持った集団であって、あくまでも経営者が決めることに、人事面からアドバイスをするだけでした。例えば、会社が、中国に進出をするといった戦略を立てるときには、必ず人の問題に遭遇します。具体的には、中国のある地方のエリート層を採用するためには、どういうことをしなければいけないかみたいな戦略と合致したことをやらなければいけません。これが今、非常に指摘されています。それが、人的資本経営にももちろんつながっているわけです。
三番目が企業業績への直接の影響の重視です。これも戦略的観点と関係があるのですが、先ほどは人的資源管理の前提の話です。今度は人的資源管理の結果やその影響のことを指します。今までは、人的資源管理がどのようなものであっても、特にそれが財務業績に直接影響するということは、あまりありませんでした。なぜかというと、例えば人事が頑張って非常に良い人材を取ったとしても、その人材が会社の中で研修などを通じて育成され、適性のある部署に配置されて、業績が伸びるのは何年後かということになります。つまり、業績への影響はかなり先にならないとわからないため、人事自体と業績との直接的な関係は問われいませんでした。それが、最近は非常にその関係が言われるようになってきました。
四番目が施策同士の整合性重視。これは、成果主義の例で言うと一番明らかです。要は、成果主義の導入の場合です。例えば、年俸制を導入しているのに、一部、年功に合わせた給料のやり方を残していると、これはもうアクセルとブレーキの両方を踏むようなものなので、あまり上手くいかないだろうと思います。つまり、能力開発にしても、採用や育成、退職にしても同じ方向を向くようにしないといけません。どの方向を向くかを決めるかのが経営戦略だと思います。
最後の五番目が、人的資本情報の開示と人的資本の価値を向上させるための経営の重視です。言うまでもなく、人的資本経営の話です。これの1丁目一番地が人的資本に関する情報の開示です。すなわち、2024年の3月頃、大手企業が一斉に開示した情報が、女性の管理職比率や男性と女性の賃金格差などでした。しかも、ただ開示すれば良いと言うわけでもありません。開示した情報が企業としては、良くなっていくという方向を、ストーリーとして見せなければいけないのです。例えば、こういう施策をやった結果、社員のエンゲージメントが向上し、その結果、例えばリテンション、つまり定着率が上がって業績につながりましたというようなことを、ストーリーとして、ステークホルダー(関係者)に見せていく。これを人的資本の価値を向上させること、すなわち人的資本経営というのですが、こういうことが重視されました。ストーリーを見せるためには情報を出さなければいけませんし、出すだけではなくて、それが価値の向上につながっていかなければいけないということです。
これに関係してくるのが、リスキリングや専門性の重視、組織による社員の専門性を高めるためのマネジメントです。この辺りは、私が2年前に出させていただいた、『働く人の専門性と専門性意識―組織の専門性マネジメントの観点から』という本の中に詳しく書いてありますので、そちらをご一読ください。

03深刻化する採用難と人手不足にどう手を打つべきか
山本先生の著書『人事労務担当者のための リテンション・マネジメント-人材流出を防ぐ実践的アプローチ』(日本法令)が2025年2月20日に発売されました。どのような問題意識から執筆に至ったのでしょうか。
これに関しては、4点あります。一番目が、私は2009年の『人材定着のマネジメント経営組織のリテンション研究』(中央経済社)、2018年の『なぜ、御社は若手が辞めるのか』)および2019年の『連鎖退職』(以上、日経プレミアシリーズ)など、何冊も著書を執筆してきました。今はそのときよりも、さらに構造的少子高齢化を背景にした採用難と人手不足が進行しています。特に物流の2024年問題(ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることでもたらされる物流・運送業界の問題の総称)が出てきました。トラック運転手の方の働き方改革、長時間労働の規制について適用されるようになったのが2024年です。本当に色々なところで、人手不足がリテンションの背景にあるとは言え、人手不足の問題が深刻化したというのが一番目です。
二番目は、転勤の見直しやアルムナイ(卒業生)制度、リテンションボーナス、副業・兼業の容認、テレワーク等、リテンション・マネジメントにおける新しい施策が次々に導入されてきたため、それについて述べたいと思ったことです。
三番目が、働き方改革以降注目されている働きがいやエンゲージメント向上の果たす役割に触れたかったからです。働き方改革のときは、主に働きやすさに注目が当てられました。しかし、近年は自分の成長につながる働きがいやエンゲージメントがリテンションに大きな影響を与えるようになってきました。それで、特にこの二つを別の章として取り上げた方が良いと考えました。
最後、四番目がリテンションにおいて重要ではあるものの、見過ごされがちな管理職の役割について、1 on 1ミーティングの活用等を中心に触れたかったからです。最近は上司と部下との定期面談、すなわち1on1ミーティングを生かさない手はないと指摘されています。リテンションにとって非常に役立つ施策は、コミュニケーションの活性化と待遇の改善ということがある調査で示されています。なので、コミュニケーションの部分について、特に若手社員と日常的に接するのは管理職です。管理職が1on1ミーティングの施策を通じて、例えば離職の兆候を察知するとか、できれば成長実感を味わってもらうとか、部下を褒めるとかが必要だと思っています。ここについても、また新たな章で取り上げたいと思いました。
山本先生の著書を紐解いていくと、2009年にはもうリテンションというワードに着目されていらしたことがわかります。人材領域でのリテンションという点では、先駆けと位置付けられるのではないでしょうか。
当時、リテンションという用語は検索すれば出てはきました。ただ、それらは技術系やマーケティング論の分野がメインでした。例えば、マーケティング論におけるリテンションの対象は顧客です。従業員を対象にしたリテンションは、あまりなかったと記憶しています。ましてや、従業員の定着と活躍を意味するというところまでは行っていなかったです。そういう意味では、この10数年で少し広がってきたというところではないかと思います。

04リテンション・マネジメントは経営者にとってもキーワード
著書『人事労務担当者のための リテンション・マネジメント-人材流出を防ぐ実践的アプローチ』(日本法令)を通じて、読者にメッセージされたかったポイントは何ですか。
実は、出版社から「『人事労務担当者のための』というショルダータイトルを入れてほしい」と言われたので織り込みましたが、私としては以下の三者にも読んでいただきたいという想いがありました。
まず一番目に、これから人事部門で仕事をされる人事担当者の皆様を中心に、リテンション・マネジメントについて求められる基礎的な知識を身につけてもらいたいと思いました。例えば、別の部署から人事に移ってきたとか、新人で人事に配属となった…、そういう方々を中心に、まずリテンション・マネジメントについて求められる基礎的な知識。例えば、そもそも何なのかとか、リテンションが向上したというのはどういう指標で分かるのかとか。そういうことも含めて、基礎的な知識を身につけてもらいたいと思ったのが一点目です。
二番目は、就職や転職を考えている人の会社研究の一環として、リテンションという視点からこれから身を置きたい組織を考えてもらう際の参考にしてもらいたいと思いました。いわゆる、一般の方々です。先ほどお話した通り、転職を考えている人は非常に多いです。あと就活生も会社研究をするはずです。今も当然、検索サイトやSNSで調べると思うのですが、会社研究の一環として定着、そして活躍という観点から、身を置きたい組織を考えてもらう際の参考にしてもらいたいと思っています。
実際、私のゼミの学生も、自分が行きたいという企業の退職率を調べるということを結構聞きます。他社に比べて退職率が多いのは、何か問題があるのではないかと判断しているようです。
三番目が、自社の人事課題として、採用や能力開発への関心が中心になりがちな経営者や管理職の方々に、現在勤めている社員の重要性を再認識してもらうきっかけになってもらいたいと思います。「自社の人事課題は何ですか」と経営者の方に聞くと、最も多いのは採用です。採用ができないという悩みです。次に多いのが、研修や能力開発。実は、定着となるとかなり順位が低くなります。
しかし、人事部門は定着に対してかなり危機感を持っています。なので、どう取り組んでいけば良いかと考えている人が多いです。もっと多くの経営者の方にも定着やリテンションについて関心を持っていただく。つまり、今勤めている社員の重要性を再認識してもらうきっかけになってもらいたいと思いました。
それを考えるようになった発端は、人事の方との会話です。結構聞くのは、「先生、今年の転職者も即戦力として活躍してもらえませんでした」という声です。できれば、転職してもらった方には、職場にスムーズに慣れ、早い時期から前職での経験やスキルを発揮してもらいたいものです。そして、長く勤めてほしいはずです。そのためには、どうマネジメントをしていけば良いのかを経営者や管理職に学んでほしいと思っています。

05退職者との関係を維持する「アルムナイ制度」も有効な施策
その意味では、タイトルに「人事労務担当者のために」とありますが、こちらの本は幅広い読者を想定されておられるのですね。ところで、著書でも触れておられますが最近はアルムナイ制度に対する関心が急激に高まっています。先生はどう捉えておられますか。
非常に有効だと思っています。特にIT業界では辞める人も多いです。せっかく新規プロジェクトに入って、新しいことをやってくれたのに、辞めてしまうと非常に痛いですよね。昔は元○○という言葉が付く会社は、リクルートぐらいでしたが、今は沢山あります。
しかも、色々な会社出身の人が再び戻ってくる。そういうことも珍しくなくなっています。カムバックと言ったら良いでしょうかね。となると、リテンションという概念を広げるという意味では、アルムナイ制度は必要だと思います。
ただ、アルムナイ制度を活性化させていくための1つのポイントが、いわゆる辞めるときにあります。通常、辞めるときに退職時面談、exitインタビューを行うはずです。退職理由は何なのかを聞き取ろうとするわけです。会社としては、それを職場環境や人事制度の改善につなげていきたいからです。
これは、当然行われていることなのですが、「どういう理由なのか」とあまりきつめに聞いてしまうと、それがもうプレッシャーやストレスとなって、「もうこの会社のアルムナイなんてとんでもない、二度と戻りたくない」と思ってしまいます。忸怩たるところかもしれませんが、「なぜ辞めるのか」という本音を知りたいのは良くわかるものの、あまりしつこく聞かないことです。実際に、20代の女性に対するアンケートで、「前の会社にいたときに一番不満だったこと」のトップが、辞めるときにしつこく「何が不満なのか」と聞かれることだと言います。
そうした背景にあるのが、最近話題の退職代行でしょうね。今年になって需要が急速に伸びてきました。「とにかく、あの嫌な上司に退職届を出すのなら、5万円を出しても良い。もう辞めたい」ということなのだと思います。
やはり、辞めるとなってもお互いがWin-Winの関係でありたいものです。双方が良ければ、何らかの形で周年行事等にも出てもらえます。場合によっては、出戻りということにつながるかもしれません。たとえ戻ってこなくても、副業やアウトソーシングを含めてパートナーとして仕事を受けてくれる可能性もあるはずです。いずれにしろ、良い関係性を構築していくために、注意点が色々必要となってきます。
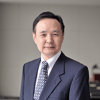
山本 寛氏
青山学院大学
名誉教授
キャリアデザイン論担当。博士(経営学)。メルボルン大学客員研究員歴任。働く人のキャリアとそれに関わる組織のマネジメントが専門。日本経営協会 経営科学文献賞などを受賞。大学では、人的資源管理論とキャリアデザイン論を担当してきた。主な著書(単著)は『連鎖退職』、『なぜ、御社は若手が辞めるのか』、『「中だるみ社員」の罠』(以上、日経BP社)、『自分のキャリアを磨く方法』(創成社)、『人材定着のマネジメント』(中央経済社)、『働く人の専門性と専門性意識』、『昇進の研究』、『転職とキャリアの研究』、『働く人のためのエンプロイアビリティ』(以上、創成社)など。2025年2月に『人事労務担当者のための リテンション・マネジメント-人材流出を防ぐ実践的アプローチ』(日本法令)を出版。

