「現場で実践できるリーダーシップ」をメインテーマにし、リーダーを素養や資質ではなく、望ましい行動として捉える当連載。
今回は組織で仕事をしているうえで基本となるPDSサイクルにおいて、優れたリーダーがどのような行動をしているかを取り上げます。
PDSはリーダーに限らず、新入社員でもベテラン社員でも、仕事における基礎概念です。
リーダーの行動に焦点はあてるものの、組織で働いている方には参考にしていただける内容でしょう。
 01 Plan:問題特定力と問題解決力を養う
01 Plan:問題特定力と問題解決力を養う
プランニング段階で必要となるのは「問題を特定する力」と「問題の解決策を考案する力」です。
ハーバード・ビジネス・スクールのロバート・カッツ教授が提唱したカッツモデルの「コンセプチュアルスキル」に含まれる能力で、より大きな組織をリーディングするためには不可欠な力です。
カッツモデルの中でも難易度が高いスキルですが、実はヒューマンスキルと比べても、努力によって十分開発できる力といえます。
優れたリーダーは、なるべく小さなテーマや身近な題材でコンセプチュアルスキルを磨く訓練をして、習熟を重ねることで上位層のリーダーに就任しています。
したがって、本記事ではリーダー初心者の方でも、参考にしやすい内容にブレイクダウンしてお伝えします。
問題を的確に特定するためには
リーダークラスのビジネスパーソンになると、ある課題を前にすると、過去の経験や前例などをもとに問題を特定できることは多いでしょう。
ただし、その特定した問題が的確だったとしても、「過去の経験が生かせた」というだけでは、そのプロセスはブラックボックスになってしまいます。
優れたリーダーは問題特定のプロセスを常に可視化し、そのことでメンバーの問題特定力を高める努力を怠りません。
問題特定プロセスを可視化するためには、「全体をモレなく、かつ構造的に把握する」ことが重要です。
これをシステマチックに行う手法として「ロジックツリー」があります。ロジックツリーは『MBAクリティカル・シンキング』(グロービス・マネジメント・インスティテュート著、ダイヤモンド社刊)など多くの書籍で紹介されている、コンセプチュアルスキルの基礎的なフレームワークです。
ロジックツリーでは、あるテーマを論理的にその構成要素に分解し、さらに同じように分解し、結果的に次々と枝分かれして木のような形になります。
一例として、身近なテーマで「朝の電車がなぜ混むのか?」でロジックツリーを作ると、以下のようになります。
構成要素に分解する際にポイントとなるのは、「モレなくダブリなく分解する」(MECE=Mutually Exclusive、Collectively Exhaustive)ことです。
このことで、問題を特定する際の混乱を防ぐことができます。
チームメンバーのアイデアを活用し、問題解決に取り入れる
特定した問題の解決策を検討するプロセスも、前章同様ロジックツリーを使うことが効果的です。
問題特定の場合は「なぜ?」という問いだったのに対し、解決のためには「どうすれば?」という問いになります。
解決策を決めるのはリーダーのミッションですが、解決策を考えるのはリーダーだけとは限りません。むしろ優れたリーダーは「もっと良いアイデアがあるかもしれない」という思考が強いため、チームメンバー全員の視点を活用して、解決策を見出そうとします。
イノベーションの多くは、実は複数の人材の優れた才能を組み合わせた中から生まれています。これは「コレクティブ・ジーニアス(集合天才)」という考え方です。
イノベーションを起こすリーダーは、自分とは異なる視点のメンバーから複数の解決策アイデアを募ります。さらにどれか一つの解決策だけを採用するのではなく、それらを組み合わせてアレンジすることで、より高次のイノベーションを実現しているのです。
根拠を示し、透明性を持った決断を行う
リーダーの重要なミッションの一つは「決める」ことです。
しかし残念なことに、日本企業のリーダーの苦手なことの一つも「決める」ことではないでしょうか。
日本企業はコンセンサス(合意)を取ることを重視する風潮が強いため、会議や稟議システムでは、参加者の大半が納得するまで議論を尽くす傾向があります。
ここで認識しておきたいのは「決断」と「判断」は違う点です。
- 決断・・・・・・「やること」「やらないこと」を決めること
- 判断・・・・・・複数の選択肢から最適解を導き出すこと
優れたリーダーは、AかBかを簡単に「判断」できることはメンバーに権限委譲して、どんどん現場での意思決定にチャレンジさせていきます。
リーダーの役割は「決断」することです。
決断は責任を伴うので、責任の所在を明確にして周囲に示す必要もあります。また、得てして全員の合意を得られない状況でも、実行スピードを上げるために、決断をしなくてはならない場面もあります。
そんな時でも、周囲に「やること」「やらないこと」の取捨選択の理由や根拠を明示し、なるべく多くの方からの合意を得る工夫は忘れないようにしましょう。
このプロセスを怠ると、いくら力量があるリーダーでも、ゆくゆくは「一匹狼」のような状態に陥ってしまいます。
 02Do:自分が動くだけでなく、メンバーを動かす
02Do:自分が動くだけでなく、メンバーを動かす
プランニングのプロセスでいくら素晴らしい絵を描いたとしても、課題解決策の実行プロセスでうまくいくリーダーと、頓挫しがちなリーダーに分かれていきます。
その分かれ目を招く要因の大半は、メンバーへの働きかけにあります。
リーダーのプレイヤー化が避けて通れない労働力不足の状況でも、優れたリーダーは自分と同等、あるいは自分以上にメンバーが奮起する工夫を行っています。
ここでは問題解決の実行プロセスでの、リーダーのメンバーへの働きかけを紹介します。
メンバーの気持ちを動かす(態度変容)
解決策が複数あり、メンバーが複数人いる場合は、メンバーにジョブアサインメント(仕事の割り当て)をするはずです。
ジョブアサインメントのゴールは、伝えることそのものではなく、メンバーに伝えた内容を理解してもらい、実行のモチベーションを高めてもらう「態度変容」が目的となります。
これを実現するためのキーワードが「TCME」です。
マーケティングでよく使用される概念を組み合わせた造語ですが「Target・Contents・Media・Expression」の4つの単語の頭文字を取ったものです。
- Target
今回のテーマを担わせるメンバーは誰にするか
- Contents
伝えるメンバーは当該テーマにどれほどの情報を所持しているか
- Media
メンバーの理解を促すためには、資料がいいのか映像がいいのか口頭がいいのか
(ドラッカーによるとインプットには「利き手」があり、文字でのインプットが得意な人と会話でのインプットが得意な人などと分かれる)
- Expression
伝えるメンバーはどのような価値観を持っていて、どのような伝え方が響くのか
とりわけ、Expressionはリーダーの腕の見せどころでしょう。
メンバーが日常的に使っている言葉や興味を抱く表現、事例・比喩を活用することが有効です。
このように細かい伝え方(=伝わり方)に配慮することで、メンバーの理解度が高まり、前向きに態度変容する可能性が高まります。
メンバーの行動を促進する(行動変容)
リーダーがメンバーに仕事を依頼する際のポイントは、仕事の実行当事者であるメンバーの能力・スキルに応じたサイズに整えることです。
いわば「相手の持てる荷物の大きさにする」ようなものです。
大風呂敷を広げて現場にハッパをかけることがリーダーの仕事を勘違いしている人もいるようですが、それではメンバーの行動は促進されません。
例えば営業部門で「売上げを倍にするぞ」とメンバーに伝えるだけでは、戸惑ってしまうメンバーも多いことでしょう。
自力で拡販戦略まで描けるメンバーもいるかもしれませんが、ほとんどのメンバーが「売上げ倍」というお題では、荷物が大きすぎて持てなくなるのです。
したがって
- 数量×顧客単価に分解する
- 既存顧客or新規顧客の売上げに分解する
- 営業プロセス別に分解する
など、メンバーが持てるサイズにまでリーダーは分解したうえで、メンバーに依頼する必要があるのです。
メンバーから具体的な質問や別のアイデアが出てくる状態になったら、メンバー自身が行動に移すイメージが持てた状態と認識できます。
リーダーは「鳥の目、虫の目」のような全体を俯瞰する鳥の目と、現場の詳細が分かる虫の目が両方求められているといえるでしょう。
 03See:説明責任を担い、結果から学ぶ
03See:説明責任を担い、結果から学ぶ
目標や課題に対して一通りの実行施策が終わったら、いわゆる「振り返り」フェーズになります。
このフェーズでリーダーに求められることは、説明責任と結果の分析です。
結果に対して説明責任を持つ
経済不安が続く昨今、企業や政治家など影響力のある組織や人が「説明責任を果たすべきだ!」と、マスコミなどから追求される場面をよくニュースなどで見聞きすることは多いのではないでしょうか。
このように、利害関係者に対して自身が担当し権限を持ってその内容や状況について、より詳しく明確に説明することを説明責任と言います。
この説明責任という用語は、1960年代にアメリカで誕生した「アカウンタビリティ(accountability)」が語源となっており、「アカウンティング(accounting:会計)」と「レスポンシビリティ(responsibility:責任)」の組み合わせです。
VUCAのような不安定な時代では、掲げた目標のすべてが予定通りに達成できるわけではありません。
そんな時でも優れたリーダーは悲観的にならず、組織として成長する機会と捉え、目標未達の要因を分析し、周囲に説明をする責務を果たします。
ネガティブな結果に蓋をしてしまうことは、周囲からの信頼を毀損するのみならず、組織の成長にも寄与しないといえます。
リーダーとしては常に冷静な目線で結果を分析し、周囲に「なぜこのような結果になったのか」「次に生かすべき点は何か」をフラットに周囲に開示するべきでしょう。
失敗しても次にチャレンジすることを鼓舞する
メンバーの目標や役割を明確にすることは、リーダーの重要な役割の一つです。
ただし、その目的は目標を達成できたか、未達成だったのかという評価を明確にすることではありません。
重要なのは目標と結果を比較し、仮にギャップがあった場合にも、経験から学ばせることです。
得てしてハイパフォーマーは成功よりも、むしろ失敗から学ぶ傾向があります。
成功した場合は、その再現性を高めるために結果にインパクトを与え、さらに偶然ではない要因を特定します。もちろん失敗した時にも要因分析を行い、再現防止のための予防策や発生時対策を考えます。
このように、優れたリーダーは失敗を結果だけで捉えず「得がたい経験」と捉えて、そこからの学びを抽出する傾向があります。
このスタンスをメンバーにも推奨することで、メンバーも失敗を恐れず、次のチャレンジに視野が移ることになります。きちんと要因分析をしたことで「次は同じ失敗には陥らないはず」という安心感につながるからです。
 04まとめ
04まとめ
昭和の時代は、直感や経験則に頼ってメンバーを引っ張っていくリーダーが求められていましたが、現代は様相が様変わりしています。
昨今のリーダーは「感情を理解しながらも合理的に」や「メンバーに任せながらも存在感を誇示して」など、ややもすると相反する言動を駆使する必要があるといえるでしょう。
組織でリーダーシップを発揮するための葛藤や苦悩は、環境変化が激しければ激しいほど、むしろ心理学に近い領域に近づいているといえます。
つまり、小手先のテクニックよりも、本質的に人に働きかける力が問われているのです。
資質頼りではなく、リーダーシップを意識的に磨くことができれば、人生100年時代といわれる現代で、仕事だけでなくライフキャリアにも役立つ武器になるでしょう。






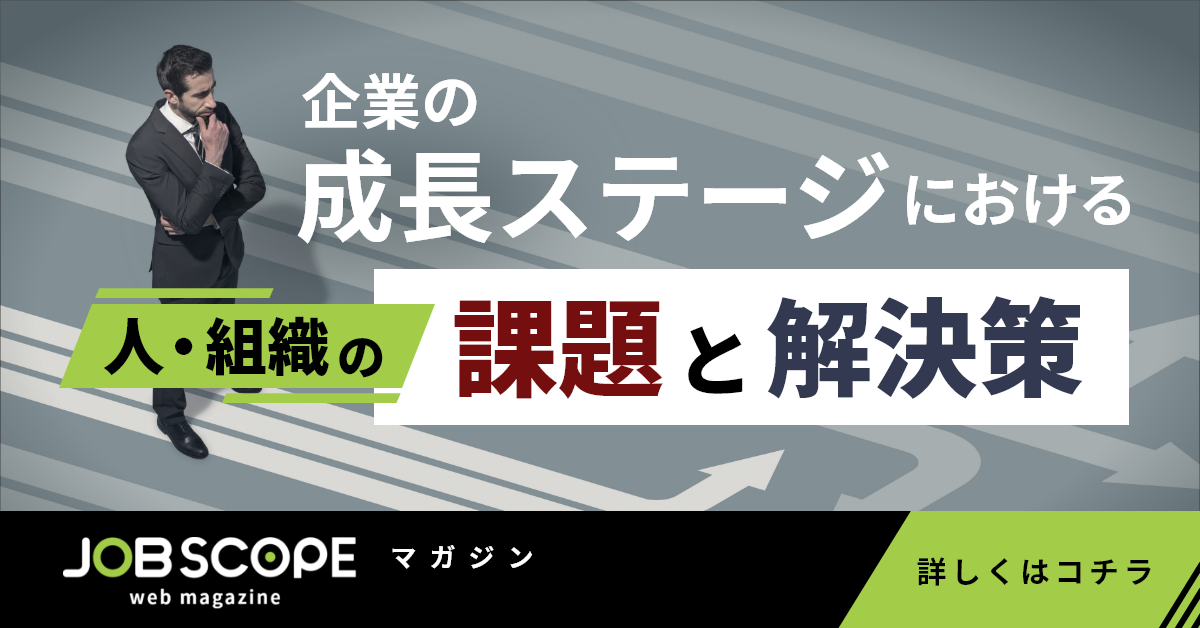





SHARE