一昔前は「従業員満足を高めたい」と考える経営・人事の方が大半でした。
一方、昨今では「従業員満足度」は「従業員エンゲージメント」という言葉に置き換わりつつあります。
エンゲージメントとは、企業自体や商品や・ブランドなどと消費者との深い関係性のことです。企業内で用いられる場合は、社員本人の内側から湧き上がる貢献意欲と解釈されています。
「従業員満足度」では、報酬やオフィス環境への満足などの外的要因を指すケースが多かったのですが、エンゲージメントは本人の内面も含めてアプローチする必要があります。
ただし、外的要因を何も整えず内面にアプローチをしても、効果は薄くなるか一時的なものとなります。
社員は外的要因の納得感と、それを運用するソフト面への納得感の両面から、「この会社で頑張ろう」という気持ちになるからです。
本記事ではエンゲージメントを高めるメリットを確認した上で、エンゲージメント向上の課題と解決策について【外的】【内的】の両面からのアプローチを紹介します。
従業員エンゲージメントを高めるメリットとは何か?
「従業員エンゲージメントは高い方が良い」
このような意見に異論を唱える方はあまりいないでしょう。
ただし、エンゲージメント向上を狙って何らかの施策を実行する場合は「自社が何を狙うのか?」と目的をしっかり設定しないといけません。
目的が曖昧な場合、的外れな施策を展開してしまったり、施策が頓挫してしまったりするからです。
本章では、具体的なデータをもとにしながら3つのメリットについて解説します。
自社のエンゲージメント向上への目的設定の参考にしてください。
社員の帰属意識が高まり、離職を防止できる
エンゲージメントが高まった状態の社員が多いと、社員の定着力を上げることができます。
企業でのエンゲージメント向上のための取り組みとは、組織へ愛着を持ったり、自社で働く意味を見いだしたりする社員を増やすための活動です。
新卒採用も中途採用にしても、いずれも苦労して採用にした人材が組織で活躍する前に離職してしまうのは、企業にとって大きな損失です。
採用した社員のエンゲージメントを高め、定着率を上げることができれば、採用活動を繰り返すことを避けられます。
実際、エンゲージメントの違いによって離職率の違いを示す研究データもあります。

参考データ:「Driving Performance and Retention Through Employee Engagement」CEB社
労働力不足に悩む企業が多い昨今の状況では、社員の離職を防止できることは大きなメリットといえるでしょう。
社員のやる気が高まり、業績の向上が期待できる
従業員エンゲージメントの向上は、企業業績の向上にも無視できない観点です。
ただし、エンゲージメントと業績の間にはさまざまな変数やプロセスがあるため、短期的には実感しにくい観点といえるでしょう。
エンゲージメントの重要性が世界的に広まった背景には、従業員エンゲージメントの企業業績や生産性向上への寄与が、データで明らかになったこともあります。
ウイリス・タワーズワトソンの調査では、「持続可能なエンゲージメント」のレベルが高い企業は、低いエンゲージメントの企業に比べ、1年後の業績(営業利益率)の伸びが3倍という結果が出ています。

出典:タワーズワトソン(現ウィリス・タワーズワトソン)プレスリリース(2012年7月25日)をもとに作成
※なお「持続可能なエンゲージメント」とは、ウイリス・タワーズワトソンが提唱した指標で、エンゲージメントを“継続的に高く維持している”という要素です。
エンゲージメントが高い状態が継続すればするほど、業績への好影響がより顕著であることが検証されています。
さらに日本でも2021年に、慶應義塾大学ビジネス・スクールの慶應義塾大学大学院経営管理研究科(岩本隆教授)の研究により、エンゲージメントの向上は、営業利益率並びに労働生産性向上に寄与することが分かりました。
参考:「持続的な企業価値向上と人材戦略に関する一考察 」慶應義塾大学大学院経営管理研究科
特任教授 岩本 隆
このような調査結果をもとに、企業規模を問わず先見の明のある企業では、従業員エンゲージメントを高める活動が加速するようになったのです。
経営ビジョンや理念が社員に浸透し、会社への愛着が高まる
エンゲージメントの高まりとは、社員が経営ビジョンや理念に共鳴している状態といえます。
つまり、「この会社が好き」「この会社の社員でいることが誇らしい」という心情の社員が多いということです。
ビジョンや理念が浸透していない状態では、個々人の社員の判断で自分が良かれと思った言動や判断を取ってしまいます。この状態では「組織」ではなく、単なる「人の集合体」といえるでしょう。
ビジョンや理念が浸透していれば、社員個人が「この判断はビジョンに照らすとどうなのだろう?」と考えるようになり、結果的にビジョンを実現しやすくなります。
さらにはビジョンや理念が風土として浸透していけば、極端に考えれば、社員の行動を規制するような、細かい人事評価制度や行動規範も不必要となります。
風土にまでビジョンや理念が昇華すれば、個人が意思決定できるいわゆる「ティール型(進化型)組織」に近い状態といえるでしょう。
「なぜ日本企業ではエンゲージメントが高まりにくいのか?
エンゲージメントを向上させたいと思っていても、日本企業が本腰を入れて取り組めないのは、何かしらの理由があるからです。
自社でエンゲージメントの向上に取り組む際には、日本企業のエンゲージメントをとりまく課題や、エンゲージメントが高まらない独特の背景を理解する必要があります。
自社を点検する観点を持ちながら、記事をお読みいただければ幸いです。
タスク・職務の可視化が進んでいない【外的な要因】
エンゲージメントに直接影響しやすいのは「会社からの自分への評価」といえます。
この評価は、制度としての人事評価に限らず「忙しさの違い」「仕事の分担の違い」「報酬・賃金の違い」など、会社内に存在するさまざまな場面を含んでいます。
これらさまざまな評価場面を社員が眺める観点は「公平であるかどうか」という基準でしょう。
しかし職能資格制度をベースとしがちな日本企業では、欧米ほどタスクや職務の可視化が進んでいない課題があります。
その結果、仕事の内容と評価は大雑把であいまいになり、社員は不満を抱きやすい状態になります。
極端な例ですが「何でも仕事を受ける良い人」「どんな仕事もとにかく頑張る人」に負担が集中し、社員は会社から何を求められているかが分からなくなってしまいます。
一方で負担が集中した社員も「こんなに頑張っているのに、手を抜いているベテラン社員の方が給与が高い」などの不満を抱いてしまうでしょう。
インナーコミュニケーションが未発達【内的な要因】
社員へのケアというインナーコミュニケーションの観点は、歴史的・風土的に日本企業には薄いといえます。
インナーコミュニケーションが未発達なことは、「会社が何も手を打たなければ、社員のエンゲージメントは勝手に高まらない」ことにつながります。
歴史をひもとくと、元来日本企業は社員の満足よりも顧客満足に徹する姿勢が強い傾向があります。
顧客の要望に応えたい商人精神が功を奏し、高度経済成長下では日本が誇るモノづくり文化が形成されていきました。
しかしバブル崩壊後、日本企業は競合との顧客獲得争いにさらされ、顧客へのサービス合戦が過熱していきました。
その結果、一部の業界でサービス残業や超過勤務などが発生し、ついには顧客第一主義が社員を犠牲にする弊害が起こったのです。
そんな日本で急速に従業員エンゲージメントが注目されたのは、米国の調査会社ギャラップ社が2017年に実施した調査結果です。
この調査では、日本企業は「熱意あふれる社員」の割合がわずか6%であり、139ヵ国中132位と最低ランクに近い順位であることが判明しました。
参考:「熱意ある社員」6%のみ 日本132位、米ギャラップ調査
社員自身の「やりたい」を引き出すエンゲージメントには、多くの日本企業では何も策を投じていなかったからです。
この結果から、日本企業でもインナーコミュニケーションを強化する動きが加速しましたが、未だ発展途上といえるでしょう。
日本企業で社員エンゲージメントを高めるために
エンゲージメントは何か施策を投じたからといって、ただちに向上するものではありません。
一度施策を行って効果が感じられないからといって、施策をストップさせてしまうと、社員の不信感を招き、かえってエンゲージメントが低下してしまいかねません。
本章では【外的】【内的】のアプローチを紹介しますが、いずれも1回の施策で完了するものではありません。
だからこそ、本章をヒントにしながら最終的な理想系を描くことを推奨します。
理想像がクリアになっていれば、その状態に到達するまで、何度でも必要な施策が考えられるでしょう。
自律・分散型の組織をつくる【外的アプローチ】
職能資格制度に代表されるように「人材を固定して、そこに職務を割り当てる」制度では、組織内に存在する社員の力量や人数によって、ジョブが増えたり減ったりしてしまいます。
自律・分散型組織を目指すためには、職務の「可視化」と、組織の「流動化」が条件となります。
具体的には、経営課題を解決するために必要なタスクを洗い出し、すべて職務にひも付けます。さらに職務ごとの仕事内容を明文化・可視化し、経営戦略を実行する上で必要な職務を定めて組織をつくります。
その上で、会社に存在する職務に対して、適切な人材を割り当てていくのです。
このことで、一般的なメンバーシップ(職能資格)型と対称的に、職務が固定され、人材は流動的な状態となります。
組織の中で対応できる能力が足りなければ、従業員のスキルアップをはかったり、新規採用を強化したりするなど、適切な対策を打ちます。
健全な代謝のなかで、しなやかな組織である状態を目指すことができるでしょう。
挑戦と成長を促すコミュニケーションを取る【内的アプローチ】
ジョブをベースとした組織を整えたら、次に取り組むべきはその運用プロセスです。
前章で紹介したように、日本企業は歴史的にインナーコミュニケーションに力を入れてきませんでした。
その影響からか、インナーコミュニケーションを強化しようとすると「とにかく褒める」や「プライベートな会話を増やす」など、少々的外れな方向に行ってしまう企業も少なくありません。
先が見えないVUCAの時代では、既存のやり方を貫くままでは、勝ち残っていくことは難しいでしょう。
そのため社員には、今までと違うやり方を考える「挑戦」を推奨し、今の能力以上の仕事を担える「成長」を促す必要があります。
従来の人材育成では、社員に対して、基礎的なビジネススキル開発や、自社流のスキルや考え方を一律に鍛えるような形式でした。
エンゲージメントが高まっている状態では、社員自ら「もっと挑戦したい」や「もっと成長したい」という気運が高まっています。
そのため、人材育成や現場マネジメントのコミュニケーションも、あくまで社員の自律性を重視する必要があります。たとえば一律的な教育メニューの押しつけではなく、カフェテリア形式での教育メニューの用意などが効果的です。
タスクや職務の可視化も進んでいれば職務ベースでの必要スキルも提示できるため、社員のスキル開発の納得感や意欲も増すでしょう。
これらを通じて、社員は社外でも通用するスキルを得て、転職マーケットでの市場価値を高めることにもつながります。
自社で育った人材が流出するのは一見すると企業の損失のようですが、成長できる環境と実績があることは労働市場で評価されるでしょう。
これは人材を囲い込む以上に、事業を持続的に成長させる企業価値となります。自然と自律したプロフェッショナルが集まる、強い組織ができるのです。
まとめ:「優しさ」を乗り越える「強さ」へ
これまでの日本の組織は、「安定」や「優しさ」を重要視し、それらが実現する状態を理想としてきました。
例えるなら、年功主義や長期雇用を前提に、メンバーが固定された大きな家族のような組織です。
安定した環境の中で育てられ、守られた人材は、会社のために一生懸命働きます。人を軸に組織をつくる人事制度は、高度経済成長期からバブル期にかけては、効果的に機能してきました。
しかし新興海外ベンチャーが突然競合となる現代のビジネス環境では、「優しさ」だけでなく「強さ」も求められます。
経営ビジョン実現のための職務を主軸とした人事制度は、企業競争力という「強さ」は手に入りやすいでしょう。
と同時に、その「強さ」を「痛み」と感じる社員も少なからずいるかもしれません。
「痛み」を乗り越えるためには、社員の内側から湧き上がる「それでも自分が成長して、会社のビジョン実現を成し遂げたい」という想いでしょう。
冒頭でご紹介したように、従業員エンゲージメントはもともと「従業員満足度」から派生したような概念です。
ただしエンゲージメントは「社員のご機嫌取りをして満足してもらう」のようなゴールではなく、本来的には企業競争力の向上がゴールです。
そのゴールをしっかり見据え、社員とともに痛みを乗り越えてでも、強い組織を作っていける状態をぜひ目指してください。






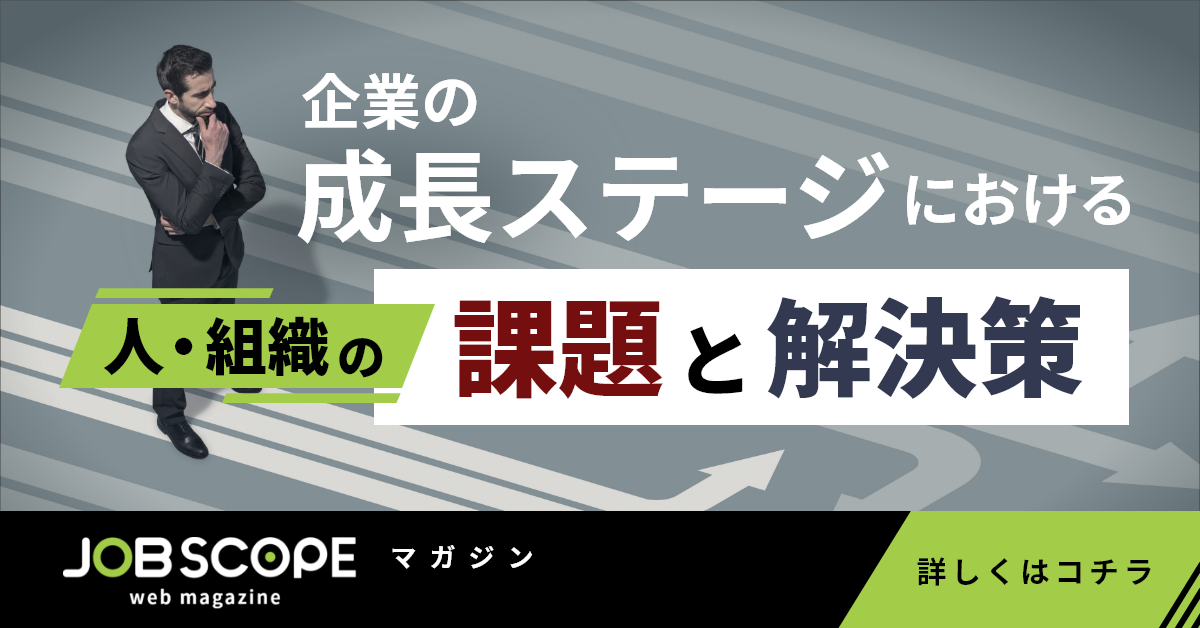




SHARE